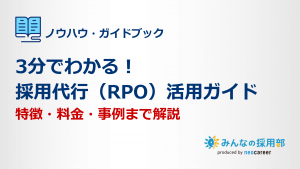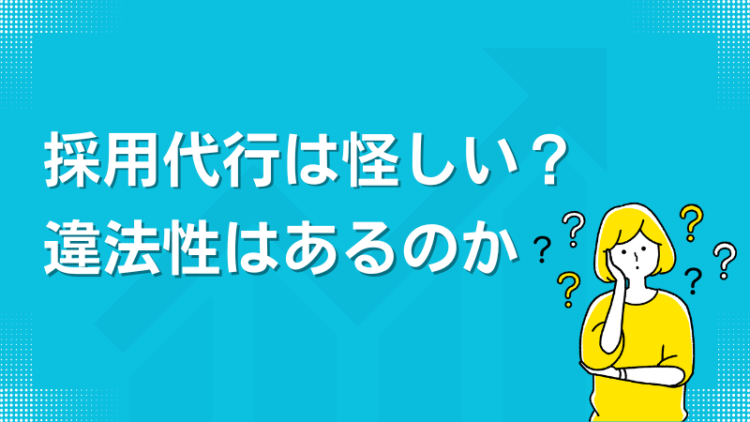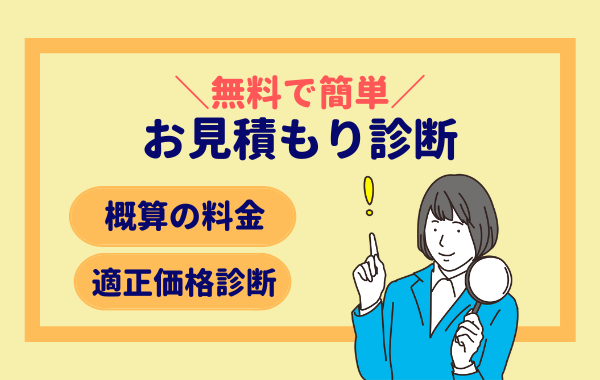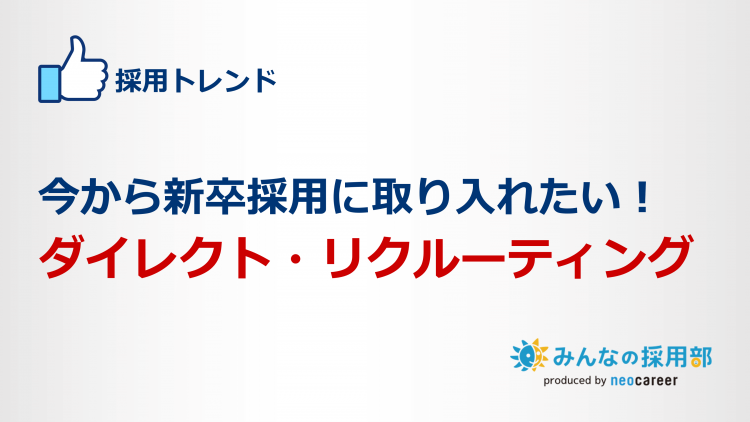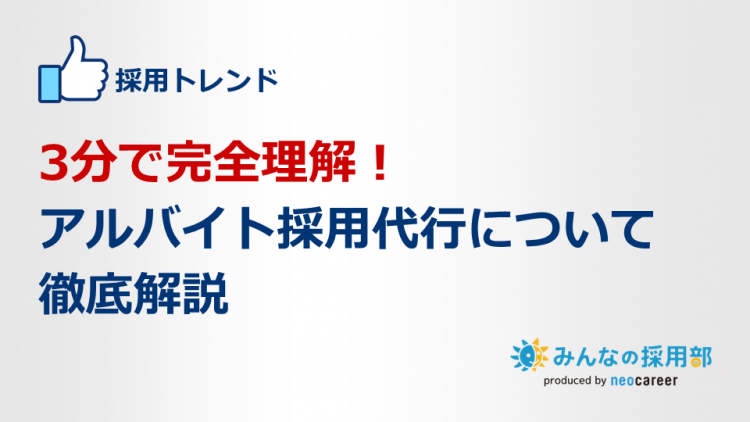採用代行(RPO)とは?|メリットや人材派遣・人材紹介との違いを解説
採用代行

売り手市場が続くなか、新しい採用方法も次々と出てきており、多くの企業が採用工数に課題を感じています。採用成功のために必要なリソースが自社だけでは補いきれず、採用活動に支障をきたしている企業も増えています。
そこで多くの企業が注目するようになったのが、採用代行(RPO)です。採用代行を導入すれば、自社のリソースを有効活用しながら採用活動を、効率的に進めることが可能です。
本記事では、
・そもそも採用代行(RPO)とは何か?
・採用代行(RPO)の業務内容やメリット・デメリット
・類似するサービス(人材派遣・人材紹介)との違い
を解説しています。採用代行を詳しく知りたい方は下記の資料もご活用ください。
目次
1.採用代行(RPO)とは

採用代行サービスとは、採用に関する業務を企業の代わりにおこなうサービスを指します。RPO(Recruitment Process Outsourcing)または、採用アウトソーシングと呼ばれることもありますが、言葉の意味としての違いはほとんどありません。
採用代行を導入すれば、採用活動のさまざまな業務を代行してもらい、自社は本来注力すべき重要な業務に集中できます。重要度の低い業務をアウトソースすることで、自社は工数のかかる作業をおこなわずに済み、効率よく採用を進めることも可能です。
1-1.採用プロセス代行型とリクルーター派遣型がある
採用代行サービスは大きく分けると、採用プロセス代行型とリクルーター派遣型の2種類に分類されます。
採用プロセス代行型は、採用に関係する事務業務を代行してくれるサービスです。一方、リクルーター派遣型は採用代行サービス会社から派遣された担当者が、企業(クライアント)に常駐し、採用に関する業務を代行・サポートするサービスです。
採用プロセス代行型は採用業務の負担を大幅に軽減できるため、多くの人員を必要とする企業に向いています。リクルーター派遣型は採用業務の詳細を都度確認できるため、密に連携をとりたい企業に向いています。
日本国内では採用プロセス代行型が主流ですが、近年はリクルーター派遣型を利用する企業も増加傾向です。どちらか片方を選択するのではなく、両方を導入するのも1つの方法です。
1-2.採用代行と人材派遣の違い
採用代行と人材派遣(採用業務が得意な人材を派遣してもらう場合)の大きな違いは、企業側が業務に関する指示を、その都度おこなう必要があるかないかです。
採用代行の場合は代行をおこなう担当者に関する指示・管理もすべて採用代行会社がおこないます。一方、人材派遣の場合は、企業側が派遣された担当者に対して業務の指示をおこなわなくてはなりません。
そのほかの料金や契約期間、教育の有無に関しても違いがあります。採用代行サービスの料金は委託料を契約時に決めて業務を遂行しますが、派遣社員の場合は時間給や日給など担当者が働いた分だけ支払うのが一般的です。
契約期間については、採用代行であれば自由に決められます。人材派遣の場合は長期契約が主流ですが、派遣社員を受け入れられる期間は原則3年と定められています。教育の有無に関しては、採用代行の場合は必要ありませんが、派遣社員の場合はケースバイケースで必要になることもあるでしょう。
1-3.採用代行と人材紹介の違い
採用代行と人材紹介の大きな違いは、人材確保の方法やサポートの範囲にあります。採用代行の場合は求人媒体の活用や直接応募者への対応などさまざまな方法で人材の確保をおこなうのに対して、人材紹介の場合は基本的に人材紹介会社の登録者のなかから人材を確保します。
また採用代行であれば、採用計画や母集団形成のサポートなど、採用に関わるさまざまな業務を代行可能ですが、人材紹介の場合は候補者を探して推薦し、入社までをフォローするサービスであって、そのほかの業務については対応しません。採用代行と人材紹介の違いについてさらに詳しく知りたい場合は下記の記事を参考にしてみてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
1-4.採用代行(RPO)が注目される理由
採用代行が注目される理由の1つは、近年、採用市場において売り手市場が続いていることが深く関係しています。複数の企業からのオファーを受けるような優秀な人材を確保することは難しくなっており、多くの企業が採用活動に力を入れています。
従来の採用方法では期待した結果が得られなくなり、多様な採用手法を駆使することにより、企業の負担が増加しているのも注目される理由の1つです。
また、現在企業が求める求職者は待ちの採用では集まらないケースが多く、自社の魅力を伝えるためのアプローチをしていくなどの攻めの採用をおこなう必要性があることも起因しています。複雑で高度な採用業務の効率化を進めるため、採用代行(RPO)を活用しようという流れが加速しています。
2.採用代行(RPO)は怪しい?違法性はあるのか
採用代行は職業安定法に基づき、厚生労働省や都道府県労働局長の許可が必要になる業務ですが、許可をとった上で採用代行会社に依頼するならば違法ではありません。
採用代行に関する法律 |
(委託募集)第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (権限の委任)第六十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。 |
出典:e-GOV 法令検索「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)」
許可をとっているにもかかわらず違法となるケースとしては、実際と異なる条件を求人内容に記載した場合(労働基準法に違反)や、応募者の個人情報を本人の同意なく第三者に共有した場合(個人情報保護法に違反)などがあげられます。
違法となるリスクについては、採用代行を依頼する会社に対して事前に確認しておきましょう。優良な採用代行会社であれば丁寧に説明してくれるはずです。
2-1.委託側と受託側の両方が許可基準を満たす必要がある
採用代行は法律上(職業安定法)の委託募集に該当します。委託募集をおこなう際には、委託側(企業)と受託側(採用代行サービス会社)の双方が、許可基準を満たす必要があります。
経験豊富な採用代行会社であれば、厚生労働省か都道府県労働局長に申請し、許可を取る手順についても精通していますので、まずは利用するにあたっての準備について相談することをおすすめします。
2-2.許可がいらないケースもある
利用する採用代行サービスの内容によっては、厚生労働省や都道府県労働局長の許可が必要ない場合もあります。たとえば企業側で面接や募集をおこない、採用試験の問題作成・実施を採用代行会社に委託する場合は、委託募集に当てはまらないため、許可は必要ありません。
3.採用代行(RPO)の業務内容

採用代行サービスの業務内容は、採用計画から母集団形成、応募者の管理から面接、採用選考、内定後のフォローなど多岐に渡ります。
すべてをまとめて任せることも可能ですが、部分的に代行を依頼することも可能です。たとえば採用面接に集中するために、応募者の管理やフォローを採用代行に委託するのも良いでしょう。
すべてをお任せする場合は、統一感を持った採用を実行することができますので、自社にノウハウがない場合やより質の高い採用を求める場合に向いています。
3-1.採用計画/企画
採用計画とは、採用活動のガイドラインのようなものです。「どのような人材を」「何人」「いつまでに」採用するのか、「どうやって採用するか」「面接回数や選考基準をどうするか」などの目標を設定することを指します。
採用計画は、人材を適切に採用・配置することで事業を成功させることを目的としているため、事業計画とのすりあわせが不可欠です。そのため、採用代行に採用計画や企画を委託した場合、まずは企業が抱えている悩みや要望をヒアリングからはじまり、課題解決に向けた業務フローを提案し構築していきます。
採用計画に問題があると、人材が確保できない場合や、人材が確保できても思っていた人とは違うことに不満を感じる場合がありますので、納得がいくまで採用代行とすり合わせをおこないましょう。
求人の即時募集だけでなく、会社が目指す方向にどのような組織を作るべきかを踏まえ、中長期的な採用ニーズの理解も必要です。優秀な人材を確保し人手不足を回避するために、適切な計画を立て、それに沿った採用活動を進めていくことが重要です。
3-2.母集団形成
採用活動には母集団形成も重要です。母集団とは、人材を採用するための候補者のグループを指します。母集団を形成するためには、自社に関心のある人材を多数集める必要があります。
母集団を形成するためには、自社との相性が良い求人広告選定や自社の魅力を伝える効果的な原稿、興味を持ってもらいやすいスカウトメールの作成などをおこない、応募者を効率よく獲得していかなくてはなりません。
優秀な採用代行会社は、年間数百社以上のアウトソーシングを請け負っています。その年間支援企業社数分の採用ノウハウを保有しているため、自社のニーズに沿った求職者を引きつけ、母集団形成の効率向上が期待できるでしょう。母集団形成について詳しく知りたい場合は、下記の資料をご活用ください。
3-3.応募者の管理/スクリーニング
採用角度を上げる一つの方法として、応募数を増やす方法があります。しかし応募が集まるほど、書類選考の選定にはかなりの時間がかかるでしょう。
採用代行では、自社の採用基準を共有することで、応募者のスクリーニングを依頼できます。スクリーニングとは、多くの応募者の中から、自社が求める人材を選び、絞り込むプロセスを指します。
ほかにも応募書類の収集や管理、応募者からの問い合わせ対応など、応募・選考に関する各種連絡業務を委託することが可能です。このような事務的で面倒な業務をアウトソースすることで、自社では重要な採用業務に集中できるでしょう。
3-4.採用選考
採用選考は、応募数が多いほど付随する業務に時間がかかります。合格・不合格の通知やWebテストの実施、成績管理や面接日程の調整など、直接の意思決定につながらない管理業務をアウトソースすれば、自社は面接での選考に集中できるため、自社に最適な人材を見つけやすくなるでしょう。
面接や採用選考をアウトソースすることも可能ですが、自社にそぐわない人材の採用を避けるため、面接や採用選考などの重要な業務を委託する場合は、事前の打ち合わせを念入りにおこないましょう。
採用代行では、応募者への迅速かつ丁寧な対応が可能なので、「採用担当者に連絡が取りにくい」「合格・不合格の連絡が遅い」などの理由による選考辞退を防ぐことにも繋がります。
3-5.内定者のフォロー
内定者のフォローも重要な採用業務の1つです。近年、応募者の選考社数が増えたことによる内定辞退が増えています。そのため、内定者への対応をおろそかにしていると、優秀な人材は他社へと流れてしまい、機会損失になりかません。
自社で応募者に定期的な連絡を取り続けることは、容易なことではありません。工数がかかった末に辞退されるケースも多いです。一方で採用代行を利用すれば、内定から入社までの長い期間、定期的な連絡での惹きつけをおこなうことが可能です。自社への興味が保たれ、辞退者を減らすことに繋がるでしょう。
とくに新卒採用の内定者フォローは非常に重要な課題であるため、豊富な経験を持った採用代行にアウトソースすることで、課題解決につながります。
4.採用代行(RPO)のメリット

採用代行のメリットは、採用担当者の負担軽減や採用コスト軽減、採用活動の質向上や採用候補の人数が増えることなどがあげられます。採用代行を通じて採用プロセスを学ぶこともできます。それぞれのメリットについて詳しく説明しますので、参考にしてみてください。
4-1.負担が軽減される
採用代行を利用することで、応募者を社内で管理する手間を削減できます。
とくに面接スケジュールの調整、申請書類の管理、応募者への連絡などの工数を必要とする日々の業務をアウトソーシングできれば、重要な業務にのみ集中でき、仕事の質の向上にもつながります。採用業務の効率化を図れば、必要な人材を短期間で採用できるでしょう。
採用担当者の負担を減らす方法について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
4-2.採用コスト削減に繋がる
増え続ける採用業務に対応するためにリソースを増やす方法もありますが、多くの場合、従業員数を増やすよりも採用代行にアウトソーシングする方が安く済みます。採用のノウハウが豊富な採用代行にアウトソーシングすることで、採用活動全体の合理化が図れ、採用コストの削減が期待できるでしょう。
採用コストを削減するためには、自社の採用課題に合わせ業務の一部だけをアウトソーシングしたり、繁忙期にのみアウトソーシングしたり、自社に合った使い方を見つけることが重要です。
採用活動の効率化や経費削減について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
4-3.最適な採用手法により採用活動の質が向上する
採用代行の利用は、専門的な観点から採用できることも大きなメリットです。採用代行は各種企業の採用活動の経験を持つスペシャリストであり、各社の採用課題に応じて最適な採用方法を選択し、実施できます。
実績のある採用代行会社ほど、さまざまな業界や職種での知見があるため、成功事例をもとに自社に最適なプランニングをおこなってくれます。最新の採用情報やトレンドも把握しているため、時代の変化に合わせて流動的な採用活動をおこなえるでしょう。
採用活動の質の向上は、選考辞退・内定辞退を減らすことにも繋がります。選考辞退を減らす方法や内定辞退を減らす方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
4-4.専門性の高い採用プロセスが学べる
採用代行の採用手法は、さまざまな職業や業界の採用実績にもとづいているため、採用代行から提供された客観的なアドバイスやノウハウを自社に取り入れることで、自社の採用力の強化を期待できます。
たとえば効率的な業務フローや、求職者を惹きつけやすい求人の原稿やメール文なども学べます。とくに導入社数の多い採用代行を選べば、多くの成功事例の中から最も効果的な、採用課題の解決に向けた提案をおこなってくれるでしょう。
初めての採用活動で方法がわからなかったり、今までの採用活動に行き詰まっていると感じた場合は、見本として採用代行を利用するのも1つの方法です。
4-5.採用成果を可視化できる
採用業務を採用代行にアウトソーシングすると、社内の従業員のみで採用する場合よりもコストの結果を管理しやすくなり、採用パフォーマンスを視覚化するのが容易になります。費用対効果が明らかになれば、自社が次のステップに進みやすくなり、より効率的な採用活動の推進につながるでしょう。
採用の成否が事業の成長に影響を与える時代になりつつあり、採用活動=営業活動といえますので、採用成果の可視化により管理しやすくなる点は、採用代行を利用する大きなメリットの1つです。
4-6.採用担当者が不在でも適切な採用活動ができる
採用担当者が退職してしまったり、そもそも採用担当者がいなかったりして、採用活動に力を入れていなかった場合でも、採用代行サービスを利用すれば適切に採用活動をおこなえます。
採用代行会社から採用計画・企画や母集団形成の方法を学びつつ、採用選考に集中するのも良いでしょう。採用代行会社によっては面接のノウハウを持ち、アドバイスや代行をおこなうことも可能です。
事前に自社で不足している知識・経験をまとめ、採用代行会社に相談してみるのも良いでしょう。
4-7.採用候補の人数が増える
採用代行会社の利用により、母集団形成や採用活動の質が向上すれば、自然と応募数も増えます。採用代行会社に応募者や内定者のフォローを依頼すれば、リマインド通知や複数回のメール・スカウトなどをおこなってくれて、選考辞退や内定辞退も減るでしょう。
採用代行により時間の余裕ができれば、求職者の惹きつけなどに力を入れることも可能で、さらに採用候補が増える可能性があります。
5.採用代行(RPO)のデメリット

採用代行を導入することへのデメリットはありますが、いずれも対策可能です。ほとんどのデメリットは準備不足などによって生まれるものなので、採用代行を導入する前に把握しておきましょう。
とくに事前に業務範囲や求める人物像を決めておく必要がある点や、選ぶ採用代行会社によって差が出てしまう点については、依頼前の準備でほぼ解決できます。
5-1.事前に業務範囲や求める人物像を決めておく必要がある
自社がどの業務をアウトソーシングしたいのかを事前に決めておかないと、採用代行の導入前におこなう、要件のすりあわせに工数がかかってしまいます。採用代行の導入前には必ず委託したい業務範囲や求める人物像などを事前に決めておきましょう。
採用課題の解決のために、効率的な提案をおこなう重要な作業ですが、採用業務を早く開始してほしい場合は、できれば時間をかけずに導入できるのがベストです。
採用代行会社によっては、事前準備の段階からサポートが可能なので「そもそも、業務範囲や求める人物像をどうやって決めていけば良いのかがわからない」という場合は、採用代行会社のサポートを受けながら慎重に決めていくことをおすすめします。
業務開始前に綿密な業務フローの確認をおこなわないと、何かあるたびに採用代行会社からの確認作業が入り、その対応にも自社の工数がかかってしまいます。工数を削減するための採用代行(RPO)なので、事前の要件のすりあわせの前に、まず自社でも業務のフローを確認しておきましょう。
5-2.採用代行(RPO)の選び方によって結果に差が出る
採用代行をおこなう企業は増えてきていますが、もともと採用関連の仕事をしていたわけではなく、まったく別の分野でアウトソーシングしていた採用代行会社もあります。
知識や経験が乏しい採用代行会社に採用代行を任せてしまうと、採用課題が解決できなかったり、採用担当者の負担が軽減されなかったりして、費用相当の効果を感じられないかもしれません。
採用代行の利用に伴う成果や信頼性は、どれだけ多くの採用業務をおこなって、成功事例が蓄積されているかが大きく影響します。また、採用代行会社によっておこなえる業務や得意分野も異なるため、どのような採用代行会社を選ぶかはとても重要です。
採用代行会社を選ぶ上で迷ってしまう場合は、いくつかの採用代行会社に見積り依頼を出し、提案内容や費用を比較すれば、それぞれの採用代行会社のメリットやデメリットを判断しやすくなるでしょう。
5-3.情報共有が不十分だとミスマッチが発生する
採用代行会社との情報共有が不十分だと書類の審査や面接、合格/不合格の決定の際に、自社の要件を満たしていない人を選んでしまうリスクがあります。
とくに、面接や選考など採用に関わるコアワークをアウトソーシングする場合は、事前に採用基準や条件について慎重に検討する必要があります。できれば余裕をもって情報共有をおこないたいところなので、できるだけ早く採用活動の準備をはじめた方が良いでしょう。
急ぎの場合は、採用代行会社と打ち合わせをする前に自社が求める採用基準や条件などをあらかじめ決めておくと、採用代行との情報共有もスムーズにすすみます。
5-4.応募者とのコミュニケーションが不足しやすい
採用代行会社に任せる業務範囲によっては、応募者・内定者とのコミュニケーション不足になりやすく、選考辞退や内定辞退に繋がる恐れがあります。コミュニケーション不足を解消するためには、選考以外をアウトソーシングする、面接時に同席するなどが効果的です。
コミュニケーション不足の回避を意識しつつ、どこまで委託すべきかを採用代行会社と相談しながら決めるのも1つの解決策です。
5-5.情報漏えいのリスクがある
採用代行会社の不手際が原因で応募者の個人情報などが流出してしまった場合、自社のイメージが大きくダウンするだけでなく、責任問題に発展するかもしれません。優良な採用代行会社であれば、個人情報の保護を徹底しているはずですが、契約前に確認しておきましょう。
SLA(サービス・レベル・アグリーメント)を締結し、個人情報の取り扱いについてルールを決めておくのも1つの方法です。採用代行のメリットとデメリットについてさらに詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
6.採用代行(RPO)の導入が向いている企業
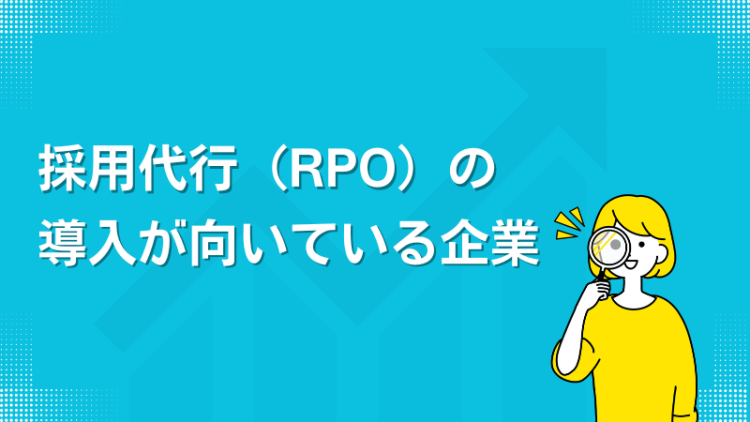
採用代行の導入が向いている企業は主に、人手不足や担当者の業務過多などのリソース不足か、辞退率の改善や応募数の増加など採用に関するスキル不足を解決したい企業などです。何かしらの採用課題を抱えているなら、採用代行は最も良い解決策です。
6-1.採用業務をできる人がいない・ノウハウがない
採用業務を任せる人材が不足している場合も、採用代行を依頼すればすぐに解決するでしょう。
- ・繁忙期で人手が足りないため、一時的に人手が必要になった
・コア業務に集中して採用力を上げたい
・戦略立案にリソースを割けない
・募集ポジションが幅広い・採用ボリュームが大きい
採用代行の導入が増えている要因の1つは、企業の採用活動に関連する仕事の量が増え、複雑化しているからです。たとえば採用方法1つをとっても、直接採用や紹介、ダイレクトリクルーティング、SNS採用など、採用チャネルが多様化しています。
人材紹介会社や求人広告・施策ごとに管理業務が必要になるため、既存の方法では対応しきれない企業は採用代行を導入する傾向にあります。採用代行を活用すれば、一部または一時的に業務を任せることで、リソース不足が解消されます。
6-2.選考・内定辞退率を改善したい
選考・内定辞退を防ぎ、優秀な人材を確保するために、ノンコア業務を採用代行にアウトソースし応募者や内定者フォローに注力する企業が増えています。
- ・掲載している求人広告が多く、対応業務だけで一日が終わってしまう
・応募者対応ばかりを優先し、面接の準備などに時間が割けない
・内定者のフォローなど、本来時間をかけたほうが良い業務に時間をかけられていない
・応募者受付・面接日程調整で取りこぼしが発生している
・採用を急いでいる(遅れによる選考・内定辞退率を改善したい)
採用業務にはコア業務とノンコア業務、2つが存在します。コア業務とは、企業の基礎を形成する業務で、利益を上げるための直接作業です。採用業務でいえば、採用戦略の立案や面接、応募者とのコミュニケーションなどが相当します。
一方でノンコア業務とは直接作業を支える業務で、利益を生まない関節作業のことを指します。ノンコア業務は難易度が低く高度な判断は不要である場合がほとんどです。採用業務でいえば面接の日程調整や問い合わせ対応、通知の作成・送付や、各種データ入力などが相当します。
ノンコア業務が遅れるとコア業務が妨げられるため、ノンコア業務にある程度の時間を割く必要があります。ノンコア業務を採用代行会社に委託すれば、本来注力すべき面接や惹きつけなどのコア業務に取り組めるでしょう。
6-3.欲しい人材が採用できない
自社が求める人材が採用できず、採用代行に委託する企業もあります。
- ・求人は出しているが欲しい人材からの応募が来ない
・初めての採用で何から始めたら良いかわからない
・特殊な職種なため、どの求人広告を利用したら良いかがわからない
企業間の人材競争が激化しており、求職者に自社をアピールするための「採用ブランディング」などの採用力強化の施策が重要になっています。採用能力を強化するためには、人員や時間だけでなく、採用分野に関する深い知識やノウハウが必要です。
このような背景の中、採用の専門家である採用代行に採用業務をアウトソースすることで、採用力を強化したいという企業が増えています。一時的に採用代行を利用し、今後の自走を見据えてノウハウの吸収に努める企業も珍しくありません。
6-4.求人を出しても応募が少ない
さまざまな方法で求人を出しても、応募が少ないと自社が求める人材に出会える確率は低くなるうえコストがかさむ一方です。
- ・応募数が少なく、採用業務が行き詰まっている
・自社の魅力が伝えられず、母集団が集まらない
・多くの人材紹介会社に依頼している
自社の求人に関心があり、応募する可能性のある方々を母集団と呼びます。母集団の形成は、採用業務で十分な結果を出す上で重要な課題であり、自社にあった対策が必要です。
多くの採用代行会社は、母集団形成のプロフェッショナルであるため、母集団形成に関する戦略の立案や実行を任せれば、応募数もおのずと増えてくるでしょう。採用力を高めるための方法を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
7.採用代行(RPO)を選ぶポイント・注意点
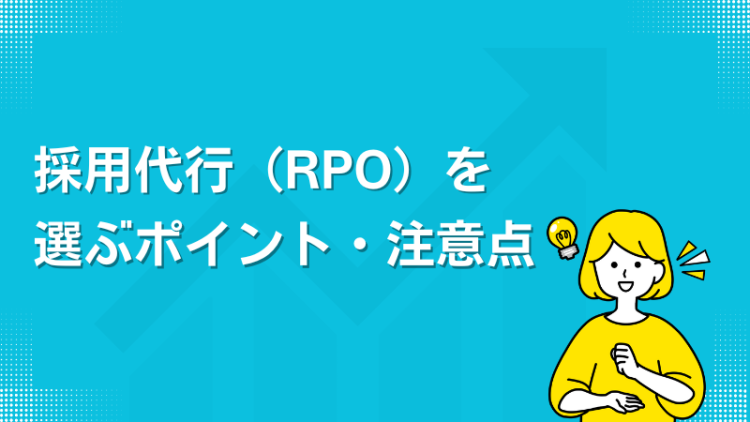
採用代行を選ぶポイントや注意点を5つ紹介します。いずれも重要なポイントなので、採用代行会社と契約するまえに確認しておきましょう。ポイントや注意点を確認せずに委託してしまうと、思わぬトラブルを招く可能性が高くなります。
7-1.採用代行の対応範囲や実績を確認する
契約前に自社が求める業務が対応範囲に含まれているか、実績があるのかを確認しておきましょう。採用代行会社によって、得意分野や対応可能な範囲が異なります。採用代行会社に直接問い合わせる場合は、実績に関する証拠や事例の提出を求めると安心です。
7-2.情報共有の方法や頻度を確認する
情報共有不足や進捗状況の確認のために、情報共有の方法や頻度を確認しておきましょう。明確なルールを決めておけば、採用活動の把握も容易になります。契約前に委託中のリポートがどのようなものになるか、サンプルを見せてもらうのも良いでしょう。
7-3.機密情報の扱い(セキュリティ)を確認する
人事情報や応募者の個人情報などの取り扱い方法やセキュリティ体制を確認しておきましょう。万が一流出してしまった場合はどう対処するのかも確認しておくと安心です。機密情報の取り扱いに関して明確なルールを決めるべく、SLA(サービス・レベル・アグリーメント)を締結しておけば、情報漏洩のリスクも抑えられるでしょう。
7-4.業務範囲と責任の明確化
採用代行に委託する業務範囲と責任を明確化することで、業務の振り分けに関する認識の違いから起こるミスを防げます。曖昧なままだと、採用代行に委託したと思っていた業務が一切進行せずに、期限間近になって気づくというような事態が起こりえます。
7-5.採用のパートナーとして考える
採用代行の委託先を単なる外注先や下請け業者ととらえるのではなく、2人3脚で採用課題を改善するパートナーとして考えると、より上手く活用できるでしょう。委託するだけではノウハウの吸収などのスキルアップが難しくなりますが、パートナーとしてとらえれば今後の自走も早期に実現できます。
8.採用代行(RPO)の費用相場

採用代行の費用相場は、委託範囲や料金タイプによって大きく異なります。採用代行の料金タイプは大きく分けて「定額制」「成果報酬制」「従量単価請求制」の3種類あります。
8-1.定額制
定額制は月ごとの料金が決まっているタイプです。費用相場は40~50万円前後ですが、委託する範囲が小さければ10万円~20万円におさめることも可能でしょう。
8-2.成果報酬制
成果報酬制の場合は、あらかじめ決めておいた成果を達成した場合に費用が発生する仕組みです。ほかの料金体系よりも割高な傾向にあり、相場は60万円~120万円程度です。
8-3.従量単価請求制
従量単価請求制は、最も普及している料金タイプで、業務量に応じて費用が変動します。たとえば「採用媒体の管理:10万円」「面接代行:1万円(1回)」といった具合です。相場は業務量によりますが合計10万円~70万円程度です。
料金体系 | 特徴 | 費用相場 |
定額制 | 月ごとに一定の料金が決まっている | 40~50万円前後 |
成果報酬制 | 成果を達成した場合に費用が発生する | 60万円~120万円程度 |
従量単価請求制 | 業務量に応じて費用が変動する | 10万円~70万円程度 |
採用代行の費用について詳しく知りたい場合は、下記の資料をご活用ください。
- あわせて読みたい記事はこちら
- 【比較表あり】最新の採用代行(RPO)45社丸わかり!料金相場・特徴・選び方も解説
9.採用代行の活用事例

採用代行(RPO)を利用したことで採用成功につながった事例を、新卒採用と中途採用で1つずつ紹介します。
9‐1.新卒採用の活用事例(不動産)
求める人材 | ・新卒採用 ・営業職 |
従業員数(サービス利用前) | 10名程度 |
採用課題 | はじめての新卒採用でやり方がわからない |
利用したサービス | 採用戦略の立案/採用手法・媒体の選定/選考フローの設計など新卒採用全般のコンサルティング |
はじめての新卒採用でノウハウ不足が主な課題でした。告知の方法から選考フローまで全てゼロから構築する必要がありました。就職サイトの活用だけでなく、会社説明会も実施し、結果的に6名の採用に至りました。
9‐2.中途採用の活用事例(エンジニア)
求める人材 | ・IT知識が豊富で、エンジニアとしての経験がある ・エンジニア業務経験だけでなく、お客様とのコミュニケーションが取れる |
従業員数(サービス利用前) | 30~50名 |
採用課題 | ・母集団形成 ・採用マンパワー不足 ・採用サイトの情報が更新できていなかった |
利用したサービス | ・採用アウトソーシング ・スカウト代行サービス ・採用サイト制作 |
将来の事業拡大を見据えた大量採用を計画しており、母集団形成が課題となっていました。さらに人手不足により、日々の採用活動や情報の更新などに十分に時間を割くことができていませんでした。採用代行(RPO)を利用したことで人事担当者の負担が大幅に減り、コア業務に集中できるようになりました。
結果的に、面接とカジュアル面談を毎日のように実施することで多くの応募が集まり、内定出しも順調に進んでいます。
10.まとめ
採用代行(RPO)は、自社の採用課題の解決のために、代わりに採用業務をおこなってくれる採用のプロフェッショナルです。採用代行にアウトソーシングする最大のメリットは、工数のかかる管理業務をアウトソーシングすることで、重要な業務に集中できることです。
採用に関するノウハウ不足が発生している場合も、採用代行(RPO)から学ぶ事で、多くの知識と経験が得られるでしょう。採用課題を解決し優秀な人材を確保するために、上手く採用代行(RPO)を利用しましょう。みんなの採用部では採用代行のご相談について無料で承ります。気になる方は下記ページをぜひご覧ください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る