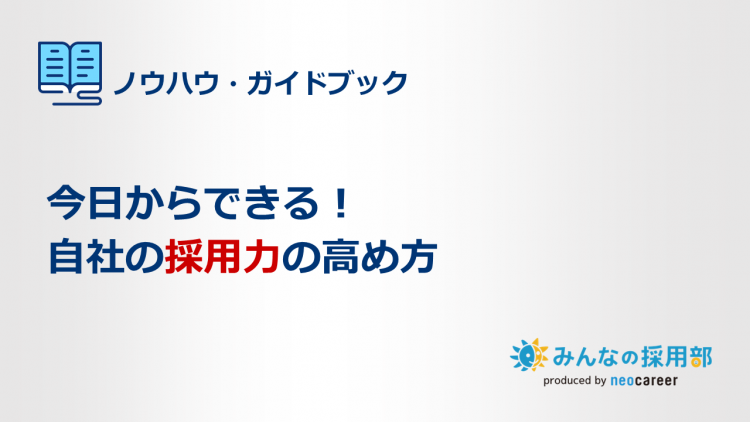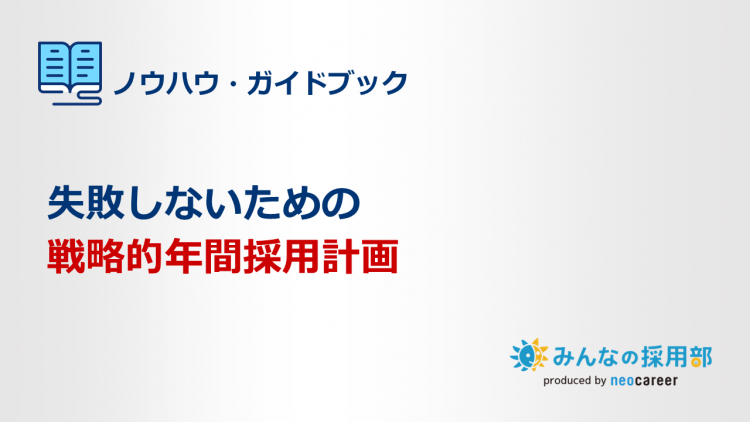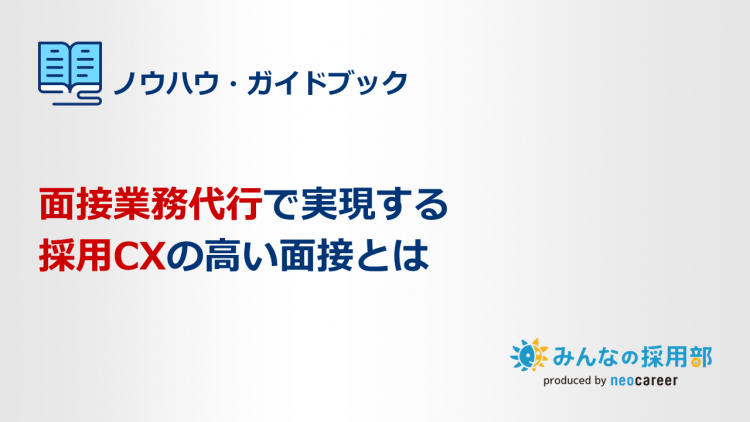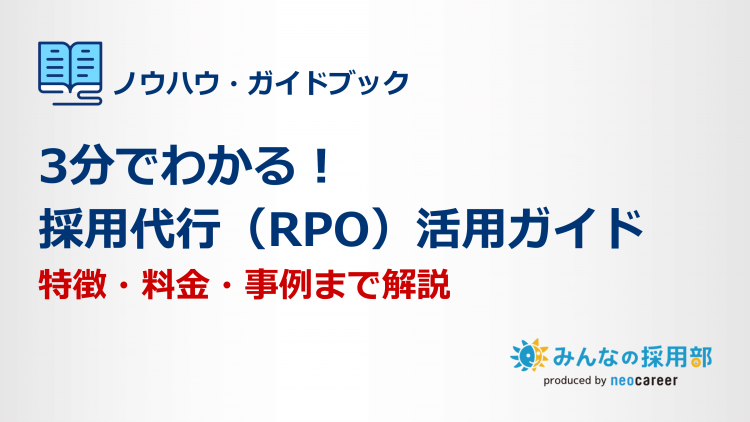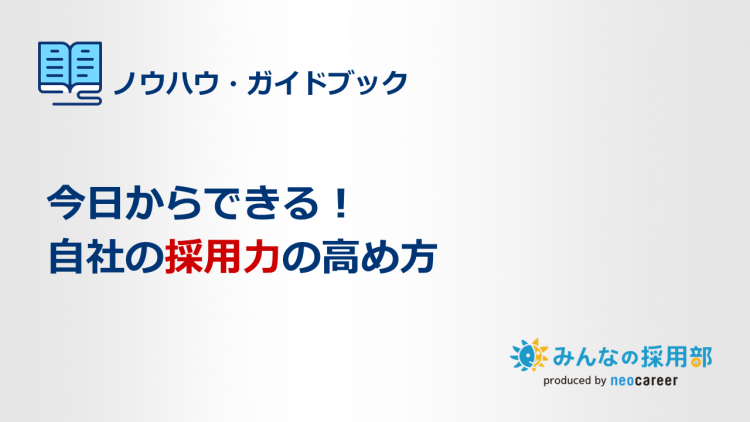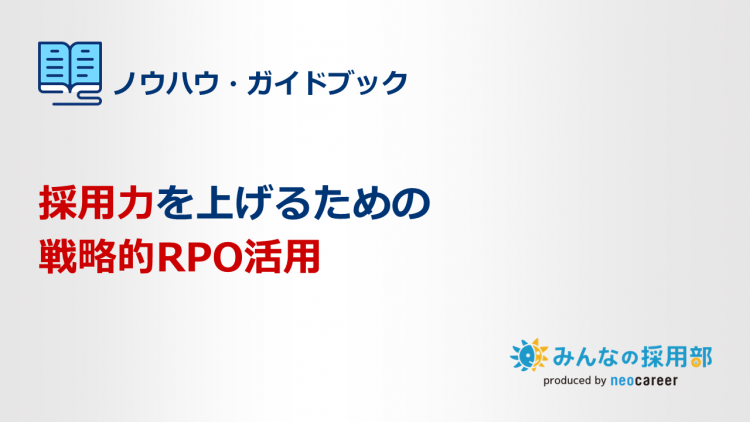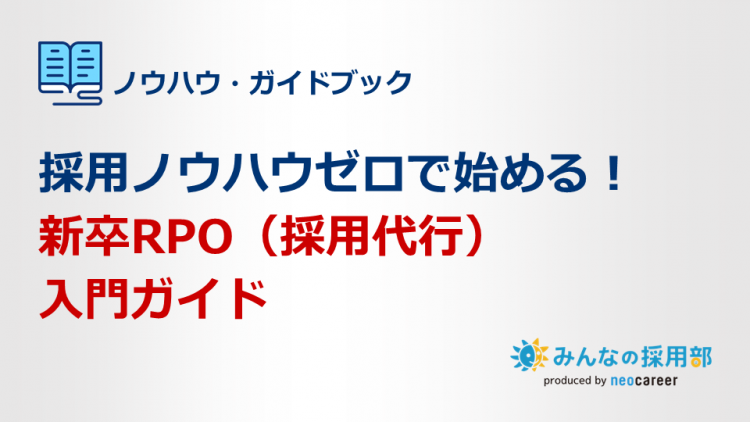採用力とは?採用を強化する必要性とポイントを解説|採用力が高い企業の共通点も紹介
採用力
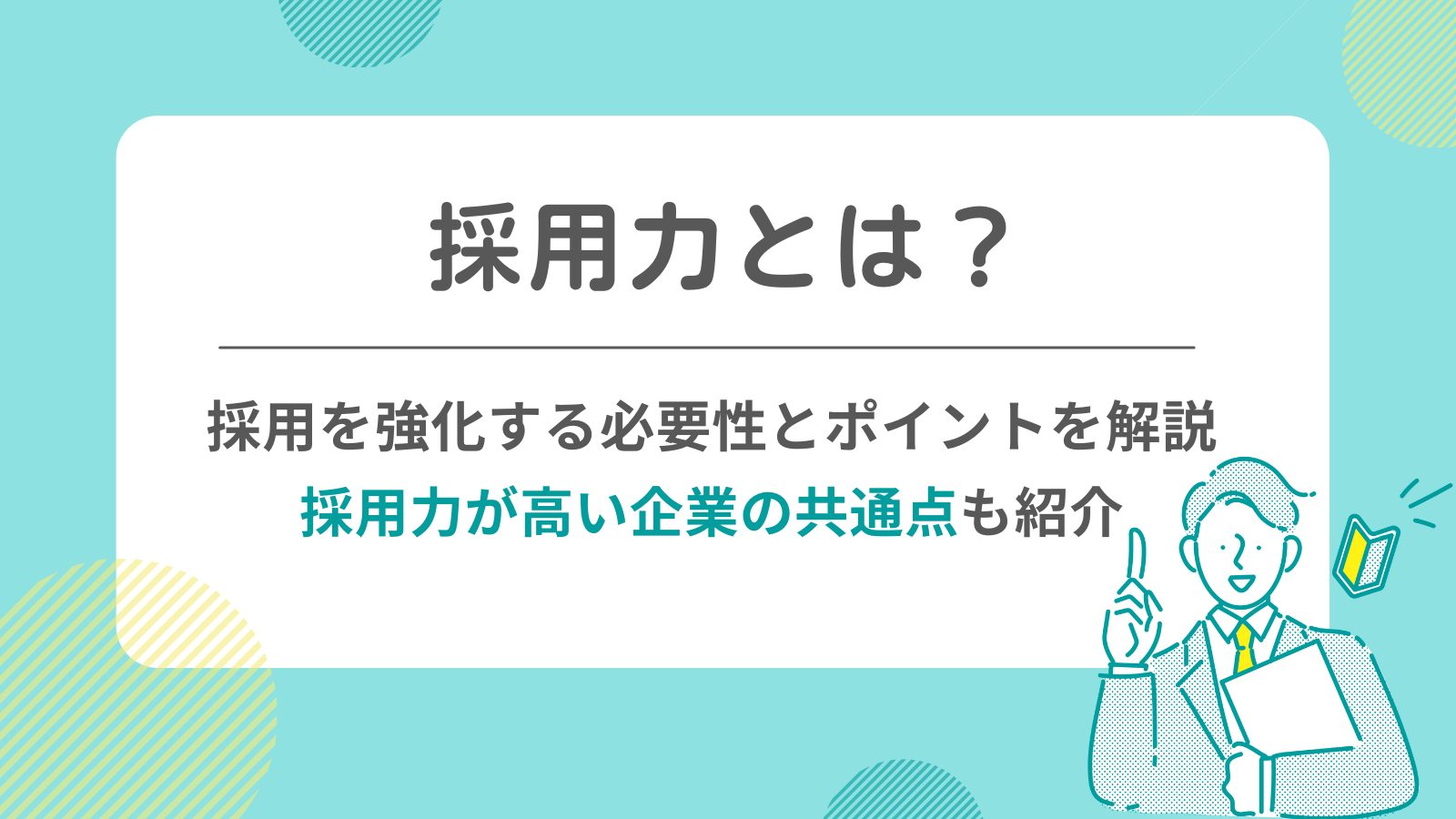
企業は採用力を強化することで、計画に沿った採用や求める人材の確保ができます。持続的に会社を発展させていくために、採用力を強化しましょう。
本記事では
・採用力とは何か
・採用力を高めるためのポイント
・採用力が高い企業の共通点
についてご紹介します。
なぜ採用の強化が必要なのか、強化するためのポイントなど参考にしてください。
1.採用力とは
採用力の定義はさまざまですが、自社にとって必要な人材を適切に採用する力のことと言えるでしょう。必要な期間までに必要な人数を採用できる企業は採用力があると言えます。
また、一般社団法人日本採用力検定協会によると、採用力は「組織および社会に有益な採用活動を設計・実行する力」を指すと言われています。
以下は採用力の5つの要素です。
要素 | 内容 |
パースペクティブ | 採用に対する視座 |
マインド | 採用に向き合う姿勢 |
ナレッジ | 採用を良くするための知見 |
スキル | 採用を良くするための技能 |
アクション | 採用における意思決定 |
採用力を強化していくためには、採用の質の向上や採用目標を達成させるための知識やスキルを学ぶことが必要です。採用力は知識の習得や経験によって身に付く力と言えるため、自社の状況や採用トレンドを把握しながら採用成功につなげていきましょう。
出典:一般社団法人日本採用力検定協会「採用力検定について」
2.採用力の強化が必要な理由
少子化による労働人口の減少により採用母数の確保が困難になったため、企業は人材確保のために他社との差別化をする必要が出てきました。また、働き方の多様化により採用力の強化がさらに求められるようになりました。
以前の日本であれば新卒一括採用の終身雇用が一般的でしたが、現在の日本では終身雇用は崩壊しつつあります。そのため、1つの企業に定年まで勤め上げるという求職者の意識は薄くなっています。転職を最初から視野に入れている求職者に対して、長い期間勤務する価値があることをアピールするためにも、採用力の強化が必要だと言えます。
3.採用力を向上させるポイント
採用力はどれか1つを強化すれば効果が現れるものではなく、包括的に強化していくことが大切です。まずは、自社にはどこに改善の余地があるか、どこからなら取り組めそうか確認しながら読み進めてください。
3-1.採用計画の設計
採用力を向上させるポイント1つ目は、採用計画の設計です。なぜ採用をおこなうのか、何人採用する必要があるのか、いつまでに完了させる計画なのかを明確化しましょう。さらに、求める人材の要素は何か、採用にかかる費用はいくらかも決めます。その結果、自社の状況を把握でき、採用の基礎ができあがります。
採用の基礎があることによって自社の状況が把握でき、競合他社の比較が可能になります。さらに求める人材像が明確になるため、そのターゲット層をより多く獲得するための手法や媒体などを取捨選択するための情報収集もおこなうことになります。このように採用設計に必要な知識を学んでいくことで、自然と採用力も強化されます。
さらに、詳しく採用計画の目的、立て方、見直し方法を知りたい方は、こちらを参考にしてください。
3-2.採用市場・採用トレンドの適切な理解
採用力を向上させるポイント2つ目は、採用市場・採用トレンドの適切な理解です。採用業界のトレンドは常に変化しています。とくに現在であれば、ダイレクトリクルーティングにより、企業側から求職者に直接コンタクトを取る形が一般化されました。
こうした時代の変化に乗り遅れることなく、トレンドを適切に理解することで応募者数の確保や求職者への適切なアプローチが可能になります。採用市場・採用トレンドを読み解くことで、自社のターゲットが多く集まる場所を見抜けるようになります。その結果求めている人材を獲得できる可能性が上がり採用力が強化されます。
3-3.競合他社の調査・分析
採用力を向上させるポイント3つ目は、競合他社の調査・分析です。採用活動をするにあたり、競合他社の調査・分析をすることで自社との採用状況を比較が可能です。そして競合他社と比較することで、客観的に自社の強みや弱みを見つけられます。その結果、同じターゲット層を狙っている企業と比較して自社はどこをアピールしたらよいかなど戦い方がわかってきます。
調査と分析を怠ると、なぜ競合他社にのみ応募が集まるのかがわからず、採用力を強化するために必要なデータが不足します。しっかりと競合他社の調査・分析を行い、自社の優位な点や自社にしかない魅力をアピールして求める人材を獲得し、採用力の強化につなげましょう。
3-4.採用基準の明確化
採用力を向上させるポイント4つ目は、採用基準の明確化です。採用には経営幹部、人事、現場社員など多くの人が携わります。しかし、誰が面接担当者になっても同じ採用基準で判断しなければなりません。
採用基準がない場合、その日の気分や、見た目、直感といったあいまいな基準で採用・不採用の判断を下すことになります。採用基準を明確化させることは、求める人物像がブレることを防ぎ、採用力の強化につながります。その結果、採用計画通りの人材が集まり、想定している活躍をしてくれるでしょう。
3-5.採用CXの設計
採用力を向上させるポイント5つ目は、採用CXの設計です。労働人口の減少により、採用の母数を確保することが困難になりました。その結果、応募数増加を狙いつつ採用途中での辞退を防ぐ目的で、採用CXを設計する企業が増えました。とくに面接の採用CX向上は重要視されます。なぜなら、面接は求職者にとって企業を判断する大きな要素になるからです。
採用CXの設計を適切におこなうことで、求職者が面接を受けて良かったと感じるようになります。その結果、選考辞退者が減少し欲しい人材が獲得しやすくなります。面接における採用CXについて知りたい方は、こちらを参考にしてください。
3-6.採用力検定の受験
採用力を向上させるポイント6つ目は、採用力検定の受験です。優秀な人材を確保するためには、採用担当者も優秀である必要があります。期日までに必要な人数をそろえる行動力や求職者の性格や特性を見抜く力など、さまざまなスキルが求められます。
採用力検定を受験することで、採用に必要なスキル、知識、姿勢、行動力などを包括的に学ぶことができます。自分で勉強するため時間とお金はかかりますが、今後のキャリアにも役立つ知識が学べ、よりよい採用を続けていくことに役立つでしょう。採用担当者のスキルが向上することで、優秀な人材を見極められるようになり採用力の向上につながります。
3-7.自社に適した採用手法の選定
採用力を向上させるポイント7つ目は、自社に適した採用手法の選定です。企業に合った採用手法が何かを知っておくことは大切です。採用手法は、求人広告、自社サイト、企業説明会、ダイレクトリクルーティングなどさまざまです。
それぞれの手法における特徴や強み、弱みを把握しておき、自社のターゲットやペルソナにはどの手法や媒体があっているのか判断できるようにしておきましょう。例えば、求人広告であれば採用母数は確保できますが、ある特定のスキルを持った人材を採用することには向いていません。
一方、ダイレクトリクルーティングは企業側から気になった人材に直接アプローチができるので、採用したい職種やスキルが固まっている場合は有効ですが、採用数が多い場合はタイムパフォーマンス的に向いていない手法です。このように採用手法の特徴を理解し適切に選択することで、求める人材が的確に獲得でき、採用力の向上につながると言えます。
3-8.外部サービスの活用
4.採用力が高い企業の共通点
採用力の高い企業は、自社の状況をしっかり把握できており、かつ情報が統一されています。さらに経営幹部、人事部、現場の認識のすり合わせができていることも多いです。
本章では採用力の高い企業にみられる8つの共通点をご紹介します。
4-1.自社独自の情報を発信している
採用力が高い企業の共通点1つ目は、自社独自の情報を発信していることです。現在の企業の多くは、Instagram、YouTube、Xなど情報発信する媒体をいくつか持っています。
以前であれば自社サイトなど限られた媒体でしか発信する場所はありませんでした。しかし、現在はターゲットに合わせたSNSで適切に発信を行い、自社の魅力をアピールできます。
こうした活動は競合他社との差別化になり、求職者にとっても判断材料になるため採用力を高める上で重要です。
4-2.情報発信に一貫性がある
採用力が高い企業の共通点2つ目は、情報発信に一貫性があることです。自社の魅力を発信するにあたって、ターゲットが選定されていなかったり、ストーリーがなかったりすると、求職者に魅力は伝わりません。誰に向けて発信し、どのように受け取って欲しいのか、どういう行動を促したいのか明確にすることで、初めて情報発信に一貫性が生まれます。
さらに情報発信にストーリーを持たせることで、受け手側に共感してもらうことができ、企業に親近感を持ってもらえます。自社の情報をたくさん発信したい気持ちはわかりますが、一貫性を保つために届けたい情報はしっかり選定しましょう。
4-3.採用担当者の認識が統一されている
採用力が高い企業の共通点3つ目は、採用に携わるメンバーの認識が統一されていることです。採用には多くの人が携わります。採用担当者ごとに面接で伝える情報が違ったり、求めている人材の認識が違ったりすると、最初の計画を達成できなくなるでしょう。
また、認識が統一されることでチーム全体の連携が強化され、一体感が生まれます。採用は時間とお金がかかる大きな業務です。既存社員に帰属意識が生まれることで共通の目標や価値観を持って業務できるようになります。
さらに、採用に携わるメンバーごとにバラバラの情報を伝えてしまうと、求職者は混乱し不信感を持ってしまうかもしれません。専門的な業務内容でないかぎり、誰に質問がきても同じ回答ができるように認識を統一させましょう。
4-4.自社にあった方法で採用している
採用力が高い企業の共通点4つ目は、自社にあった方法で採用していることです。採用を始める前に、まずは採用ペルソナを明確にしておきましょう。例えば若手の人材が欲しいのか即戦力が欲しいのか、その理由はなぜかということをしっかり分析します。
ペルソナをもとに採用計画を立てることで、若手が必要であれば20代が多いサイトに求人を出したり、即戦力を求めるのであれば人材紹介会社に依頼したりと、適した方法が選択できます。このように、求める人材ごとに適した方法を選択することで、計画に沿った採用ができ、採用力が向上します。
4-5.現場との連携が取れている
採用力が高い企業の共通点5つ目は、現場との連携が取れていることです。採用担当者は求職者と接する機会が多いため、採用担当者の意見に採用の判断が左右されます。しかし、採用した人材が現場の求める人材でないことが往々にして起こります。
そうした採用ミスマッチを防ぐためにも、現場との連携が取れていることが大切です。現場が求める人材像はハイスペックになりがちですが、近年の採用市場ではそのような全てを兼ね備えた人材を見つけることは困難です。
そういった際にどこのポイントを優先させるのか、妥協できるポイントはないか、しっかりコミュニケーションを取って決めておきましょう。こうした関係性を普段から築いておくことで、スムーズな連携が可能になります。
4-6.候補者への対応スピードが速い
採用力が高い企業の共通点6つ目は、候補者への対応スピードが速いことです。候補者は自社以外にも多くの企業に応募しています。そのため、対応スピードを速くすることで熱量を持った状態で選考に進んでもらうことができます。
もし対応が遅くなってしまうと、自分はそれほど期待されていないと感じたり、選考に落ちたと判断されたりして歩留まりが悪くなってしまうため注意が必要です。
4-7.応募管理体制が整っている
採用力が高い企業の共通点7つ目は、応募管理体制が整っていることです。求職者とのやり取りは企業を代表しているという意識が必要です。そのため、応募管理体制を整えておかなければなりません。
応募管理ができていないと、求職者からの連絡を何日も返していないなどという問題が起こってしまい求職者の信頼を失いかねません。また、応募管理体制が整っていることで、採用状況の把握や分析が可能になります。雑な管理方法では貴重なデータを生かすことができないため、注意しましょう。
4-8.採用データを蓄積している
採用力が高い企業の共通点8つ目は、採用データを蓄積していることです。データがあることで求人広告に掲載した場合、ダイレクトリクルーティングを行った際の反響率などを比較できます。
データを比較することで課題把握が容易になり、改善するきっかけになるでしょう。また、採用データが蓄積するほど自社の強みや弱みがわかります。このようなデータがあることで、他社との差別化を図るヒントにもなります。
5.採用力を強化する際の注意点
採用力を強化する際に、採用担当者の負担が増えすぎないように注意しましょう。採用にはさまざまな要素が絡み合っています。やれること全てを取り入れようとすると採用担当者にばかり負担がのしかかります。
採用担当者は幅広い業務を担当しますが、何かを新しく取り入れるためにはタスクの優先度を決め採用業務にあたることが重要です。全てをこなそうとすると、かえって大切な業務に時間を割くことができなくなります。
採用に関してどうしても人手や時間が足りない場合は、採用代行(RPO)を選択するのも1つの手です。採用代行については下記資料も参考にしてください。
6.採用力の強化に成功した企業事例
採用力の強化に成功した事例を2つ紹介します。
6-1.freee株式会社
freee株式会社は、リファラル採用を取り入れたことで、価値観を共有できる質の高い人材の採用に成功しました。とくにQA(Quality Assurance : 品質保証)チームはリファラル採用で採用の拡大に大きく貢献しています。
リファラル採用とは、既存社員が新しい人材を推薦する採用方法です。既存社員が社風や価値観をあらかじめ伝えてくれるため、入社後に訪れる認識のズレを防ぐことが可能です。また、企業側も推薦者のスキルや経験を把握しておけるため、入社後に適正のあるポジションに配置できます。
このようにリファラル採用を活用することで、自社の社風に合う人材を効率的に採用できるため、採用力の向上につながった事例だと言えます。
出典:freee株式会社「QAドリームチームの野望──リファラル採用で集まった品質保証のプロ集団」
6-2.株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、採用CXに力をいれ採用力を強化させました。2018年ごろは採用の仕組みが整備されておらず、採用プロセスやシステムの使い方もバラバラでした。
その後、「世界に通用する企業を目標」に求職者1人ひとりを大切にする採用にシフトし、面接担当者は模擬面接に参加することで質の向上に努め、求職者に面接をして良かったと思われる面接作りに注力しました。
出典:株式会社メルカリ「メルカリの今昔“採用”物語を現役メンバーが振り返る #今メルカリが一緒に働きたい仲間」
7.まとめ

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る