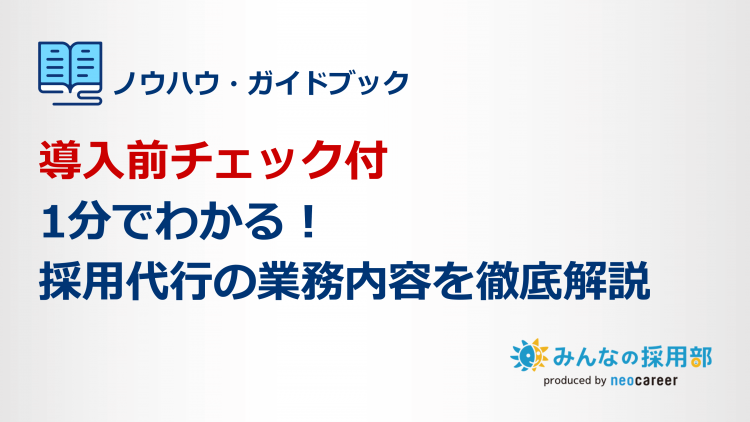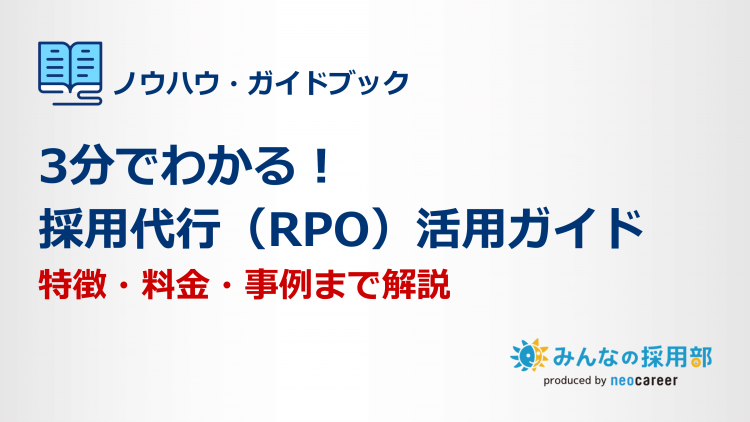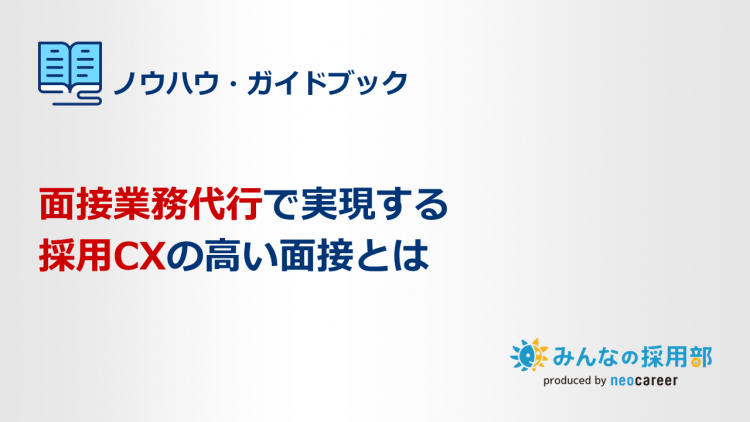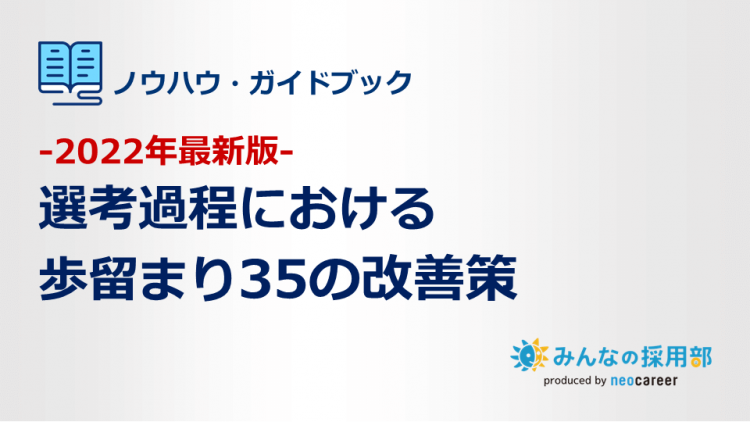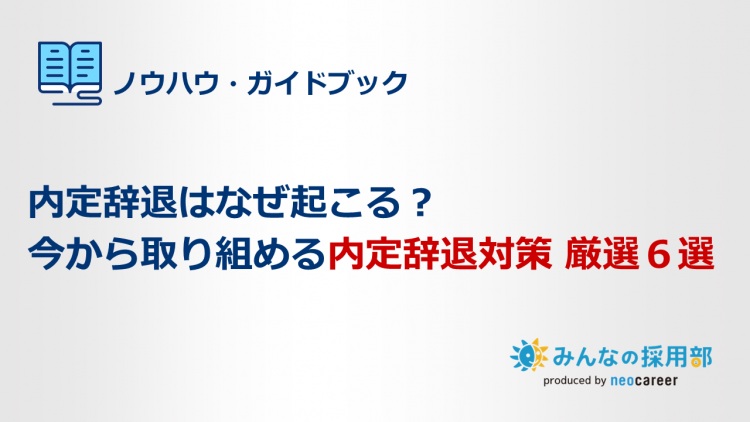選考辞退を防止するための対策は?辞退の原因を応募者側と企業側に分けて解説
選考辞退 防止
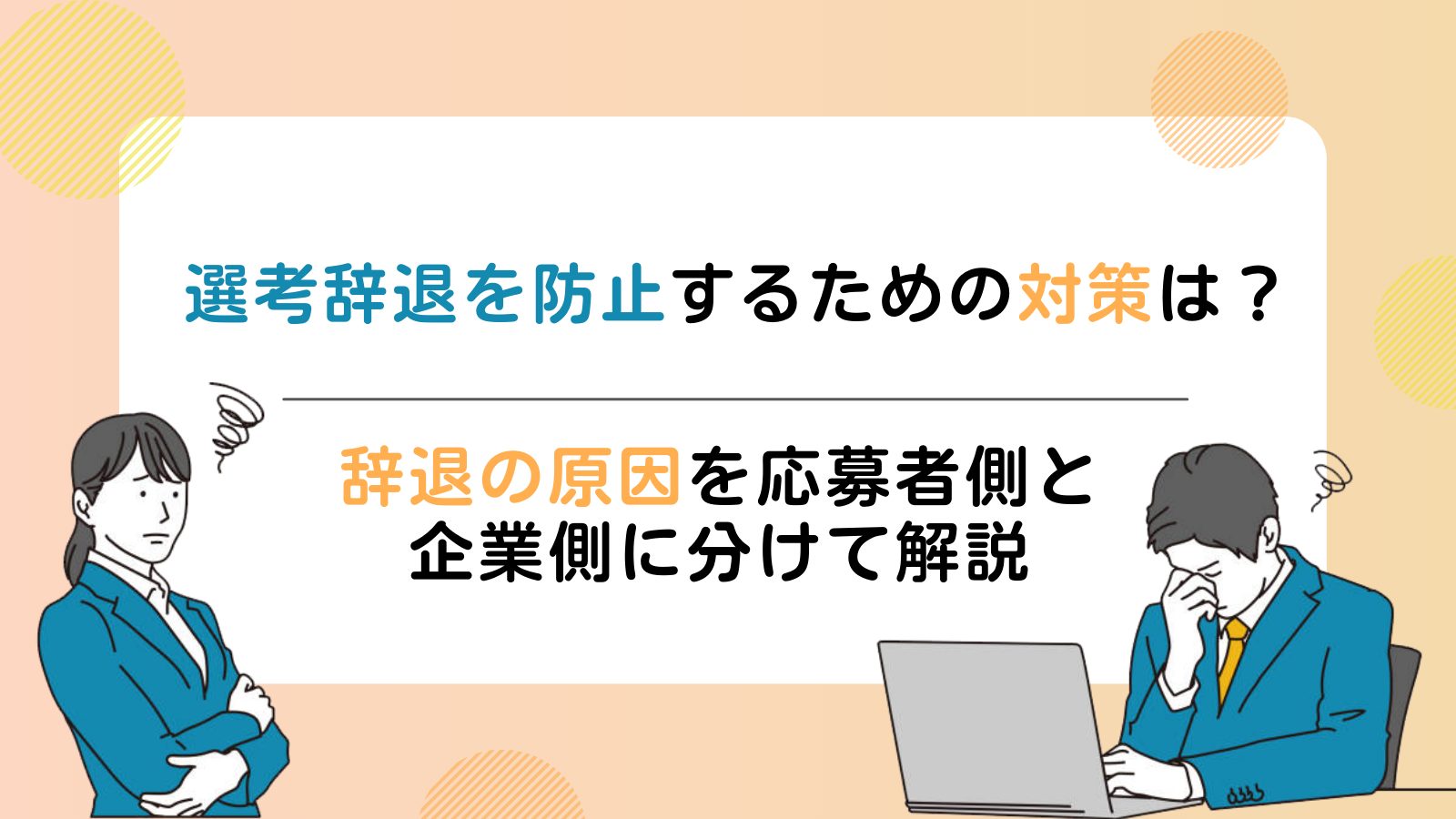
採用活動において「応募者が面接をキャンセルした」「選考中に連絡が取れなくなった」など、一部の応募者が選考途中で辞退することに悩んでいる採用担当者もいるでしょう。
選考の辞退を防止するためには応募者への対応方法を見直す必要があります。しかし、選考中の応募者や内定者が辞退をする理由がわからなければ、改善のしようがありません。
本記事では、
・選考辞退が増えている背景と理由
・企業側に考えられる選考辞退を招く原因
・選考辞退を減らすためにできること
についてご紹介します。
応募者が選考辞退する原因や、選考辞退を防止するためのポイントなどを説明していきますので、今後の採用活動にぜひ役立ててください。
1.選考辞退が増えている背景
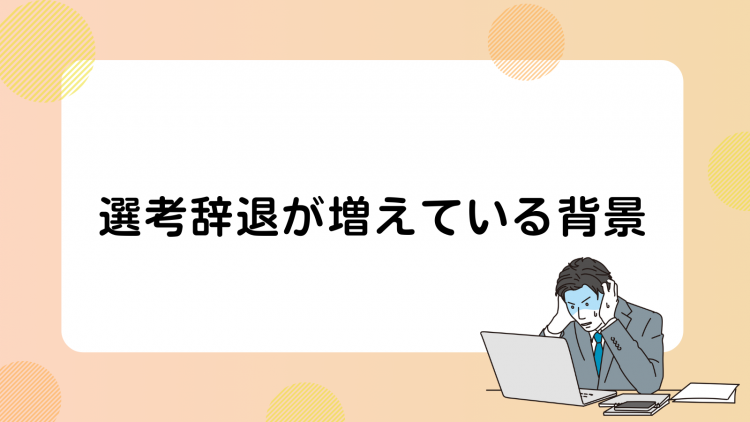
昨今では、採用のオンライン化によって企業と応募者のコミュニケーションが不足し、選考辞退が増加傾向にあります。対面でのやり取りでないと、応募者が企業に対して親近感や信頼感を持ちにくくなる可能性があると言えるでしょう。
オンラインでの応募は容易で、応募者が複数の企業から内定を獲得するケースもあります。応募者はより良い条件を求めてさらに応募を続け、最終的に他社からの内定受諾も増えていきます。内定受諾のタイミングによっては、自社の内定や、面接のタイミングに関係なく、選考途中で辞退することが多くなっているのです。
また、コロナ禍で採用を控えていた企業が、一斉に採用を再開したことで求人件数が増加しています。応募者が増えるとともに、選考辞退に悩む企業も増えているのです。
2.応募者側の選考辞退の理由
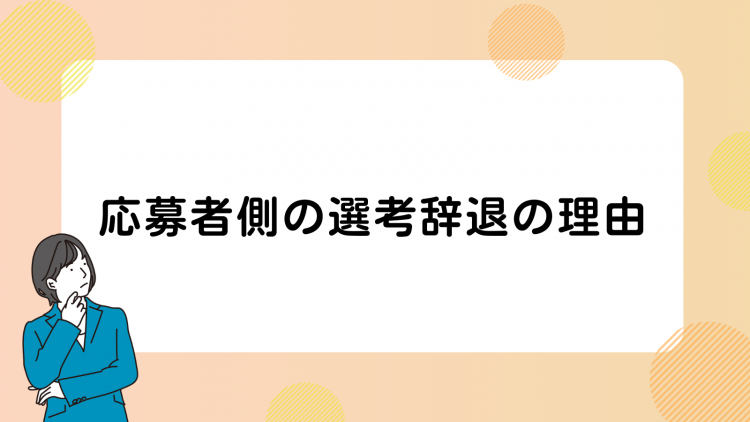
企業が選考辞退防止の対策をしていくためには、応募者はなぜ突然選考辞退をするのか、他社に魅力を感じてしまうのはどのような理由なのかを把握する必要があります。
本章では、応募者側の要因による選考辞退の理由を6つ紹介します。
日程が合わなかった
複数の企業に同時に応募している応募者は少なくないため、日程が合わず選考辞退することもあります。また、中途採用の場合は、仕事をしながら効率的に就職活動をおこないたいと試行錯誤している応募者も多いです。
そのため、他社の選考日程との兼ね合いが悪いと、選考辞退に繋がってしまいます。応募者の選考希望日時に合わせたり、選考日の選択肢を増やしておくなどの対策を講じましょう。
また、場合によっては、自身の体調不良といった不測の事態も起こり、企業への訪問が困難になることもあるでしょう。
面接回数が多いと現在の仕事の調整が難しいというだけで選考辞退に繋がる可能性がとても高くなってしまいます。まずは他社よりも早く選考を進め、内定を応募者に連絡するようにしましょう。
最近では、面接1回で採用を決める企業も見受けられます。1回の面接で決めるために社内での採用基準を明確にして、面接の回数を減らすだけでも選考辞退を防ぐ効果が期待できます。
仕事内容や条件が合わなかった
「採用のポジションがやりたい仕事ではなかった」「勤務時間、給与、福利厚生など条件が希望とマッチしない」など、条件の不一致で選考辞退に繋がるケースも散見されます。転職活動において、応募者が求める条件は十人十色です。
もし条件が満たされていて、応募者が同様の仕事内容で複数の企業に応募をしている場合は、条件がより良い企業を求めるのは当然のことです。他社がより良い条件を提示している場合、応募者の興味は自社から失せてしまうため、選考辞退や内定辞退に繋がってしまいます。
昨今は仕事内容や条件だけでなく、社会貢献活動や企業文化を重視する応募者もいます。 応募者のニーズを理解して応じていくと、条件の中で応募者の希望とマッチしない内容が少しあったとしても、選考辞退を減らすことができるでしょう。
条件が応募者の希望と完全に一致しない場合でも、仕事が面白い内容であったり、魅力的な企業であると感じてもらえたりすることで入社を前向きに検討してもらえる可能性があります。選考プロセスの中で、自社の魅力や採用への熱意がしっかり伝わったかどうかを振り返りましょう。
他社から内定をもらった
応募者が選考辞退をする理由の一つに、他社からの内定受諾があります。複数社から内定をもらえば、応募者はより魅力的な条件や企業文化を持つ企業を選ぶ傾向にあります。とくに、選考方法にスピード感がある企業は、応募者が信頼感や安心感を抱き、高く評価されやすいです。
逆に、選考が長引いたり返事が遅れたりすると、他社に気持ちが移りやすくなり、選考辞退の原因になりかねません。
そのため、企業は選考全体でスピード感を重視することが重要になります。例えば、面接日程を迅速に調整したり、合否連絡を早めにおこなったりすると良いでしょう。スピード感のある対応は、応募者に「この企業は私を本当に必要としている」と感じさせることができ、選考辞退への効果的な防止策となります。
入社後のビジョンが見えなかった
入社後のビジョンが見えないことで、選考辞退をする応募者もいます。なぜなら転職を検討する理由として、「仕事へのやりがい」を求めている応募者も増加してきているからです。
単純に仕事内容を伝え、少し高めの給料を提示するだけでは、応募者が他社を選んでしまいかねません。応募者は転職先に、給料だけではなく自身の成長とやりがいを求めている場合もあります。
応募者は、以下のように入社後の姿を考えます。
・仕事内容
・任される仕事
・仕事を任されるようになった先の可能性
・自分がこれから残す結果
・自分の将来的な成長
そのため、自身が考えていることをより魅力的に伝えてくれる企業への就職を決める傾向があります。
企業は、自社が求める人材に、自社の魅力をしっかり伝え、就職するイメージを明確にしてもらいましょう。
ネット上でよくない評判があった
ネット上で企業のよくない評判があったために、選考を辞退する応募者もいます。
例えば、社内の人間関係が悪い、給与や賞与が低い、または社内の雰囲気が悪いといった情報が広まっていると、応募者はその企業に対して不安を感じ、選考を辞退する場合があります。
ネット上での評判による辞退を防ぐためには、企業側が自社の評判を定期的に確認し、問題があれば早急に対策を講じることが重要です。ネット上の評判を軽視せず、積極的に対応することが、選考辞退を防ぐための有効な手段です。
転職活動をやめた
転職をするか迷いながら転職活動をおこなっている中、何らかの理由で転職をしないことを選択し、選考を辞退する場合があります。
時間がとれなかったり、今勤めている会社より条件の良い企業が見つからなかったり、など理由はさまざまです。現在の勤め先において、優秀な人材と考えられており、勤め先から辞めにくいような条件が出されたり、引き止められたりすることも当然考えられます。
応募者が転職を考えている間に、企業は時間をかけずに内定まで選考を進められるよう、スピード感をもって対応しましょう。
3.企業側に起因する選考辞退の原因
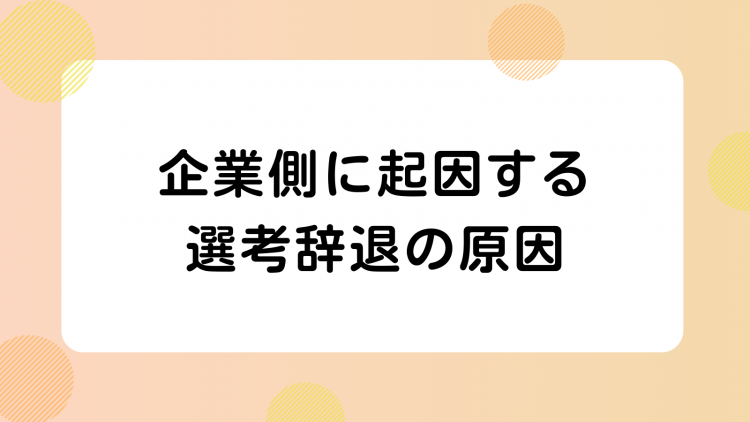
採用活動における選考辞退は、応募者側に起因するものだけではありません。
企業側が無意識のうちに選考辞退者を増やしてしまっていることもあります。本章では、企業側に起因する選考辞退の原因を4つ紹介していきます。
他社より選考スピードが遅い
面接の日程調整やメールの返信をできるだけ早くおこなうことが大切です。なるべく早く返信をすることで、応募者から信頼してもらえるようになります。
なぜなら、自社以外に複数の企業に対して、選考の応募をしている応募者は少なくありません。自社の都合を中心に考えて選考を進めていると、選考の合間に、応募者が他社で採用が決まってしまうことや、応募者の自社への興味が徐々に薄まってしまいかねません。
自社からの返信が遅い場合、応募者は返信が来ないストレスや不安から「応募したけど、きっと自分に全然興味を持ってもらえなかったのだろう」「きちんとしていない、雑でルーズな企業なのでは」と想像で決めつけてしまう可能性もあります。返信が遅いと、応募者が自社に対して抱く印象は急転して悪くなってしまうでしょう。
また、返信が遅い不安から、「返事は来ないかも」と待っている間に、諦めて他社に応募してしまうこともあります。応募者にとっては、たとえ第1志望でない企業であっても、対応が早かったことで信頼するようになり、良いイメージを抱いたまま入社を決める応募者もいるのです。
応募者は複数の企業に応募していることが多いため、可能な限りの早めの連絡が有利に働きます。応募者への返信は1営業日以内、遅くなるとしても2、3営業日以内にしましょう。選考結果連絡に時間がかかりそうな場合は、時間がかかる旨と目処となる日数をすぐに返信しておくと良いでしょう。
選考スピードを速くしたいけれども、応募者への対応が間に合わない、人手や経験値が不足していると感じる場合は、こちらの記事をチェックしてみてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
- 採用のプロがわかりやすく解説!
採用効率UPに繋がるプロのノウハウ!
・採用を強化したいが人手が足りない
・面接実施後の歩留まりが低下している
・面接の判断軸が定まっていないそのような人事担当者におすすめです!
採用課題の解決に繋がる資料をご確認ください!
求人広告の採用情報量が足りない
求人広告の内容は、競合他社と差別化できるように充実させましょう。なぜなら、応募する前に企業の転職サイトを確認しない応募者もいるからです。
応募者が複数企業に応募をしている場合は、企業の転職サイトではなく、まずは求人広告の内容を見て、興味のある企業を選んでいく傾向にあります。したがって、応募者が求人広告を見た時点で興味を持っていなければ、自社の転職サイトまでたどりつきません。
そして、誰もが転職の理由を明確にして行動しているわけではありません。「同僚が転職をした」「別の仕事をしてみたい」などの理由で、とりあえず求人媒体に登録する方もいます。求人媒体を眺めていたところ、関心のある企業を見つけたため転職しようと考えて応募した応募者も少なくありません。
また、企業の転職サイトを確認するタイミングは、 カジュアル面談で興味を持った後、という応募者も増加しています。競合他社より自社にしっかり興味を持ってもらえるよう、求人広告の情報は応募者が満足する量や内容を意識して用意しましょう。
面接官の対応や印象が悪い
面接官の態度や印象が悪いと、応募者が面接後に選考を辞退する場合があります。なぜなら、採用における面接は、企業が応募者の人柄などを判断するためだけの場ではなく、同時に応募者が企業を判断する場でもあるからです。
応募者は、今勤めている企業よりも、より良い企業を求めて、転職活動を進めていくので、不愉快な印象を与える面接官がいるような企業を選ぶ可能性は非常に低いといえます。 面接官は将来上司になる可能性もあるため、面接官に不愉快な対応や印象を感じれば、応募者が選考辞退するのはごく自然です。
面接官と応募者は、優劣なく、あくまで対等な関係です。 面接官が応募者に対して、優秀な人材かどうかを見極めて採用したいと考えるのと同じで、 応募者も採用してもらったら将来的に長く付き合っていける企業や社員であるかどうかを判断しようと考えます。
採用担当者は、応募者が求めている内容をしっかり聞き出し、提案や質問をおこなって応募者の満足度を高めましょう。また、給与面や残業といった応募者が聞きにくい内容については、自社から積極的に提供することで、好感度や信頼が増します。
応募者とのコミュニケーションが足りない
選考中、応募者とは可能な限り丁寧なメッセージや連絡をおこなうようにしましょう。応募者は、企業の採用担当者と実際に対面するまでは、送られてくるメールの内容が、そのまま企業に対するイメージとしてとらえる傾向にあります。
メールでやり取りする中、メッセージ内容で応募者に悪い印象を与えると、企業全体のイメージダウンに繋がりってしまいかねません。
たとえば、テンプレートを用いて、「応募いただきありがとうございます。」という決まりきったメッセージを送るのではなく、一人ひとりにきちんと対応するという小さなことが選考辞退の防止に繋がっていきます。メールでは単純な文面にはならないようにしつつも、読みやすく硬すぎない文章にするのが望ましいです。
4.選考辞退を防止するための対策11選
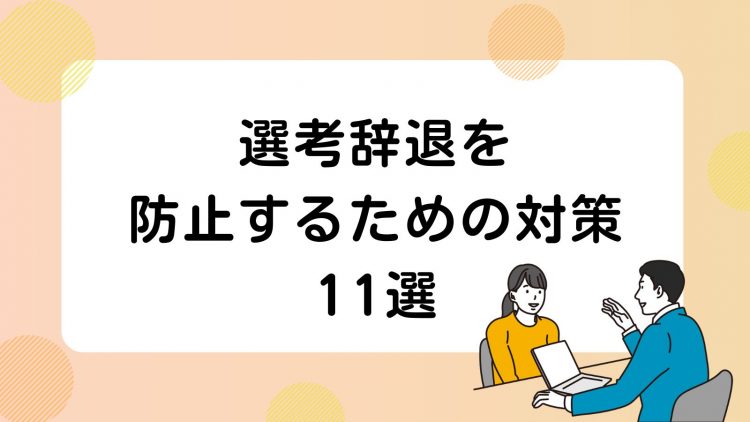
採用活動において、自社の望む人材を獲得できている企業にみられる特徴はどのようなものなのでしょうか。本章では、選考辞退を防止し、応募者に選ばれる企業になるための方法をご紹介します。
採用側が素早い対応をする
選考辞退を防止するために何よりも大切なのは、応募者へのスピード感ある対応です。応募者からの応募を確認したら、可能な限り早く返信することがとても重要になります。応募者からのメールの返信率の高い企業は、数時間以内に返信しています。
応募した後の応募者は、転職への意欲が非常に高い状態です。自社から送ったメールに対して、すぐに返信がくる可能性がとても高いのです。そこで「面接の候補日」をいくつか提示したり、応募者の面接の希望日を複数聞くことで、応募者の都合に合わせつつも、容易に選考のスケジュール調整が可能です。
また、選考日程が短いほど選考辞退者は少なくなっています。中途採用での転職活動の場合、2〜3ヶ月かかることもあるでしょう。しかし、応募から採用まで日数が経てば経つほど、応募者の自社への興味は減少していくため、内定を出すまでに面接を1回にする企業もあります。
もし、応募者からの問い合わせやメールに対してすぐに回答ができない場合であっても、応募に対する返信をすることで、応募者の転職意欲を高いまま維持してもらえます。迅速な対応を心がけることで、応募者の自社への信頼度を高められます。選考中における自社への興味を保ちつつ、選考辞退を防止するようにしましょう。
正確でわかりやすい求人情報を提供する
求人情報では、「給与」「昇給」「勤務時間」「福利厚生」など、求職者が興味を持ちそうな条件を伝えましょう。なお、正確に誤解のないよう、そして興味のありそうな順で伝えると良いです。
求人広告は、応募を考えている方が企業に興味を持った後に最初に目にするものです。入社後の具体的な情報が正確かつわかりやすく掲載されている求人情報は、 応募後のミスマッチを抑えられ、内定までの選考辞退を防ぐことに繋がります。
応募後のミスマッチが少ない企業の求人情報には、入社後の働き方をイメージしやすいように、自社の雰囲気や従業員の毎日のスケジュールといった情報が載せられています。
自社の魅力をイメージしてもらいやすくするために、社員の仕事風景や様子を動画で伝える企業も増えており、自社への応募者における選考辞退の割合を下げています。
たとえ魅力的な文章で興味を持ってもらえてたとしても、十分な職務情報を提供しないと選考辞退に繋がりかねません。求人情報の情報量が十分であることは非常に重要なポイントです。
転職活動をしている方は、仕事内容や企業情報、労働条件などの最低限の情報だけでなく、「対象となる人物像」「残業時間」「業績」といった求人情報に興味を持つことが多いです。
応募後、面接までの間に応募者の自社への興味を保てる魅力的な文章と、面接時にミスマッチを起こさない対策として、充実させた情報を掲載しましょう。
採用への熱意を伝える
応募者に対する期待を言葉で表わすことは、応募者の入社意欲を高めるのに効果的です。 「ぜひとも自社で働いてほしい」という想いを、応募者に対して個々に伝えることが非常に大切です。
応募者の入社意欲を維持できている企業は、応募者のどのようなところが自社にどう貢献できそうか、ということを個別に伝えています。個別に伝えられた応募者は、自分が応募先の企業に必要とされているとしっかり感じることができます。ここで大事なのは、自社からのオファーが応募者にとって特別である、という印象を持ってもらうことです。
選考プロセスの合間で、応募者のフォローをするのも良いでしょう。電話で応募者の現在の気持ちや状況をヒアリングし、いつでも相談や質問ができることを伝え、応募者に安心感を持ってもらいます。入社を歓迎していると応募者に感じてもらえたら、入社への不安も解消され、入社意欲の維持が期待できます。
面接前にはリマインドの連絡をする
面接の日程が近づいたら、メールと電話で連絡をしましょう。多忙な応募者の場合は、面接があることを忘れてしまうことがあります。事前に連絡することで、面接日時の再確認が可能であるだけなく、採用側の意欲ややる気も一緒に伝わります。
応募者の面接への参加率が高い企業にみられる傾向は、「面接でお会いできるのを楽しみにしています」というように、前向きな姿勢を見せていることです。あわせて緊急連絡先を伝えておくと良いです。応募者が急な体調不良や、急な仕事で面接に来れなくなっても、面接日程の再調整に繋げることができ、選考辞退を防止できるでしょう。
また、応募者に応じた連絡ツールを利用することもおすすめです。 電話番号に送信されるテキストメッセージのSMSは、配信率が非常に高いツールです。 メールの送信だけでは、メールの受信数が多すぎて自社のメールが見過ごされてしまう可能性もあります。メールだけでなく、SMSもあわせて送信しておけば、開封率が上がり、面接への参加率向上に繋がるでしょう。
Web面接と対面面接を選択可能にする
Web面接の活用は、応募者の面接の負担を軽減するためにとても効果的です。応募した複数企業で、面接スケジュールが重複してしまうと、応募者は志望順位の高い企業を選択します。応募者が志望順位の高い企業の面接を優先した場合、志望順位の低い企業は面接の機会を失い、面接前に応募者を逃すことになりかねません。
面接の日程をしっかり組めている企業は、応募者の希望に寄り添い、「Web面接」と「対面面接」のいずれかを選択できるようにしています。Web面接を併用することで、時間がない応募者も面接を受けることができます。また、地方や遠方からの応募者に対しても、遠方へ移動する負担をかけることなく、面接をおこなうことが可能です。
一方で、企業の社内や社員の雰囲気を知りたいと考えて、Web面接ではなく、対面面接を希望する応募者も多いです。「Web面接」と「対面面接」どちらでも選べるようにすれば、応募者を逃さずしっかりと面接予定を組むことができます。
採用担当以外の社員に面接時の対応方法を浸透させる
応募者の選考辞退を防止するためには、採用担当者以外の社員にも面接時の対応やマナーを周知徹底することが不可欠です。採用担当者以外の社員の対応や印象が重要になります。
応募者の来社時に、社員から積極的に関わることが好印象に繋がり、企業に良いイメージを持ちます。応募者は、入社後のイメージがわき、入社意欲が向上するでしょう。
逆に、不親切な対応や無関心な態度を取ると、企業全体のイメージが悪くなり、選考辞退の原因になることもあります。企業全体で応募者に良い印象を与える環境を作り上げることが、選考辞退を防ぐためには有効です。
面接では親身な対応を心がける
面接時は、応募者にしっかり興味をもって親切な対応をしましょう。応募者との共通点や、共感できるポイントを伝えることで、応募者は入社後をイメージでき、入社の意欲を高められるでしょう。また、応募者の知りたい情報に対して、全て丁寧に提示して答えることで信頼が増します。
応募者が選ぶ企業は、入社後の直接の上司や会社が、応募者に期待していることを伝え、応募者の希望や価値観と重なる自社の魅力を伝えています。多くの特徴や魅力を伝えることで、他社との差別化を図り、自社に興味を持ってもらえるような工夫をしているのです。
近年は、面接ごとに応募者へのフィードバックをしたり、応募時に一緒に働きたい理由をドキュメントで応募者に送るなどしている企業が、応募者から好印象のようです。
しかし、応募者からの質問に曖昧な答えを返すと、応募者からの信頼を失うことになります。就業規則や残業、給与や昇進についてなどの質問には、必ず明確に答えられるようにしておきましょう。応募者の満足度の高さが入社意欲に繋がりり、第1志望として考えてもらいやすくなります。
メッセージはカジュアルにする
近年のチャットツールの普及に伴い、硬い文面よりもカジュアルな文面や短く簡潔な文面が好まれる傾向にあります。
応募者が返信しやすいと感じる企業からのメールは、「明日の来社時は気をつけてください。」 「お気軽にご相談ください!」のように、優しい印象を与えられるような工夫がされているのです。
硬い文面にせず、優しい印象にすることで、返信や連絡のハードルが下がり、応募者からの返信率が上がる期待ができるでしょう。
面接ではなく面談を実施する
最近では、「面接」ではなく「面談」をおこなう企業が増えています。通常の選考における面接と比べ、応募者と企業の双方がリラックスして話せる「カジュアル面談」が設けられ、相互理解を深める場になっているのです。
選考辞退率が低い企業は、面談を通じて業務内容や企業文化を説明し、応募者の悩みをヒアリングすることで、応募者の不安を解消しています。
また、多くの応募者は、「面接」という言葉に不安を感じるため、「カジュアルな服装でもOK」とすることで、参加のハードルを下げ、面談の参加率を上げることにも成功し、自社を知ってもらうための機会にもなっているのです。
面接に代わる実践型研修をする
面接はおこなわず、応募者を対象にした合宿形式の実践型研修をおこなう事例があります。合宿型の実践型研修では、応募者のコミュニケーション能力やチームワーク力、さらには将来的な成長の可能性を見て選考をおこないます。また、応募者の本来の姿を見極めるのにも効果的です。
合宿を通じて応募者が実際の業務に近い環境で活動するため、企業と応募者の相互理解が深まります。応募者も入社後のイメージが具体的にもわきやすく、入社意欲も高まり、選考辞退を防ぐことに繋がるでしょう。
採用代行サービスを利用する
採用活動を効率良くおこなうために、採用代行サービスを利用する方法もおすすめです。
選考辞退を防止するための対応の1つとして求職者への迅速な対応が必要となりますが、面接調整や、面接前日のリマインド連絡等も採用代行サービスで対応してくれます。自社では迅速に対応できない業務も代行サービスを活用することで確実に丁寧に対応してくれ、求職者からの信頼も保つことができます。
面接などの実際に求職者と密なコミュニケーションが必要な場面は人事担当者が対応し、面接のリマインド連絡などの業務は採用代行サービスを取り入れてみましょう。
自社の時間をかけるべき採用活動を見極めて、選考辞退防止につなげましょう。採用代行の概要や事例を確認したい場合はこちらをチェックしてみてください。
- 3分でわかる!採用代行(RPO)活用ガイド ~特徴・料金・事例まで解説~
採用効率UPに繋がるプロのノウハウ!
・採用を強化したいが人手が足りない
・面接実施後の歩留まりが低下している
・面接の判断軸が定まっていないそのような人事担当者におすすめです!
採用課題の解決に繋がる資料をご確認ください!
5.まとめ
本記事で紹介した選考辞退の防止方法を実践すれば、選考辞退率を大きく低下させ、応募者に内定まで高い意欲と興味をもって参加してもらうことが可能になるでしょう。
再度、重要な要素について記載します。
・応募や質問に対して迅速に返信して自社への信頼度を高める
・正確でわかりやすく豊富な情報量の求人情報を提示する
・面接の前には電話とメールでリマインドの連絡をする
・面接ではなくカジュアル面談を実施して、応募者と企業双方の理解を深める
・面接で来社した応募者への対応方法を全社員に周知徹底する
実践すべきことが多いですが、ぜひ取り組んでみてください。選考辞退が減少し、自社の望む人材を確保できる可能性が高まるでしょう。
もし、さまざまな理由で採用に工数が割けない場合や、応募者の興味を惹くことがうまくいってないように感じる場合は、採用代行サービスの利用を検討するのもおすすめです。採用に関する工数を削減、さらに採用効率を上げて、自社の望む人材を確保しましょう。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る