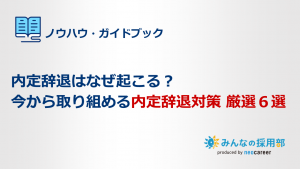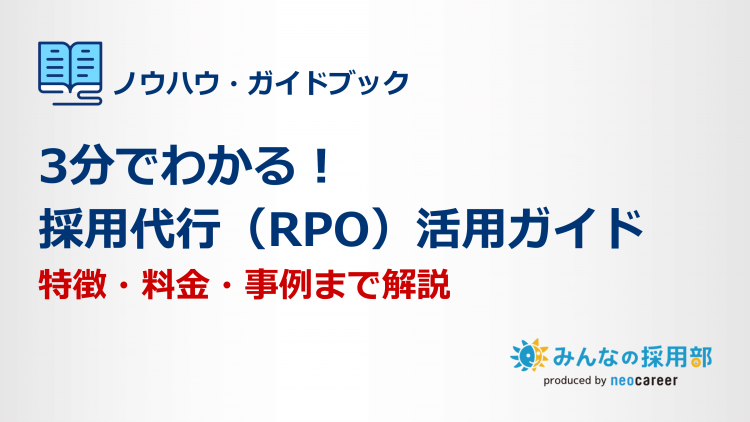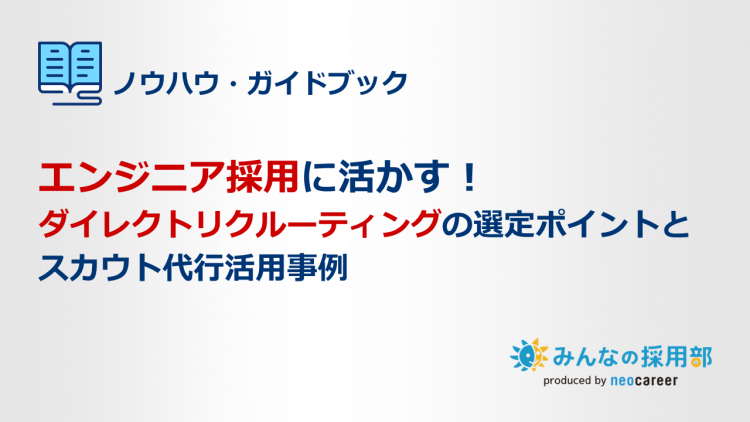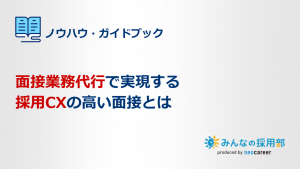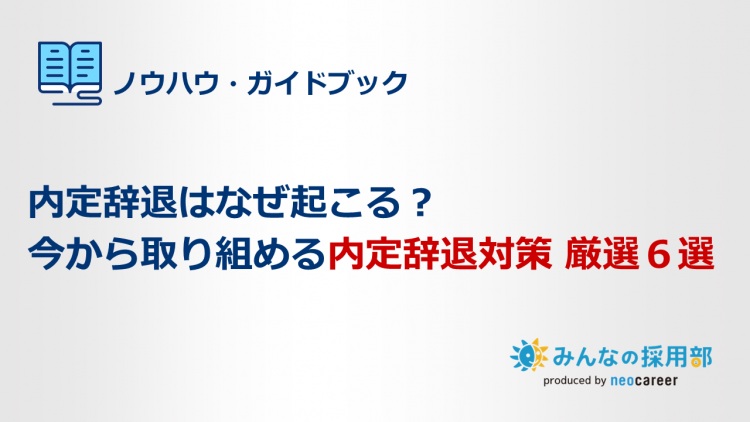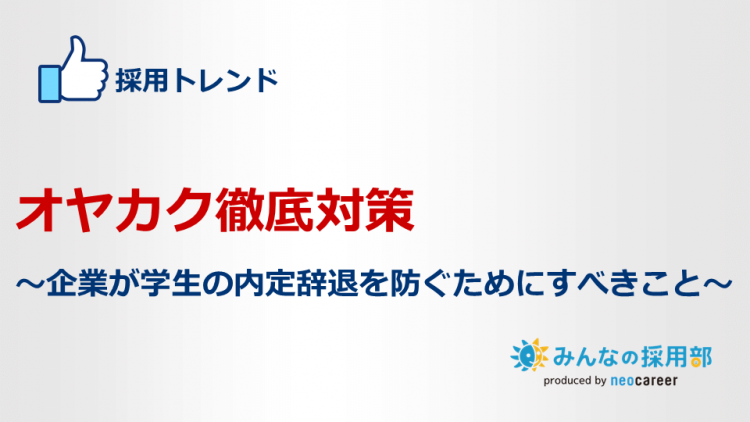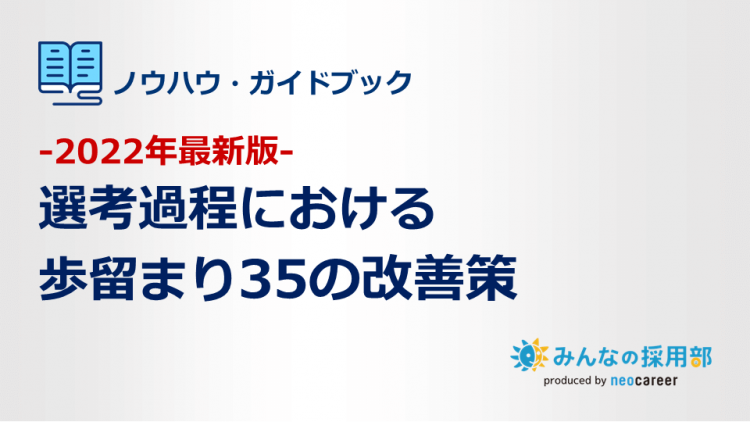内定辞退を減らすには?|原因と効果的な対策6選!企業の成功事例も解説
新卒採用
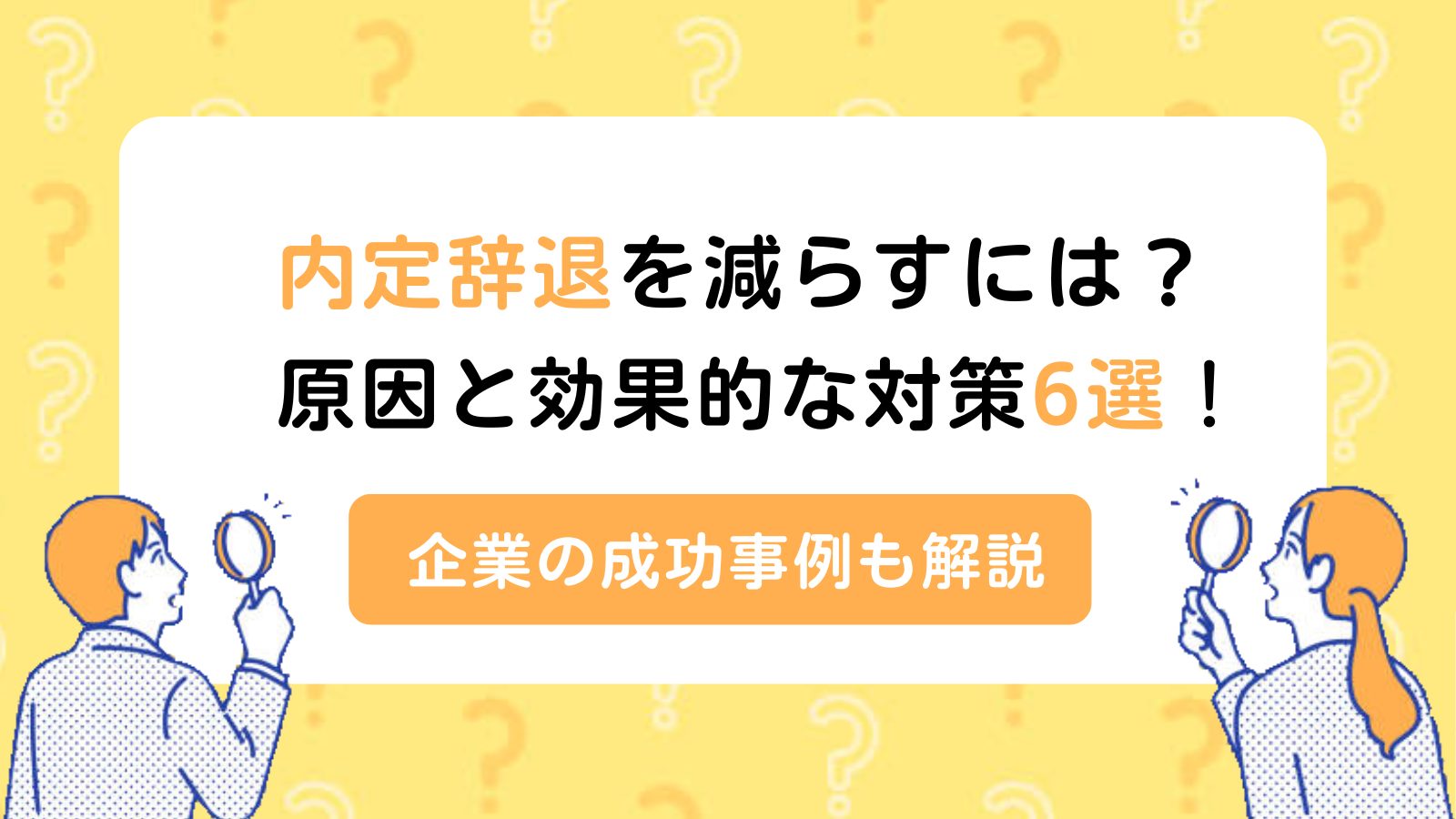
入社予定者の内定辞退が多くなってしまい採用活動が計画的に進まず、内定辞退に関して悩みを抱えている採用担当者は少なくないでしょう。
内定辞退の理由は、企業への不安・不満の高まりや、興味・関心の減退による求職者の志望度低下によって引き起こされます。その背景には、採用担当者が求職者に適切な対応をとれていないケースも見られます。
そこで本記事では、
・求職者が内定辞退をする理由
・内定辞退を減らすための対応方法
・内定辞退の減少に取り組む他社事例
について紹介します。
自社の状況を踏まえた適切な対策を講じて内定辞退を減らし、人材採用を効率化しましょう。
1.内定辞退や選考辞退で多い5つの理由
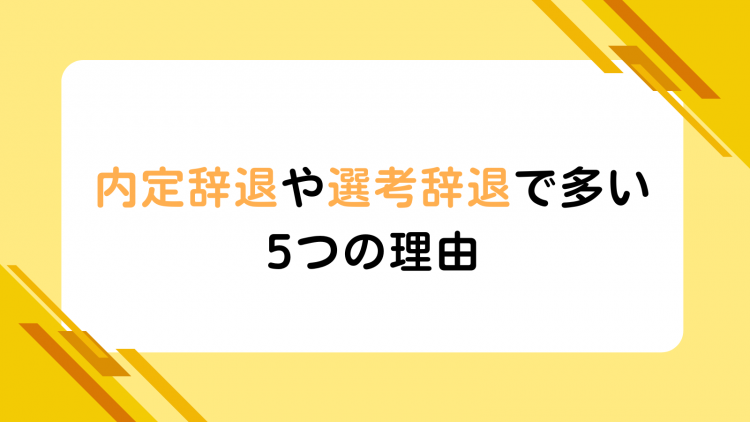
内定や選考の辞退を減らす対策を検討するうえで、背景にある理由や原因の的確な把握が重要です。
採用市場において採用側が優位な状況だと求職者は選り好みできないため、内定や選考の辞退は発生しにくくなります。しかし、現在の求職者優位な市場動向では、求職者は複数企業から内定を得た後に自分の志向や好みに合致する企業を選択する傾向があり、内定辞退や選考辞退が増加傾向にあります。
そのため、求職者が企業を選択する時代であるという前提に立ち、内定辞退される理由を把握して内定辞退・選考辞退の発生を防ぎましょう。
ここでは、内定辞退・選考辞退されてしまう理由を5つご紹介します。
志望順位が高い企業での採用が決まったため
内定辞退や選考辞退で多い理由の1つは、志望順位が高い企業での選考が進んだり採用が決まったりしたケースです。
「内定が決まった」「他社での選考が通過し、受ける企業を絞りたい」などの理由で、求職者から選考辞退の連絡を受けるケースは少なくありません。求職者は、将来のキャリアや目標への適合度に合わせて企業に対する志望順位を決めます。
そのため、内定を受けていても志望順位の高い企業から内定が出た場合には、ほかの企業の選考や内定を辞退する傾向が顕著です。求職者の志向やキャリアを企業が把握できていない場合、予期せぬ内定辞退・選考辞退につながってしまうと言えるでしょう。
求職者の望む仕事環境や待遇と合致していないため
内定や選考辞退の理由に、自社の仕事環境や待遇が求職者の希望に添えていない点も挙げられます。
求職者にとって、自分の価値観やライフスタイルに合った職場環境、待遇の良し悪しは企業選びの際の判断材料です。特に、人材不足により就職市場が求職者優位な売り手市場になっている現在、求職者は過去と比較しても複数の企業から内定を獲得しやすい傾向にあります。
そのため、自分の望む働き方を実現でき、希望する給与を提供してもらえる可能性の高い企業を選択し、就職したいと考える求職者が増えています。求職者が望む仕事環境や待遇が整っている企業が選ばれやすく、採用市場の変化に対応できないと内定辞退が増える点を理解しておきましょう。
企業のイメージと実態に違いがあるため
求職者が企業に抱くイメージと実態との大きな隔たりが、求職者が内定辞退・選考の辞退を決断する理由になる場合も少なくありません。
就職活動の一環として、求職者は企業のWEBサイトや求人広告を通じて企業のイメージを形成します。しかし、説明会や選考会で得た情報が求職者の想定と異なると、期待外れと感じて企業への志望度が低下するのはよくあるケースです。
背景には、自社の説明が不足していたり、勘違いをさせてしまうような内容になっていたり、うまく伝えきれていないなどの要因が挙げられます。そのため、求職者にありのままを「伝える」「魅せる」といった点を意識するのが大切です。
面接官や社員の印象が悪かったため
面接官や社員の悪い印象は、求職者が内定辞退・選考辞退を検討する際の主要な判断材料の1つです。
求職者は面接官や社員の態度や対応から企業の文化や職場の様子を推測します。例えば、「質問に対する回答があいまい」「面接に遅れてくる」などの言動が目立つ社員に対し、求職者は不満を募らせるのは当然です。
一方で、「面接だけでなく、就職活動のアドバイスをしてくれた」など、採用担当者が親身になって接すると求職者の志望度が上がる傾向も見られます。不本意な内定辞退や選考辞退を招かぬよう、求職者に接する可能性のある社員には教育を徹底するなど対策を講じましょう。
内定後のコミュニケーションに不満を感じたため
内定を受けてから入社までの間に企業から接触がなく、求職者が不安や不満を感じると内定辞退する場合もあります。
企業からの連絡が不十分だと、求職者は企業から歓迎されていないと感じてしまう可能性が高まります。内定後に企業とのやりとりが少なく、相談や質問に対する回答が遅かったり曖昧だったりすると、求職者は不安や企業への不信感が高まり内定辞退に繋がるのです。
特に新卒採用の場合、内定を取得してから入社まで半年以上時間が空くため、求職者はほかの企業に目移りしやすくなります。内定者とのコミュニケーションは内定者の不満や不安解消に加え、企業イメージの向上にも貢献する重要な取り組みであると理解しておきましょう。
採用活動全体の歩留まり改善に関する方法を知りたい方は、以下の記事や資料も参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
- 採用の歩留まりを改善する9つの施策|低下する原因から成功事例までご紹介
2.内定辞退や選考辞退を減らす6つの方法
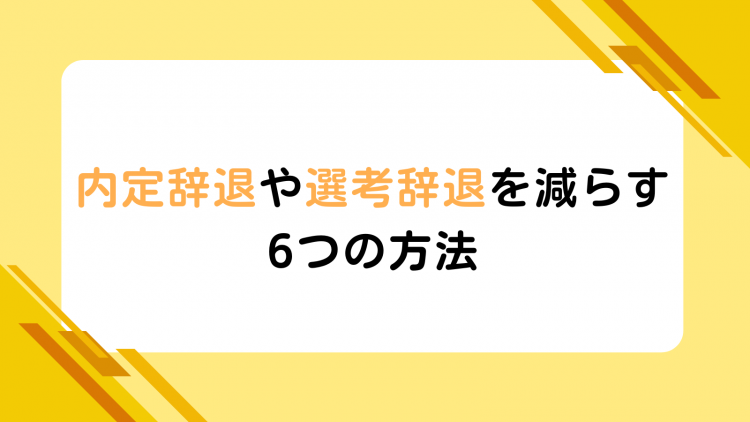
内定や選考辞退を減らすには、求職者が抱える自社への不満や不安の払拭や、自社に対する関心や興味の底上げが肝要です。
不満や不安を低減できると、求職者が辞退を決める強い要因を打ち消せます。また、自社への関心や興味が高まれば自社への志望度も高まり、他社への志望度を上回れば志望順位を理由とする辞退も防げます。
つまり、内定や選考辞退を減らす対応を試みる際には、求職者の不安・不満の払拭や興味・関心を喚起する取り組みに注力しましょう。
選考を通じて求職者への熱意を伝える
内定辞退や選考辞退を減らすためには、選考を通じて求職者へ熱意を伝えることが重要です。
求職者は企業からの関心や熱意を感じると、企業への信頼感や興味が高まりやすくなります。例えば、面接で求職者に対して具体的にフィードバックすると、企業が求職者を真剣に評価している姿勢を示す方法として有効です。同時に、求職者に「自分の至らない点を教えてくれた」などと感じてもらえると、企業に対する信頼感や興味の高まりが見込まれます。
選考は求職者と企業の信頼関係を構築する大切な取り組みと位置づけ、求職者に入社したいと評価される企業を目指しましょう。
面接結果は間を空けずに通知する
他社への求職活動が優先されないように、面接実施から結果の通知まで間を空けない対応が大切です。なぜなら、求職者は選考結果が出るまでの間も複数企業への選考活動を進めるケースが多く、結果通知が遅れると他社に決める可能性があるためです。
業務多忙で迅速な通知が困難な場合には、採用代行サービスを利用するとスピーディーな対応と質の向上が見込まれます。迅速な通知によって、求職者に対する企業の誠実さや求職者への関心を示しましょう。
採用代行サービスの概要やメリット・デメリットを知りたい方は、以下の資料も参考にしてください。
企業の仕事内容や業務環境の理解を深めてもらう
求職者に企業の仕事内容や業務環境の理解を深めてもらう働きかけも、内定や選考辞退を防ぐうえで有効です。
一般的に求職者は公表されている情報や口コミなどをもとにして、応募先の企業での業務やオフィス環境を想像します。しかし、求職者の先入観や誤解により、求職者がミスマッチしていると思い込んでしまう恐れがあります。
求職者に深く正しい企業の理解を促すには、オフィスツアーやインターンシップなど、直接企業に触れる機会の提供が効果的です。入社後のイメージを正しく提供し、求職者に企業に対する興味や関心を高め、志望度の向上を図りましょう。
社員との繋がりを構築する
求職者と社員との繋がりの構築は、入社後の不安払拭やキャリアイメージをつかんでもらう方法として効果的です。求職者が採用担当者以外の社員と交流できると、職場の雰囲気を理解しやすくなったり、企業に対する親近感や信頼感が高まったりするためです。
例えば、内定者向けの交流イベントや懇親会を開催すれば、求職者と現場の社員が直接会話する機会を設けられます。一緒に働く可能性のある現場社員との交流を通じて、求職者は企業への不安や疑問の払拭だけでなく、具体的な働き方をイメージしやすくなります。
求職者を多角的に観察するという意味でも社員とつながる機会を作り、辞退する可能性の高い求職者を早期発見し辞退防止に役立てましょう。
内定者の不安や不満を取り除く
内定を出した後も定期的に内定者とのコミュニケーションの場を設けて、入社までの期間に生じる求職者の不安の軽減を続けるのも大切です。
企業から内定を得ると、それ以外の選考活動を取りやめるケースが多いですが、時間の経過とともに求職者は自分の判断に不安を感じ始めます。仮に第1志望の企業から内定を得たとしても、自分の決断に不安を抱く内定者は多く、この現象は内定者ブルーと呼ばれています。
不安が生じるのは、人生の大きな選択をしたと考えているためであり、具体的な原因がないケースが大多数です。そのため、入社までに頻繁に内定者と会話する場を設け、不安に対して寄り添う姿勢を示し、安心感を持たせるよう努めましょう。
企業から採用したい求職者に直接アプローチする
自社で活躍し定着している人材の傾向や志向性に近い人材に企業から直接アプローチする採用手法は、内定辞退・選考辞退の防止に役立ちます。なぜなら、入社後も長期間の定着が期待できる人材候補であれば、辞退されにくい選考対象者と考えられるためです。
企業への適合度が高いと見込まれる求職者にアプローチできると、採用活動の歩留まりも高まり、内定や選考辞退の可能性も抑えやすくなります。
求職者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングサービスに興味のある方は、以下の記事も参考にしてください。
3.内定辞退を減らす企業の取り組み事例3選
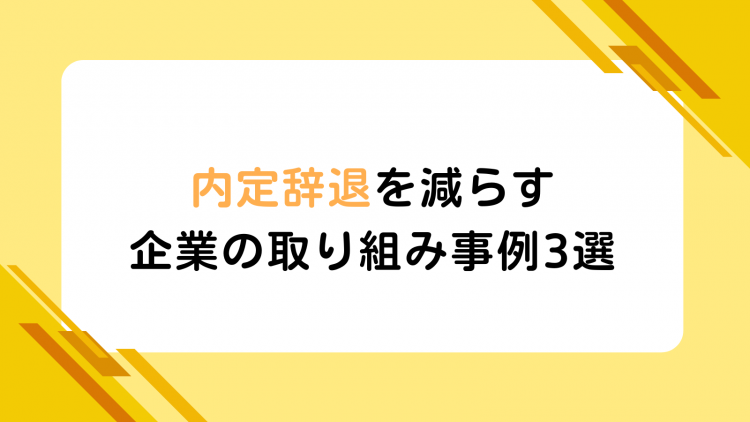
内定辞退を減らすべく、企業は自社の状況に応じた独自の方法で対策を講じています。本章では内定辞退防止に向けた取り組みをおこなっている企業事例をご紹介します。
株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリホールディングス(以後、ニトリ)は、積極的に内定辞退・選考辞退を減らす取り組みを進めています。
特徴的な取り組みは、解決したい社会問題と取り組みたい業務の関係性を整理する「エンプロイー・ジャーニーマップ」の活用です。ライフイベントも加味して10年単位の目標を設定するなど、入社後の働き方を内定者に検討してもらう取り組みです。
「エンプロイー・ジャーニーマップ」は、ニトリの人事戦略の基礎でもあり、ニトリの求める社員像や業務への向き合い方も学べます。
ニトリは企業で実際に活用している取り組みに関する体験を通じて、内定者の企業理解を深め、採用活動の成功率向上に努めています。
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、内定者の不安払拭や仕事イメージを高めてもらう独自の取り組みをしています。
具体的には、内定者に入社後の円滑なスタートを支援する育成制度、スタートダッシュ応援プログラム「DASH」を設けています。「DASH」で提供されているプログラムは以下の5点です。
・予定配属先とは関係ない部署の先輩社員と気軽に相談できるメンター制度
・社員同様に実務を体験する長期の内定者アルバイト
・配属が予定されている部署での業務を経験する短期アルバイト
・入社後のキャリアプランを自社独自の手法で検討する研修
・配属予定の部署の役員や先輩社員とのコミュニケーション会
入社までの期間における内定者への支援を充実させて、積極的に内定辞退の減少を図っている点が特徴です。
Sansan株式会社
Sansan株式会社(以後、Sansan)は、採用手法に工夫を講じて採用効率を高めています。
以前、Sansanでは内定辞退が続発して、エンジニア内定者における歩留まりの悪さに悩んでいました。そこで、採用手法に企業から求職者にアプローチするスカウト型採用を導入し、技術に加え志向も含めて適合度が高い求職者への接触を進めています。
また、採用体験の向上を目的に選考内容を見直し、求職者が選考を通じて入社動機を高め、積極的に入社を選択できる環境も創出しています。
内定辞退の原因は採用手法や選考内容にあるとして、選考活動のあり方を刷新して内定者辞退の減少を実現しているのがSansanの事例です。
内定辞退を減らす取り組みに限らず、採用戦略が成功している企業事例に興味のある方は、こちらの記事も参考にしてください。
4.内定辞退を減らす上での4つの注意点
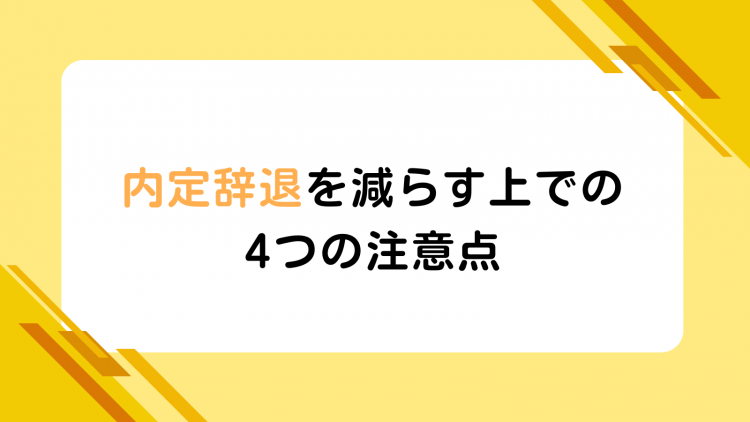
内定辞退を減らす取り組みをがむしゃらに押し進めると、辞退の抑止どころか辞退を促進してしまうリスクがある点に注意が必要です。
取り組み方や取り組む姿勢が不適切だと、求職者の企業に対する興味や関心が低くなるだけでなく、不信感が募ってしまいます。重要なのは求職者による決断の尊重であり、企業は4つの注意点を踏まえた対応が望まれます。
内定辞退を減らす活動が辞退促進につながらぬよう、適切な対処で内定承諾率の向上を実現させましょう。
ほかの企業への就職活動の終了を強要しない
内定辞退を減らす取り組みを進める際に、ほかの企業への就職活動の終了を強要しないようにしましょう。そもそも他社への就職活動をやめさせる行為(いわゆる「オワハラ」)は、憲法における職業選択の自由を妨げる違法行為になる可能性があると、政府の見解*1が示されています。
*1出典:内閣府「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」
そのため、企業に求められるのは、求職者に対して職業選択の自由を尊重する姿勢です。他社への就職活動を通じて自社の魅力を改めて理解してもらえれば、自社への興味関心が高まり志望度も向上します。
求職者が内定を自らの意思で積極的に受け入れる状況を提供し、内定辞退を減らしましょう。
内定辞退に対して引き留めすぎない
内定辞退を表明した内定者をしつこく引き留めようとすると、嫌がらせ行為と受け取られる可能性があるため注意が必要です。極度に引き留めようとすると、その内容を口コミサイトなどで暴露され、悪評が自社への就職希望者を遠ざける原因になりかねません。
また、内定者の辞退の意思を強める可能性もあり、無理な引き留め工作は差し控えるべきです。企業に求められるのは内定者の意思の尊重であり、辞退の理由が誤解から生じているのであれば、正しい情報を伝えて適切な判断を促しましょう。
万が一、内定者が他社へ就職しても、自社に対する印象が悪くなければ、転職活動時に志望企業の1つになる可能性がある点も踏まえた対応が大切です。
内定者フォローの活動実施を目的化しない
内定者に向けた社内見学や社員との交流会などの取り組みが目的化して、目的達成をおろそかにしてはなりません。
そもそも、内定者に向けた取り組みは、内定者の不安解消や企業への信頼感向上です。ただし、内定者によって状況が異なるため、内定者とのコミュニケーションから得られた情報に基づいた最善策を講じるのが肝要です。
例えば、同期とのつながりよりも、入社後の生活などに不安を抱えている場合には、懇親会よりも個別の面談が適切な場合もあります。
内定者における入社志望度の維持向上をゴールに見定め、個別対応を重視し、内定辞退を減らしましょう。
採用候補者体験(採用CX)を下げない
選考や内定通知後を含めた採用過程全体で、求職者における採用候補者体験(採用CX)を下げない工夫が大切です。なお、採用CXとは、認知から選考終了までのフェーズで、求職者に「この企業に応募してよかった」と思ってもらえるような取り組みを指します。
採用過程を通じて求職者が前向きと感じる体験ができると、企業への信頼感や興味が高まり、内定辞退のリスクが減少するためです。仮に内定者がやむなく他社への就職を決めたとしても、自社への良い印象や強い信頼感があれば、将来社員になってもらえる可能性があります。
例えば新卒採用の場合、30%以上の就業者は就職後3年以内に離職するため*2、転職活動の際に自社の採用選考に参加するケースは大いにありえます。
*2出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」
内定辞退を表明されたとしても、最後まで採用CX向上を意識した対応を継続し、内定者を将来の社員候補として大切に扱いましょう。採用CXを高める手段の1つとして注目されている面接代行を詳しく知りたい方は、以下の資料も参考にしてください。
- 面接の質を向上させたいという方におすすめ!
労働人口が減少し母集団形成が難しくなっている昨今、採用CX(候補者体験)を向上させ歩留まりを改善しようとする企業が増えています。
本資料では、面接業務代行サービスを利用し採用CXの高い面接を実現する方法についてご説明しています。
5.まとめ
この記事では、内定辞退・選考辞退が生じる理由と辞退への対策方法に加え、企業の実践事例や考慮点について紹介しました。
選考中や内定通知後において、さまざまな取り組みを講じれば、内定辞退を防げます。内定辞退に至る理由は、企業への不満や不安の増大や、興味や関心の低下による、志望度の減衰に集約されます。
しかし、求職者によって状況が異なるため、求職者に合わせた対応を施すことが重要なポイントです。内定辞退を減らして、必要な人材を的確に確保し、採用活動の効率性を高めましょう。
株式会社ネオキャリアが提供する「みんなの採用部」は、200以上の採用ツールを取り扱い、累計約14,000社(※)の採用支援をおこなっています。採用に関しては、アルバイト・新卒・中途とそれぞれの採用に最適な代行サービスを提供しています。ご予算やご要望に応じたご支援も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 【無料オンライン相談】採用のプロにお任せください!
採用に苦戦している、新しい採用手法を取り入れたいなどのお悩みを、プロのコンサルタントに無料で相談することができます。
企業の課題にあったサービスのご提案ができますので、ぜひお問い合わせください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る