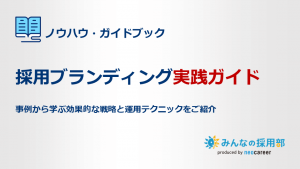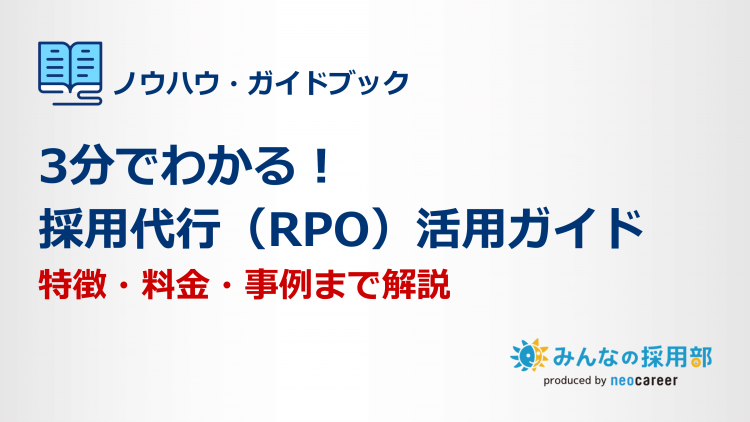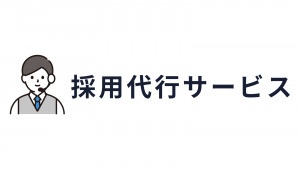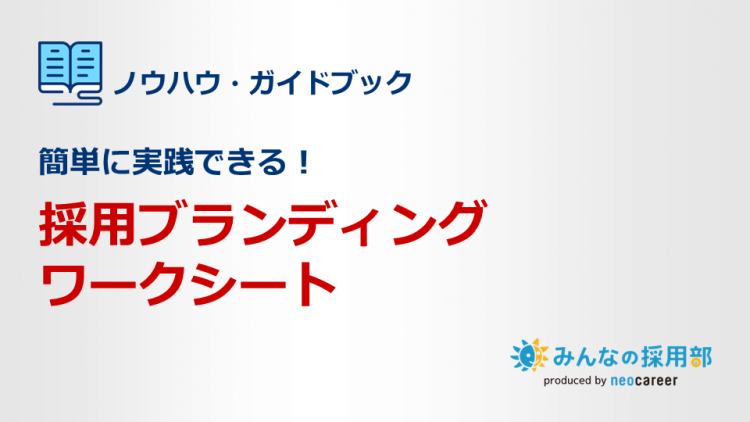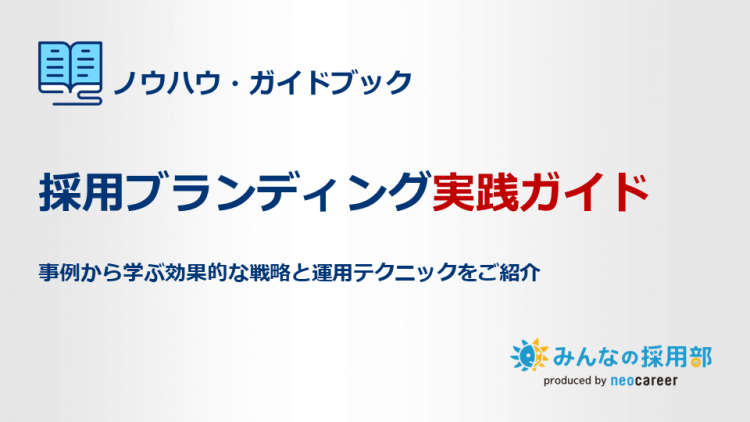採用ブランディングの成功事例と失敗事例を紹介|戦略や取り組みのポイントは?
採用 ブランディング 事例
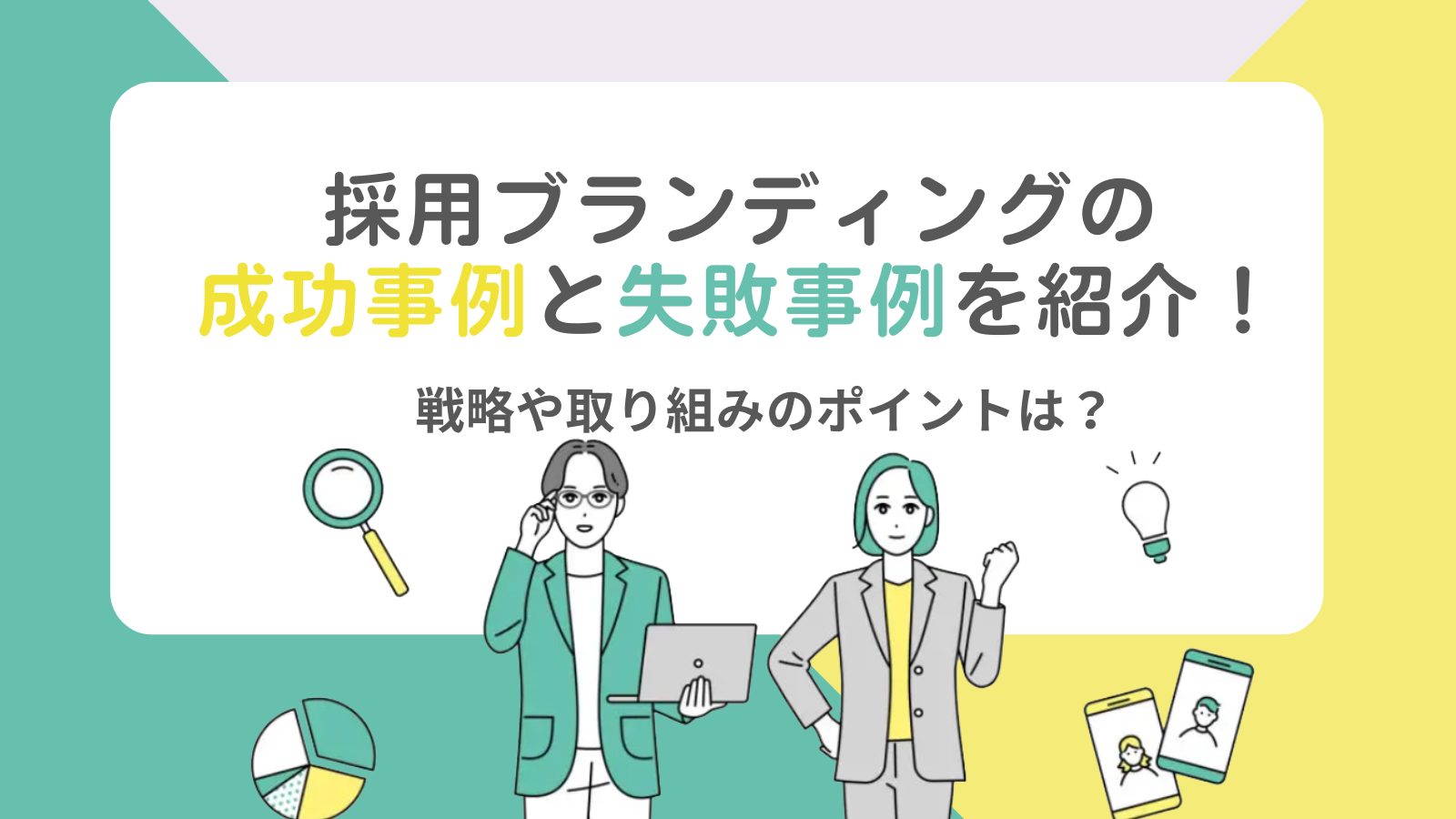
採用ブランディングは、採用をおこなう上で非常に重要な役割を担っていますが、継続的に社員を巻き込む必要があり中長期的に取り組むべき活動です。
本記事では、
・採用ブランディングとは何か
・採用ブランディングの成功事例や失敗事例
・採用ブランディングを成功させるためのポイント
についてご紹介します。
1.採用ブランディングとは
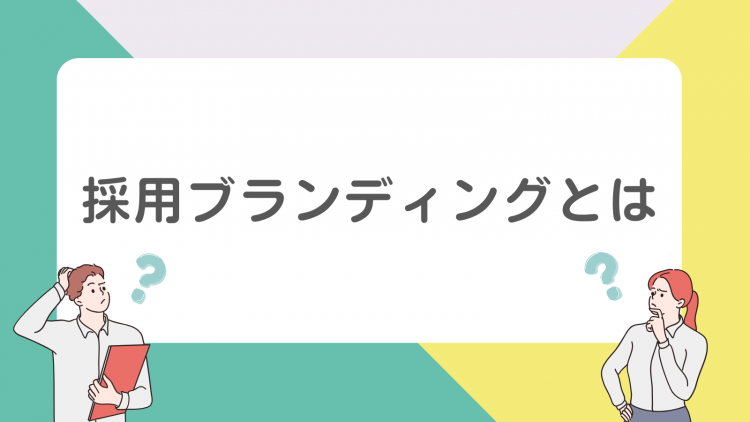
採用ブランディングとは、企業の認知度や求職者の入社意欲向上を図るために、企業のイメージをブランド化することです。競合他社と差別化し、求職者に自社を選んでもらえるように促します。
採用に関わる言葉としては、採用マーケティングや採用広報といったものもありますが、以下のように採用ブランディングとは意味合いが異なります。
採用ブランディング
企業の認知度アップや求職者の入社意欲を高めるために、企業イメージをブランド化することを指します。
採用マーケティング
企業の魅力や特徴を効果的に伝えるための戦略や手法のことです。基盤として強固な採用ブランディングが必要になります。
採用広報
人材の募集を促すための広報活動を指します。長期間かけてじっくりとおこなう採用ブランディングとは異なり、即効性のある広報活動に重点を置くことです。
社内外で企業イメージを醸成していくために、時間をかけて根気よく採用ブランディングをおこなう必要があります。以下の記事では、採用ブランディングについてより詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
2.採用ブランディングの成功事例5選

採用ブランディングを成功させるためには、成功事例を通してポイントをおさえることが大切です。以下で、採用ブランディングの成功事例を5つ紹介します。
採用ブランディングは、長期間にわたって、絶え間なく活動を続けることが成功の鍵です。それぞれの事例から、各企業が採用ブランディングを成功させたポイントを見ていきましょう。
【新卒・中途採用】A社|自社メディアで社員が働く様子をオープンに発信することでイメージアップ
A社では入社後のミスマッチをなくすことを目標にして採用ブランディングをおこない、求職者に対して風通しの良い会社というイメージを与えることに成功しました。
自社メディアを介して、社員のリアルな声はもちろん、外部メディアには出しにくいコンプライアンスや、リスク管理についても幅広く発信しています。社内で採用ブランディングをおこなうチームを設置し、創刊から2年半で採用に関する記事を約1,000本発信するに至りました。
社内外の情報格差やイメージギャップを防ぎ、社外の方からも自社について具体的にイメージしてもらい、親しみを持ってもらえるよう心がけています。
企業のサービスや実績ではなく、「従業員」に焦点を当てた発信がきっかけで、求人応募や入社に繋がっています。社外と社内のどちらからも興味を持ってもらえるよう、魅力を一方的に伝えないよう心がけ、社内の情報をクリアに発信し続けたことが、求職者の信頼醸成に結びつきました。
ちなみに、A社で採用ブランディングをおこなっているのは、新卒入社、中途入社、グローバル社員、人員計画や総務など複数の部署の社員で構成されたチームです。自社メディアの運営だけでなく、採用に関わる幅広い企画や運営をしています。
A社では、事業の成長を支えるためには組織づくりが不可欠だと考え、日々社内で幅広い社員が協力しながら、採用ブランディングに携わっています。
【新卒採用】B社|企業イメージと就労イメージのギャップを軽減
B社では写真や動画などの素材を採用活動で効果的に使い、企業イメージと就労環境イメージのギャップを埋め、採用ブランディングに成功しました。
B社は資源・エネルギー事業かつ本社が東京にあるということから、求職者からダイナミックな企業イメージを持たれがちでした。しかし、実際は四国地方にある鉱山で暮らしながらおこなう仕事です。
就業後のギャップを防ぐために、「B社で働くこと=山で暮らすこと」という採用コンセプトを打ち出し、学生が仕事内容をイメージしやすいように工夫しました。
就職サイトでは、写真や動画などの素材を活用して山で働くことを壮大に打ち出し、都会のような便利さがない環境を伝えています。サイト上の素材を通して、エントリーする学生のフィルターをかけています。
結果、B社での働き方に共感した学生がエントリーし、採用することが困難な機電系の学生を15名採用することができました。
エントリー数自体は採用ブランディング前と変化はないものの、B社での就業を強く希望する学生が集まるようになりました。採用ブランディング開始後5年の離職者も、3名以下と少数におさえられています。
山で暮らしながらキャリアを積んでいくことを具体的に示したことで、「山で働きたい」という採用コンセプトに共感した学生がエントリーし、採用に繋がりました。
【新卒採用】C社|アンケートとイベント開催で効率化
C社では採用ブランディングと採用戦略の設計をおこなうために、アンケートリサーチを活用し、効率よく採用活動をして採用ブランディングを成功させました。
当初からC社では、応募者アンケートをもとに、自社の採用マーケットでの位置付けを確認していました。効果的な採用ブランディングをおこなうためのベースづくりとして、フラットな意見を収集できるよう、学生を対象にアンケートリサーチをしています。
求職者に効率よく自社の情報を伝えるために、採用の各ステップで求職者に開示する情報を精査し、活用しています。アンケートリサーチの結果を採用ブランディングに活用した結果、応募者数が2年間で倍になりました。
また、優秀なエンジニアを採用するために、自社のエンジニアを他社のイベントに登壇させるといった工夫もしています。イベントでは、技術的な指導に加え、登壇者自身の開発への想いや将来像を伝えることで、参加者がキャリアステップをイメージしやすいよう心がけています。
登壇したエンジニアが自身の言葉で経験や想いを語ることは、参加者の共感を呼び、参加者から「自分も登壇者のようになりたい」と憧れる気持ちを抱いてもらうにも有効です。
イベントの最後には、登壇したエンジニアが所属する部署で、エンジニアを募集していることについての宣伝をし、応募者の獲得に成功しています。
【新卒採用】D社|ビジネスの独自性を打ち出して認知度アップ
自社の特徴を継続して打ち出し続けたことで、採用ブランディングに成功したのがD社です。採用ブランディングを成功させるために、独自性を打ち出すだけでなく、採用にかける予算を増やすよう、人事担当者が粘り強く上層部と交渉し続けました。
知名度の低さや地方での勤務になることが原因で応募者が少なかったD社ですが、採用予算を増やしたことで、エントリー数を300名から13,000名まで増やすことができました。個々の応募者を見ることを重視し、SNSやイベントを活用して、少ない母数でもマッチしやすい採用方法を活用しています。
2013年には、より効果的な採用活動をおこなうために、自社サイトにて「〇〇は好き?」「〇〇に住みたい?」という質問に「はい」と答えた求職者のみが応募できるよう選考方法を変更しました。
ビジネスの独自性を打ち出し続けたことで、要件にあった応募者のみが集まるようになり、ミスマッチによる離職も減りました。また、採用ブランディングが成功したことで、企業の認知度アップにもつながっています。
D社の場合、自社の採用に関する分析をしっかりとおこない、採用担当者が予算を増やすように継続的に上層部と交渉したことも、採用ブランディングを成功させた1つの要因といえます。
【アルバイト採用】E社|従業員に提供できる価値を重視した採用広報
E社では企業が従業員に提供できる価値、EVP(Employee Value Proposition)を重視して採用ブランディングをおこなっています。以下のような、一人ひとりの従業員を大切にする姿勢が採用ブランディングの成功に繋がりました。
・従業員のポジションをきめ細やかに定める
・それぞれの従業員にあった仕事を提供する
・定期的な勤務評価や長年勤続したことを表彰する
E社はサービスを提供するだけでなく、「人と人とのつながりを大切にする」ことも重視している姿勢が功を奏し、毎年十分な人員を確保しています。
また、求職者が入社後に活躍するイメージを持ってもらいやすいように、従業員教育に力を入れているのもE社の特徴です。教育ではリーダーシップ、チームビルディング、マネジメントなどについて、アクティビティやディスカッションを通じて学びあいます。
ビジネスの世界で活躍する力を養うための教育を、採用ブランディングとして取り組んでいます。
なお、アニメ制作会社と提携して従業員の成長を描いたアニメーションの配信をしたり、自社メディアを通して情報発信をしたりすることで、E社で働くことを身近に感じてもらえるような工夫も欠かしていません。
働きやすい環境の整備や細やかな勤務評価など、働く従業員の立場に立った施策を実施することで、多くの企業が人手不足に困っている中でも従業員数を保っています。
3.採用ブランディングの失敗事例4選

採用ブランディングを成功させるには、社内での協力体制が欠かせません。しかしながら、中には失敗してしまったケースもあります。以下で、採用ブランディングの失敗事例を4つ紹介します。
成功事例だけでなく、失敗事例も把握することは、より効果的な採用ブランディングに繋がります。失敗事例を1つずつ詳しく見ていきましょう。
F社|社員からの共感や納得が得られないまま発足
F社では人事や上層部を中心に策定した採用ブランディングと、社内の実態に乖離があり、社員からの共感が得られないまま採用活動を発足させました。
採用ブランディングについて社員に広く意見を聞いたのは、採用活動を見据えてホームページや採用ページ、ポスターなどのツールを準備した後です。急な方向転換ができないため、そのまま採用活動を実施したものの、失敗に終わりました。
採用ブランディングの方向性を決める際に、自社理念や行動規範、目指すべき姿をベースに検討した結果、採用メッセージが実情から離れてしまったのが失敗の原因です。
社員を巻き込むことができていないまま、採用ブランディングをおこなってしまったことで、採用がうまくいかないだけでなく、企業イメージも落としてしまいました。
社外にアピールする前に、社内で採用ブランディングに対して共通認識を持つことが大切です。実情とかけ離れた内容を社外にアピールすることは、社員の不信感を招くきっかけにもなります。
採用ブランディングをおこなう際には、社内でアンケートを実施した上で、実情と大きく異なっていないか、きめ細やかな確認が必要です。
G社|エントリーの間口を広げた結果、内定辞退者が続出
G社では事業の成長に伴って採用を強化し、応募者の間口を広げた結果、採用ブランディングに失敗しました。応募者の母数を増やすことに注力したあまり、母数は増えたものの、自社への志望度合いが低い応募者が集まってしまったことが原因です。
結果、エントリーの母数は1.5倍になったものの、内定者辞退率が40%を超えるという事態を引き起こしました。特に高学歴の求職者からの内定辞退が集中している状況でした。
エントリー数は増えたものの、採用ブランディングの際、求職者に多くの資質を求めすぎたことが内定辞退率も高まってしまった理由です。多くのスペックを持つ優秀な求職者を獲得することは、より多くの企業と人材獲得をめぐって争うことを意味します。
必要な資質を具体的に絞った上で採用活動をおこなうことは、採用活動においての無駄な作業を省き、より自社にあった求職者を見つけることに繋がります。
採用ブランディングをおこなう際には、あれもこれもと、さまざまな資質や条件を求職者に求めるのではなく、希望する条件を具体的に絞ることが大切です。
H社|実際の就業環境と異なるアピールによる終業後のミスマッチ
H社ではアピールしづらい業務内容を隠したまま採用活動を実施したことで、就業開始後のミスマッチが多発し、採用ブランディングが失敗に終わりました。より多くの応募者を求めることにこだわるあまり、就業開始後の定着率を下げてしまったのが失敗の要因です。
採用担当者は屋外や工場などの体力が必要な業務が、求職者から避けられてしまうと案じ、説明会では業務内容よりも福利厚生をアピールするよう心がけていました。エントリー者が増え、採用目標を達成できたものの、早期離職者が続出する事態を招きました。
H社の採用ブランディングが失敗したのは、実際の就業環境と異なることをアピールしたためです。業務自体がアピールしにくい場合は、現場社員のやりがいや、適性のある人物像を伝えることで、業務内容に興味を持つ求職者を集めることが大切です。
募集条件と、実際の就業環境が大きく異なる場合、内定辞退や入社後の早期離職はもちろん、面接辞退の原因にもなりかねません。以下の記事では、面接辞退を防ぐ方法や、面接への参加率を上げるための方法を紹介しています。合わせて、参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
I社|担当者の異動で継続的な採用ブランディングが困難に
I社では採用ブランディングを立て直している途中で、中心となって活動していた人事課長が異動となりました。継続的な活動が困難になったことで、採用ブランディングが失敗に終わりました。
若手社員が採用ブランディングを引き継いだものの、採用コンセプトの共有やデータの活用などの引き継ぎがうまくいきませんでした。採用ブランディングを続けるどころではなく、まず何から着手すべきなのかから説明せざるを得ないといった状況です。
引き継いだ担当者は、採用ブランディングに関して、現場や経営陣に協力を仰いだり上手く説明できず、予算を削減されてしまいました。結果的に、I社では採用ブランディングの計画そのものが頓挫してしまいました。
採用ブランディングは、自社の分析や戦略設計、計画の実施、そして見直しまで、時間も工数もかかるタスクです。社内での協力体制も、採用ブランディングを成功させるためには、不可欠です。
採用ブランディングをスムーズにおこなうためには十分な人員を割き、社内にコンセプトが浸透するまで、絶え間なく活動を継続する必要があります。
4.採用ブランディングを成功させるためのポイント
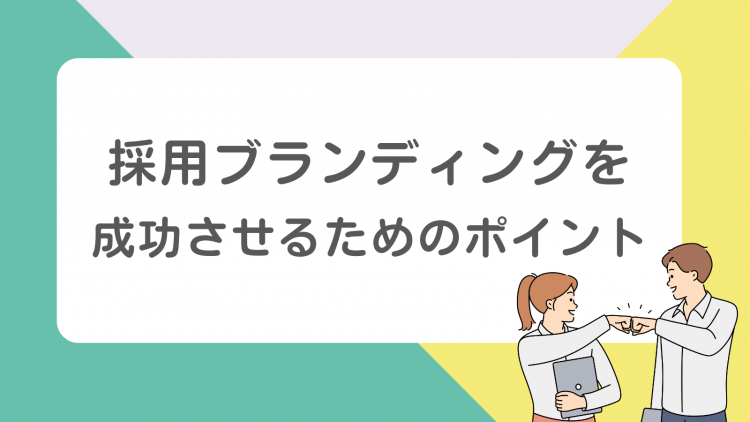
ここまで採用ブランディングの成功事例と失敗事例を解説してきました。以下では、成功事例と失敗事例を踏まえて、採用ブランディングを成功させるためのポイントを6つ紹介します。
いずれのポイントも長期にわたって、根気強く続けることが大切です。採用ブランディングへ熱量を持って取り組むからこそ、求職者が集まり、企業も成長します。以下で、1つずつ解説します。
自社の採用活動の現状について把握する
採用ブランディングを成功させるためには、まず自社の採用活動の現状について見極める必要があります。まずは、以下の点を整理するようにしてください。
・自社の強み・弱み
・競合他社の強み・弱み
・求める人物像の明確化
採用に関して発信する前に、自社の業界内でのポジションを把握する必要があります。自社の理念や強み・弱みを分析するだけでなく、競合他社の採用活動について調査した上で、自社の強みや他社と差別化できる点を把握します。
また、希望する求職者を獲得するために、ポイントを絞った上でメッセージを送ることも大切です。学歴や職歴、スキル、資格、家族構成、年齢、趣味など、採用したい人物像をできるだけ明確にすることで、よりターゲット層に訴求することに繋がります。
社内一丸となって採用ブランディングをおこなう
入社を希望する求職者に対して、自社の客観的な魅力を発信するために、採用ブランディングでは社員を巻き込んでおこなうことが重要です。採用ブランディングのコンセプトが実情とあまりにも乖離していると、社員のモチベーション低下や不信感の原因となることもあるからです。
採用ブランディングをおこなう際は、社内でもアンケートやリサーチをおこない、実情と乖離していないか確認し、社内のありのままを伝えるようにしてください。
また、採用ブランディングをスムーズに実行するためには、採用ブランディングに関わる部署や従業員に以下の点が求められます。
- ・採用コンセプトを理解していること
- ・採用ブランディングに関する実務に長けていること
- ・上層部や現場に根回しができる人物が複数名いること
人事や採用担当者だけでなく、経営陣が先頭に立って採用ブランディングの必要性を社内で説き続け、コンセプトを社内に浸透させることが大切です。
社内で採用ブランディングのコア業務に注力するために、採用活動に関するノンコア業務をアウトソーシングするのも有効です。みんなの採用部では、幅広い採用代行(RPO)に対応しております。以下の記事も合わせて参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
- 【資料ダウンロード】採用のプロがわかりやすく解説!
採用効率UPに繋がるプロのノウハウ!
・採用ブランディングを強化したいが人手が足りない
・面接実施後の歩留まりが低下している
・面接の判断軸が定まっていないそのような人事担当者におすすめです!
採用課題の解決に繋がる資料をご確認ください!
自社の情報をオープンに伝えて求職者を獲得する
求職者に自社の社風や社員の人柄を身近に感じてもらえるように、求職者の目に留まりやすい仕掛けを通して、自社の情報をオープンに伝えることも大切です。
ターゲットとする求職者の目に留まりやすい仕掛けとしては、社員との対面または非対面の交流会や、SNSでの発信など、ターゲットとする求職者と複数の接点を持つことが挙げられます。
社内の雰囲気をありのままに発信することは、発信内容に共感した求職者からの募集獲得に繋がります。また、共感をした上で入社しているので、入社後のミスマッチを防ぐこともできるでしょう。条件面だけでなく、自社のありのままの魅力を伝え、求職者に仕事のやりがいや、数年後のイメージを持ってもらうことが大切です。
特にZ世代はリアルを重要視する傾向があるので、新卒採用において自社の情報をオープンに伝えることはより効果的です。
単に自社の理念や社風をアピールするのではなく、「A社といえば、〇〇」というように、具体的にイメージを持ってもらえるような採用ブランディングを心がけてください。
就労環境や業務内容を詳しく開示してミスマッチを回避する
就業後のミスマッチが原因での離職を防ぐには、実際の業務内容を細かく伝え、採用コンセプトにも盛り込むことで、一貫性を持たせることが大切です。実情とかけ離れた採用ブランディングをおこなうことは、早期離職だけでなく、企業の信頼性自体も落とす可能性があるからです。
特に人が集まりにくい業界や業務の場合、自社の実情を発信しながら、社員が気持ちよく働けるように、どのような工夫をおこなっているかも伝える必要があります。自社のありのままの姿を伝えつつも、不利な部分を改善している内容や、メリットに転換していることを発信し他社との差別化としてアピールしていきましょう。
応募者数の母数を増やそうとするあまり、実情と乖離した採用ブランディングに陥らないよう注意しましょう。企業や業務内容の魅力的な面だけに焦点を当てて伝えるのではなく、実情に則した採用ブランディングをおこなうようにしてください。
特に、企業が従業員に何を提供できるのかという目線から、働く環境や、将来的なキャリアパスをありのままに伝えることも検討してみてください。
また、就業環境や業務内容について言葉で伝えるだけではなく、視覚的な効果を利用するのもおすすめです。自社に強く興味を持った求職者に応募してもらえるように、自社で働くイメージを伝える、写真や映像などを採用活動で使用するコンテンツに効果的に盛り込みます。
みんなの採用部では、採用ブランディングに役立つツールを数多くご用意しておりますので、合わせて活用してください。
視覚的なアピールを通じて、自社に興味を持つ求職者と興味のない求職者を選別し、効率的に採用活動をおこなうことにも繋がります。
継続的な広報活動で企業認知度アップを図る
採用ブランディングで策定した施策を継続することが、企業のブランド確立に繋がります。一貫した方針で継続的に採用ブランディングをおこなうことは、企業のイメージ定着に必要です。
企業のありのままの姿を発信し続けることで、採用コンセプトに共感した応募者のみがエントリーするようになり、より精度の高い選考ができるようになります。
とはいえ、求職者の間で企業イメージを定着させ、企業のブランド力を高めるためには継続的な発信が必要です。自社について、求職者に正しく認識してもらえるように、採用コンセプトを一貫させ、全社を巻き込んで発信し続けるようにしてください。
一貫したコンセプトで、絶え間ない採用ブランディングをおこなうことは、効果的な採用活動はもちろん、企業のイメージアップにも繋がります。
特に企業の知名度が低い場合、多くの人に注目してもらえるよう、絶え間ない活動が必要です。採用ブランディングの結果が出るまでに時間がかかることを頭に入れておき、早めに計画を立てるようにしてください。
PDCAを回しながら定期的に振り返り改善する
採用した求職者が順調に働いているか、就業環境は悪くないかなど、採用ブランディングでは定期的に振り返りをしながら、継続して取り組むことが必要です。社外だけを注視するのではなく、社内でのブランド化にも力を入れ、就業開始前後で情報に違いが出ないようにしてください。
採用ブランディングの精度をさらに上げるため、定期的に内容の見直しやブラッシュアップが不可欠です。求職者や社員へアンケートやインタビューをおこなうことで、定量・定性の両面から、振り返りと改善をおこないます。競合他社や社会の状況に合わせて、自社の採用マーケットでの位置付けを模索してください。
採用活動をおこなう中で、以下の傾向が見られるようになった場合は、特に注意をしてください。
・応募者数の減少
・応募者の質の劣化
・選考辞退者の増加
・内定辞退者の増加
・選考辞退や内定辞退に共通の傾向
採用ブランディングの効果が社内外で浸透し、結果が出るまでには少なくとも2年から3年はかかります。長期にわたってPDCAを回しながら、改善を重ねることで、より求職者に訴求する採用ブランディングを目指しましょう。
競合他社の中から求職者に自社を選んでもらえるように、定期的な振り返りと、絶え間ない改善が不可欠です。
5.まとめ
効果的な採用ブランディングをおこなうために、採用ブランディングとは何か、採用ブランディングの成功事例・失敗事例、採用ブランディングを成功させるためのポイントについて紹介しました。
現代は人々の働き方や生き方が多様化しています。自社にマッチする人材に入社してもらい、末長く働いてもらうためには、企業の魅力や価値観を明確化し、ブランドイメージの認知・浸透を図っていくことが求められます。
採用ブランディングは有効な手法である一方で長期的な視点が必要となり、工数やノウハウも必要になります。採用ブランディングに力を入れたくても人手が足りないという場合は、採用代行サービスを利用して採用のプロに採用業務の一部を依頼することも検討をおすすめします。
みんなの採用部では、採用戦略の立案を含めた採用代行サービスをご提案いたします。採用ブランディングの相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る