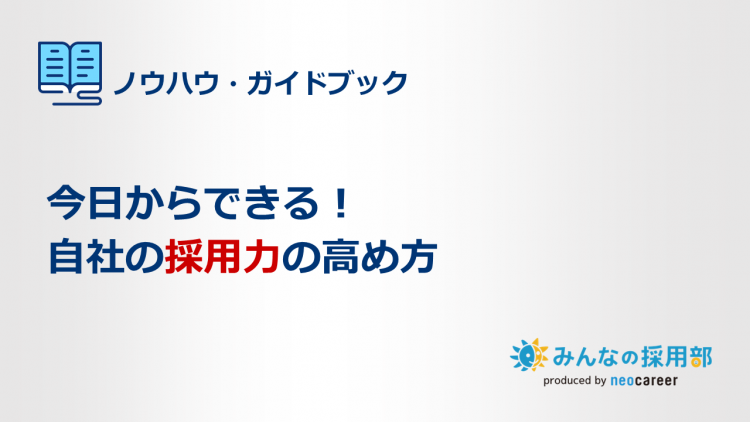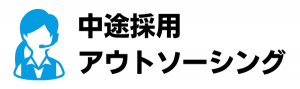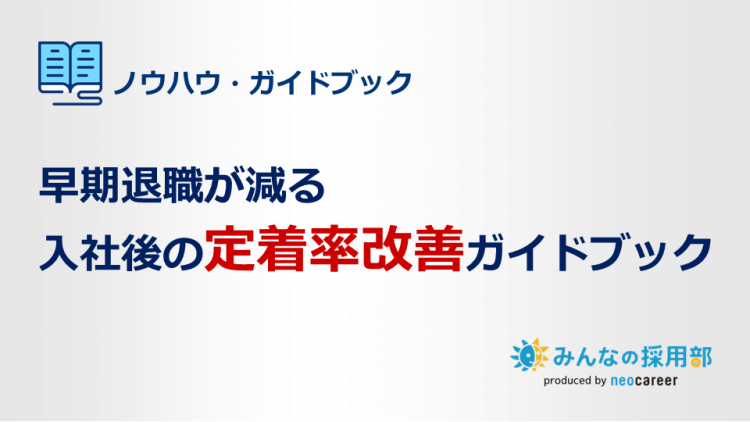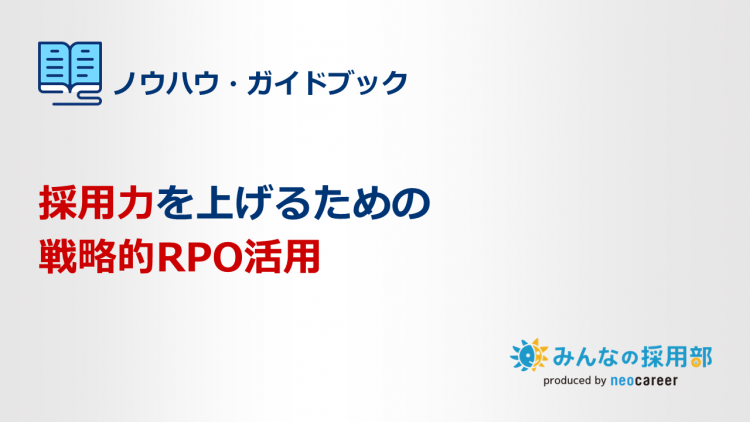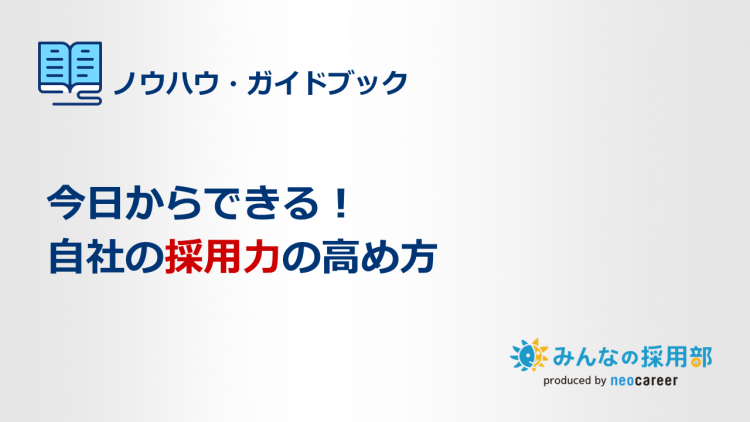効果的に社員の定着率を上げる方法とは?7つの対策と具体的な流れを徹底解説!
定着率を上げる
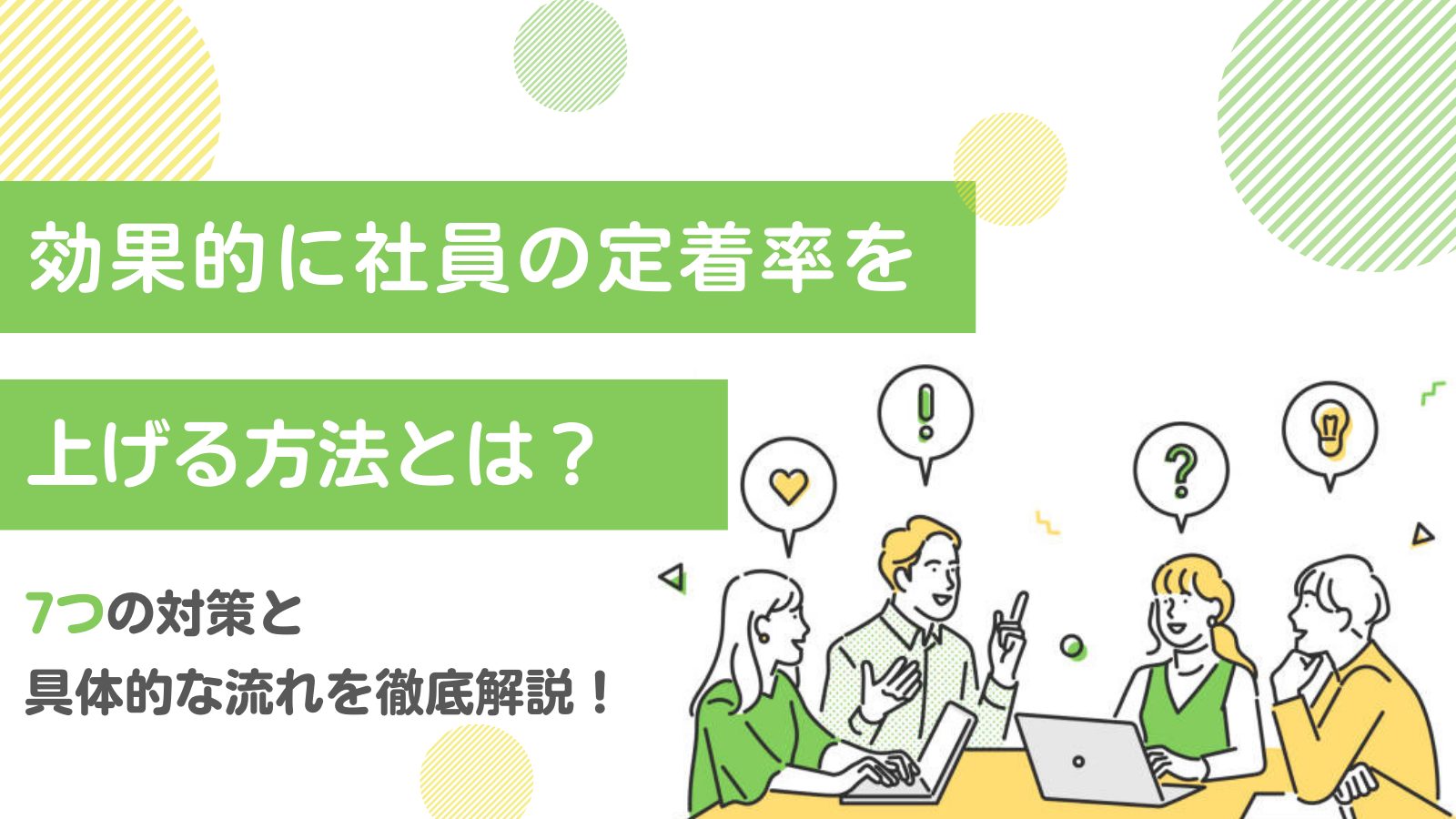
定着率を上げるには、全社をあげて取り組むことが重要です。しかし、実際は人事部が主導するケースが多く、通常業務に追われて定着率を上げる施策まで手が回らない場合があります。
そのため、定着率の改善に苦戦をし、社員の離職が増えて悩んでいる担当者も多いです。
本記事では
・定着率を上げる効果
・定着率を下げる主な原因
・定着率を上げる具体的な方法
についてご紹介します。
定着率を上げる方法について理解を深めると、社員のモチベーション向上やコスト削減にもつながる可能性があるため、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
目次
1.そもそも定着率とは

定着率とは、入社してから一定期間働き続けている社員の割合を示す数値です。定着率が高いほど社員の離職が少なく、組織体制が安定しているといえます。
定着率を公表している場合は、ほかの企業と比較されるため採用活動に影響が出る可能性があります。定着率の数値が高いほど社員にとって働きやすい環境であると判断できるため、求職者に対して効果的なアピールが可能です。
定着率と似た言葉に離職率がありますが、両者の違いについてよくわからない方もいるでしょう。ここでは定着率の計算方法と、定着率と離職率の違いについて詳しく解説します。
定着率の計算方法
定着率の測定開始日は企業によって異なりますが、一般的には年度初めの4月から起算し、1年、3年など一定期間を定めます。
定着率の計算方法は、以下の通りです。
【定着率(%)=(入社者の合計-退職者の合計)÷入社者の合計×100】
例えば、4月に入社した人数が200人、翌年3月までに退職した人数が40人の場合は、定着率は【(200-40)÷200×100=80%】となります。退職者が少なくなるほど定着率の割合は高くなるのです。
厚生労働省が発表した令和4年雇用動向調査結果の概況によると、2022年時点の国内全体の従業員定着率平均値は約85%です。国内全体の平均値よりも値が高いと、他社よりも定着率がよいといえます。
定着率と離職率の違い
離職率とは定着率と対になる指標で、一定期間に離職した社員の割合を示したものです。一定期間内で定着している社員の数に着目した指標が定着率、離職した社員の数に着目した指標が離職率です。
定着率と離職率を合計すると必ず100%になるため、【離職率(%)=100-定着率】で計算できます。例えば、定着率が85%だった場合、同じ期間の離職率は15%です。
参考に、平均離職率も紹介します。前述した厚生労働省の令和4年雇用動向調査結果によると、2022年時点で国内全体の平均離職率は15%でした。
離職率が高いと定着率が低い企業と見なされます。労働環境が不適切など組織内に問題を抱えている可能性があります。
2.定着率を上げることで企業が得られる5つの効果
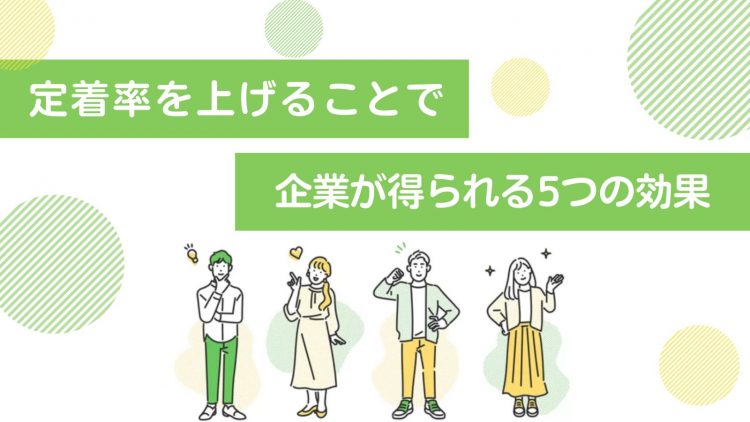
定着率を上げることで、企業にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、定着率を上げることで企業が得られる5つの効果について解説します。
人材流出の防止
定着率を上げることで離職による人材不足が解消されるだけでなく、社内技術やノウハウが社外へ流出するのを防げます。社員は企業を支える重要な資産であり、事業を継続・拡大させるためには欠かせない存在です。
しかし、優秀な社員が退職すると業務が滞ったり、社内技術やノウハウが社外へ流出したりして事業運営に影響を与えかねません。
長年働いてきたベテラン社員の退職と同時に、顧客や取引先とのつながりを失うこともあります。とくに、社員数が少ない中小企業では致命的なリスクにつながる恐れがあるのです。
知識と経験を蓄えたベテラン社員が自社に定着することで、組織や業務を安定させて将来の経営リスクを軽減できます。
コスト削減
社員の定着率を上げることで、結果として人材コストの削減につながります。
採用活動をすると、求人掲載料や人材紹介会社への出費、新人への教育コストなど膨大な費用がかかります。採用や教育を担当する社員の人件費も発生するうえ、新入社員が一人前になるまでには時間がかかるので、コスト回収には数年ほど必要です。
就職みらい研究所が発表している「就職白書2020」によると、中途採用の平均採用コストは1人あたり103.3万円という結果が出ています。1人退職する度に、この採用コストが全て無駄になります。
定着率を上げることで、社員の離職を防げるだけでなく採用コストを抑えられるので、企業資金を有効活用でき業績の成長にもつながるのです。
従業員のモチベーション維持・向上
定着率を上げると組織や業務が安定するため、既存社員のモチベーション維持・向上につながります。
定着率が高い企業は社員にとって働きやすい環境が整っており、組織に対する不満が少ないため仕事へのモチベーションが向上しやすいです。
モチベーションが高い社員が増えることで職場の雰囲気が明るくなり、一人ひとりが主体的に業務に取り組むようになるなど、組織全体に好循環を生み出せます。
一方、定着率が低い状態が続くと、残された社員は不安やストレスを感じやすくなり、組織全体の士気が下がる傾向にあります。とくに、影響力の大きい社員の離職は企業にとってもダメージが大きいものです。
定着率を上げると社員全員が安心して働けるようになり、仕事へのモチベーション維持・向上が期待できます。
生産性向上
社員の定着率を上げると、経験豊富で熟練スキルを持つ人材が社内に増えるため、業務の生産性の向上に期待できます。
業務に対して適正な人数を維持すると社員の負荷が重くならず、安定して仕事を進めることが可能です。また、自社に長年働く社員は業務に対する理解が深く経験豊富であり、社内技術やノウハウを多くの社員に引き継ぐことができるので組織全体の生産性が向上します。
一方、定着率が下がると離職による引き継ぎ作業が増えてしまい、業務が滞るリスクがあります。社内でノウハウが蓄積されないため、商品やサービスの品質低下につながりかねません。
定着率を上げることで、安定した業務進行と社内にノウハウが蓄積されるという恩恵を受けられます。
企業イメージ向上
定着率を上げると働きやすい職場だというよい印象が持たれるため、企業イメージの向上につながります。
多くの求職者は、できるだけ長く働きやすい職場で仕事したいと考えています。定着率が高い水準であることを数字で表せば、求職者に自社の魅力が伝わりやすくなり効果的です。結果、新卒社員や中途採用の応募が増え、社外から優秀な人材が集まる可能性もあります。
近年では、インターネットが発達したことによってSNSなどに企業の口コミを投稿する方が増えています。離職者が増えると口コミ投稿によって悪い印象が広がり、自社の求人や集客に悪影響を与えかねません。
定着率を上げることで企業イメージが向上し、求職者や顧客によい印象を与えられます。自社をより魅力的に伝えるために、戦略的にアピールすることも重要です。
効果的な採用ブランディングについても解説しているので、気になる方はぜひ下記記事も参考にしてください。
3.社員の定着率を下げる主な原因
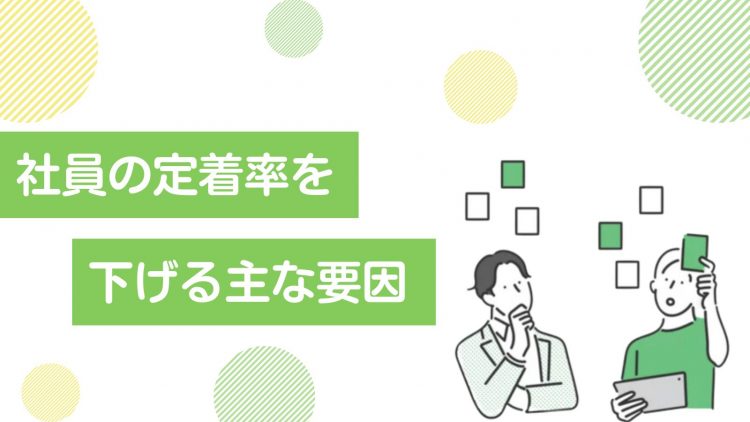
社員の離職が続くことで、自社の定着率が下がります。では、具体的にはどのような理由で社員が退職していくのでしょうか。
ここでは、社員の定着率を下げる主な6つの原因について解説します。
評価基準が曖昧
評価基準が曖昧だと、社員が正当に評価されていないと自社に不満を抱き、離職につながりやすくなります。
営業職のように結果が数字で現れる部署であれば評価しやすいですが、事務職や福祉職など数値化しづらくチームで成果を出す職業の場合は、個人への評価が難しくなります。
組織への貢献度なのか、成績なのかといった明確な基準を設けなければ、社員はどこに力を注げばよいのかわかりません。評価基準があいまいでは人事評価の結果に納得しづらくなり、業務へのモチベーション低下につながります。
また、評価基準が明確であったとしても社内全体に周知していなければ、評価に至った経緯が不透明なので社員は改善点を見出せません。結果、社員は評価者への不満を抱いて離職を考えるようになります。
人材育成の体制が整っていない
人材育成の体制が整っていないと、社員がスキルアップの機会を得られず定着率が下がる要因となります。
企業によっては、そもそも人材育成の体制が整っていなかったり、人手不足で社員教育ができなかったりする場合があります。
例えば、「業務をこなせば必要な知識や経験は自然に身につくだろう」という考え方では、新入社員はただ言われたことをこなすだけなので、やりがいや目標を持てません。
また、マニュアルなどはきちんと用意できていても、人手不足によって指導できる社員がいないケースもあります。新人は適切な教育を受けられないまま業務をすることになり、ミスが発生しやすくなるのです。
このような状態が続けば、採用してもすぐに社員が辞めていくことになり、定着率の低下につながります。
職場の人間関係が悪い
職場内における人間関係の悪さは定着率を下げる大きな要因となります。
例えば、上司と意見が合わない、腹を割って話せる仲間がいない、いじめが横行しているなど、人間関係が上手くいかないとストレスがたまりモチベーションが低下し、離職につながりやすいです。
社員同士の仲が悪いとコミュニケーションが円滑におこなわれなくなり、業務効率や品質の低下、社員の健康に悪影響を及ぼすといったデメリットが発生します。
業務に必要な情報共有がされず、ミスが頻発するようになり自社に大きな損失を招くこともあります。また、仕事のストレスによって社員が病気になり、退職するケースも少なくありません。
働き方の多様化に対応していない
自社が働き方の多様化に対応していない場合は、社員のモチベーションが低下し定着率が下がることがあります。
働き方改革関連法案施行や新型コロナウイルスの蔓延などをきっかけに、多くの企業で働き方の多様化が求められています。さらに、少子高齢化社会が進んだことで労働人口が減少し、労働力の確保は企業にとって大きな課題です。
仕事第一主義から脱却しワークライフバランスを重視する方が増えたことにより、テレワークやフレックスタイム制度など柔軟な働き方への対応が必要とされています。
しかし、働き方の多様化が進まず労働環境を改善できていないと、社員が自社へ不満を抱くようになり、離職につながる場合があります。
求人情報と仕事内容に乖離がある
求人情報と実際の仕事内容に乖離があると、社員は自社へ不信感を抱くようになり退職を考えるようになります。
採用活動をする上で、応募者の母数を増やすために自社の魅力を積極的にアピールすることは大切です。しかし、よい部分だけに偏った情報を発信していると、採用のミスマッチが発生する場合があります。
入社後に労働条件のギャップを感じたり企業イメージが異なったりすると、社員のモチベーション低下につながりかねません。
また、コミュニケーションが不足し応募者のニーズを十分に汲み取れていないと、本人が希望する部署や業務を担当させられないため、業務のミスマッチが発生します。
面接の際に、採用担当者が応募者に対して寄り添えていないと、選考辞退してしまったり他社に人材を奪われたりすることもあり得ます。
選考辞退を防止する具体的な方法が気になる方は、ぜひ下記の記事も参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
ハラスメントが横行している
既存社員がハラスメントに対する意識が低く、企業側も改善への取り組みが遅れている場合は、新入社員がストレスを理由に離職する可能性があります。
ハラスメントの代表的な例として、パワハラがあげられます。社員同士のコミュニケーションが少なく良好な人間関係を築けていない、過重労働など労働環境が悪い職場ではハラスメントが起こりやすいです。
安心してコミュニケーションが取れない環境では社員が萎縮してしまい、質問や適切な情報共有ができなくなります。多くのストレスを受けた社員はやがて疲弊し、離職を考えるようになります。
4.定着率を上げる方法7選
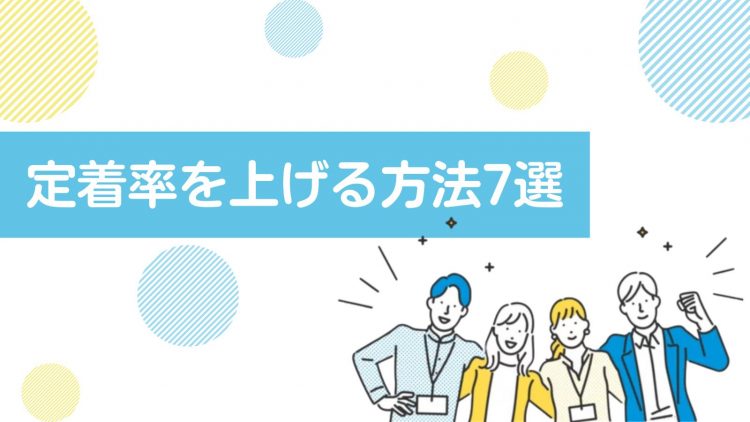
社員の離職を防止し自社の定着率を上げることは、企業にとって重要な課題です。ここでは、定着率を上げる方法を7つ解説します。
評価基準を見直す
自社の定着率上げる効果的な方法の一つとして、評価基準を見直すことがあげられます。
評価基準があいまいな場合は、できるだけ具体化することが大切です。全ての社員が「このような行動をとれば評価される」と理解できるように、項目を細分化することで評価結果に対して納得できるようになります。
また、職種や階層によって評価基準が異なるため、細やかな指標の調整が必要です。特定の評価指標に偏っている場合は、360度評価など複数の指標を組み合わせると効果的です。
評価基準を見直したら、社内全体に公開し浸透させます。透明性が高くなると管理職も部下に評価基準への理解を促しやすくなり、社員が人事評価に納得できるようになります。
社内コミュニケーションを活性化させる
社内のコミュニケーションが活性化されると社員同士の人間関係が良好になり、結果として定着率が上がります。
例えば、上司と部下が1対1で面談をおこなう1on1ミーティングや、サンクスカードなどが効果的です。1on1ミーティングは通常の会議と異なり、上司が部下の状況を把握したりマネジメントをおこないます。業務についての相談だけでなく、プライベートのことも気軽に話せる場として設けることで、両者の仲が深まり安心して仕事に取り組めるようになります。
サンクスカードは、社員同士がお互いに仕事への努力や成果を評価する制度です。お互いを褒め合うことで、仕事へのモチベーション向上につながります。
このように、日頃からコミュニケーションを活性化させ、気軽に相談しあえる環境が整うと企業への愛着が湧き、定着率が上がります。
ワークライフバランスを支援する
社員のワークライフバランスを積極的に支援することで、結果的に自社の定着率が上がります。
ワークライフバランスとは、仕事と私生活の調和がとれ両立できている状態のことです。例えば、育児や介護などのライフステージに合わせたり、家族との時間や健康維持のための十分な時間を確保できていれば、ワークライフバランスが実現できているといえます。
具体的な施策として、テレワークやフレックスタイム制度、時短勤務制度、長時間勤務の抑制などがあげられます。
企業側が積極的なサポートをおこない社員のワークライフバランスを実現できれば、仕事へのモチベーションが向上し、業務効率の上昇や生産性向上が期待できるでしょう。優秀な人材が定着すれば、採用コストや教育コストを抑えることも可能です。
スキル向上の支援を積極的におこなう
社員に対するスキル向上の支援を積極的におこなうことで生産性が向上し、人員を増やさずとも効率的に業務を促進することが可能です。
社員に業務で必要な知識や経験を習得してもらい、高いスキルを持つ社員が増えることにより、限られた時間の中でより効率よく利益を生み出せます。商品やサービスの質が向上し、顧客満足度にも貢献できます。
高いスキルを持つ社員を増やすには、継続的な支援が必要です。社内研修や外部講座の充実だけでなく、資格取得支援制度など社員のモチベーションを高める施策も求められます。
自らスキルを向上させようという意欲を引き出すことで、結果として高いスキルを持つ社員が増え、優秀な人材の定着に期待ができます。
給与や福利厚生を充実させる
社内から待遇について不満の声が上がっている場合は、給与や福利厚生の改善を図る必要があります。
給与に関しては、賃金の見直しやインセンティブ制度導入が効果的です。とくに、インセンティブ制度は勤続年数に関係なく個人の業績が反映されるので、自分の努力を正当に評価してほしい社員にとってモチベーション向上につながります。
組織内で切磋琢磨しあう環境を作りだせ、社員のスキルの底上げも期待できます。福利厚生に関しては、家賃補助や特別休暇など多くの社員にとって魅力的で愛用できる制度を充実させましょう。
各種手当や休暇を充実させると社員の満足度が高くなり、定着率を上げることが可能です。
求人や採用時におけるギャップをなくす
定着率を上げるためには、採用後のミスマッチや入社後のギャップをなくすことも重要です。
採用におけるミスマッチで多いのが、現場が求める人材と人事・経営陣が求める人材の認識にズレがあるケースです。実際に求めているスキルや現場の働き方など、現場社員と採用担当者で綿密に情報共有しておきましょう。
また、求職者に何としても入社してもらおうと自社のよい面しか伝えないことで、入社後のギャップが生じやすくなります。自社の魅力を伝えつつも、ギャップが生じやすい部分や大変な部分も一緒に伝えるとよいです。
求人票や企業ホームページなどで自社の情報発信量が少ないと、求職者は楽観的な予測に基づいて情報を解釈することがあるため、十分な情報を発信しましょう。
採用ターゲットを明確化させる採用ペルソナの設計は、採用後のミスマッチを防ぐ重要な役割を果たします。採用ペルソナの作り方についても解説しているので、気になる方はぜひ下記の記事も参考にしてください。
- あわせて読みたい記事はこちら
従業員エンゲージメントを高める
従業員エンゲージメントを高めると、結果として社員の定着率を上げることができます。
従業員エンゲージメントとは、社員が企業理念やビジョンを理解したうえで共感し、信頼する組織の為に自主的に行動しようとする意欲のことです。社員が自社の理念を理解し共感することで組織の一員としての自覚が高まり、自社に貢献しようと主体性をもって仕事にいそしむようになります。
従業員エンゲージメントを高めるには、企業理念やビジョンを明確にして自社の思想や将来の展望を広く周知することが大切です。また、基準が明確で公平性の高い人事制度を採用することで、社員が適切に評価されていると感じます。
自社に貢献したいという気持ちが強くなれば、社員の定着率が上がります。
5.定着率を上げる具体的な流れ
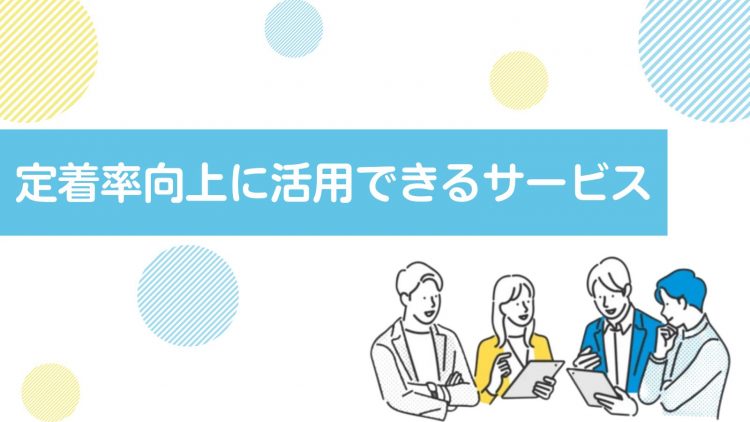
定着率を上げるために、具体的にどのような行動をすればよいでしょうか。ここでは、定着率を上げる具体的な流れについて解説します。
定着率の現状を把握する
定着率を上げる最初の段階として、現在の定着率を把握しましょう。
社内データに基づいて定着率を算出し、同業界の平均的な定着率と比較することで、自社の実態が見えてきます。
企業の規模が大きい場合は、雇用形態、部署、年齢別などさまざまな角度から人材の定着率を算出しましょう。データを細分化して分析することで、定着率が低下している箇所がわかりやすくなります。
効率的な作業をおこなうために、タレントマネジメントシステムなど社員の情報を一元的に管理・共有できるツールを活用するとよいです。
離職理由を分析する
定着率を上げる次の段階として、離職理由を分析しましょう。
分析したデータを基に退職者の離職理由や傾向を知り、自社の課題を明確化することが大切です。福利厚生の水準やキャリアへの不安、人間関係、採用のミスマッチなど、さまざまな仮説を立てます。
しかし、一般的な方法や憶測で改善策を立てても、効果を得られない場合があります。データが不足している場合は、退職する社員に面談やアンケートをおこない、何が原因で離職したのか調査するとよいです。
また、在籍している社員に対して定期的に満足度調査を実施して情報収集するといった施策も有効です。社員の離職理由を明確化すると、効果的な施策を立てることができます。
定着率を上げる施策を立てて実行する
調査や分析によって得た情報を基に、定着率を上げるための具体的な目標と改善施策を立てましょう。
「1年間で定着率を10%を上げる」といった具体的な目標を掲げることで、進捗状況を振り返りやすくなります。
離職理由に応じて、有効な改善施策を導入することも重要です。例えば、定着率低下の原因が人事評価である場合は、MBO(目標管理制度)や360度評価など人事評価を改善する施策を実行すると効果的です。
ただ、現状を分析するとさまざまな課題が浮き彫りになり、何から着手すべきか迷うことがあるでしょう。
あらかじめ課題の優先順位を評価し、どの課題から取り組むべきか決めておくと、効率的に施策を実行できます。
定期的に効果測定をおこなう
定着率を継続して維持するためには、施策内容の定期的な見直しが必要です。
一度だけ施策を実行して満足するだけでは、社員の定着率を維持できない可能性があります。四半期や半期ごとに施策実行時の課題を洗い出し、効果を検証することが重要です。
定着率に変化があったのか、定期的にデータを収集しておくと後から分析しやすいです。改善効果が見られないのであれば、再度課題を洗い出してから施策を実行しましょう。
また、定期的に社内アンケートを実施し、社員満足度や従業員エンゲージメントの計測をすることで、課題点の早期発見が可能です。施策の見直しと改善を継続的におこなうことで、定着率の維持につながります。
6.定着率向上に活用できるサービス
定着率を上げるための施策は、全社をあげての一大プロジェクトです。企業によっては、カルチャー浸透や人事制度の抜本的改革のために、専門部署を立ち上げることもあります。
しかし、実際は人事部が主導でおこなうケースが多いため、業務量過多になりがちです。また、自社の人手不足が原因で改善施策まで手が回らない場合もあります。
今すぐにでも、定着率を上げる効果が見込める施策を実行したいと考えているのであれば、アウトソーシングなど外部サービスを活用するのがおすすめです。自社の一部業務を外部の専門会社へ委託することで、ノンコア業務の削減やルーティンワークの削減を実現し、自社のコア業務に専念できます。
ネオキャリアの採用代行サービスは、アウトバウンドやインバウンドにも対応が可能なので、即戦力を求めている方はぜひ検討してみてください。
7.まとめ
効果的に社員の定着率を上げる方法や定着率を下げる原因、具体的な流れなどについて詳しくご紹介しました。
定着率を上げることで、人材流出の防止や人材コストの削減、社員のモチベーション維持向上、生産性向上、企業イメージ向上と多くのメリットがあります。社員が離職する原因を突き止め、それぞれに合った効果的な施策を実行することで定着率を上げることが可能です。
定着率を上げるための施策は社内全体でおこなうべきですが、実際は人事部が主導でするケースが多く、人手不足により業務量過多になりやすいです。
ネオキャリアのアウトソーシングサービスを活用することで、自社のコア業務に専念できます。ぜひ無料相談をご活用ください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る