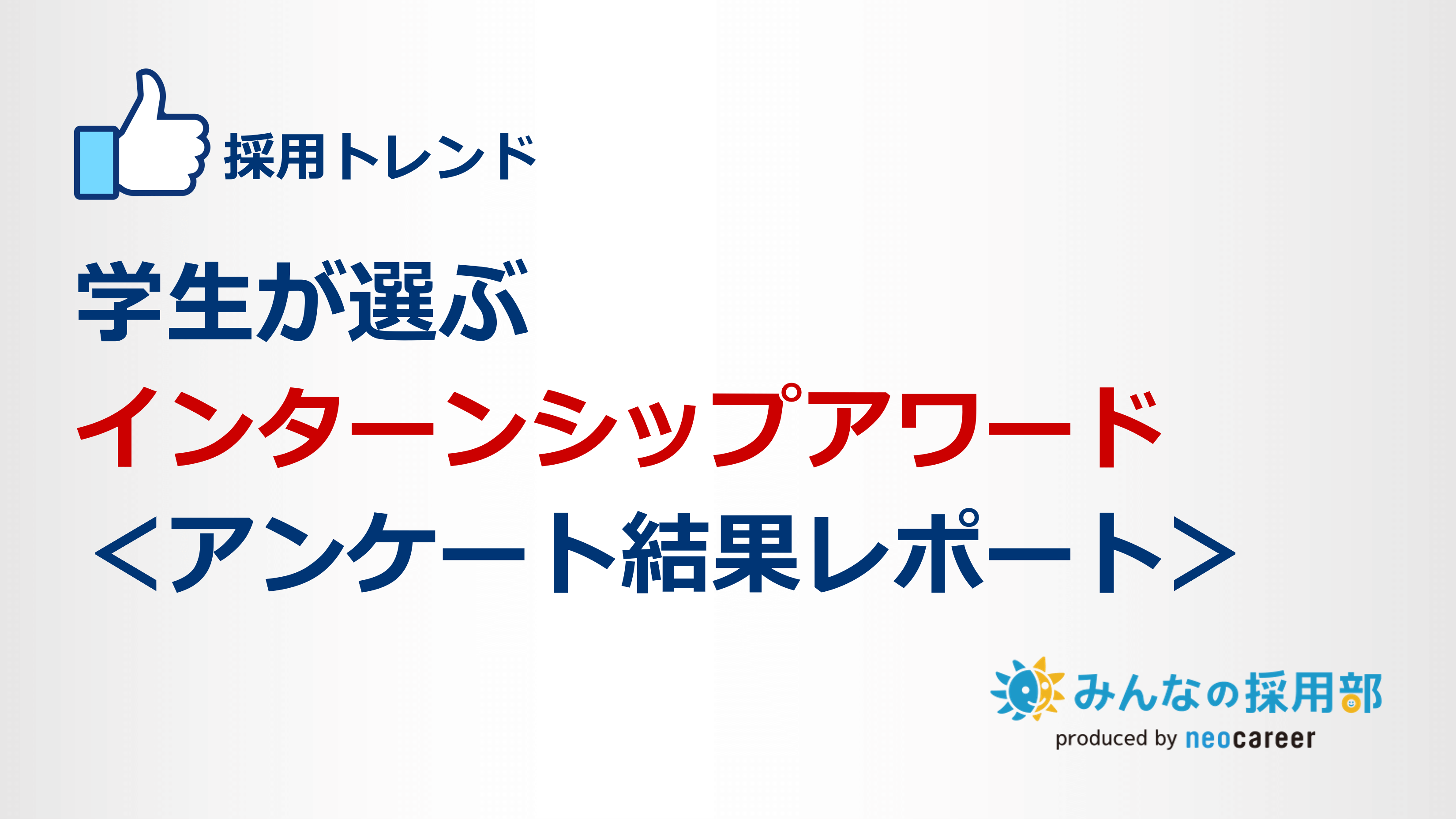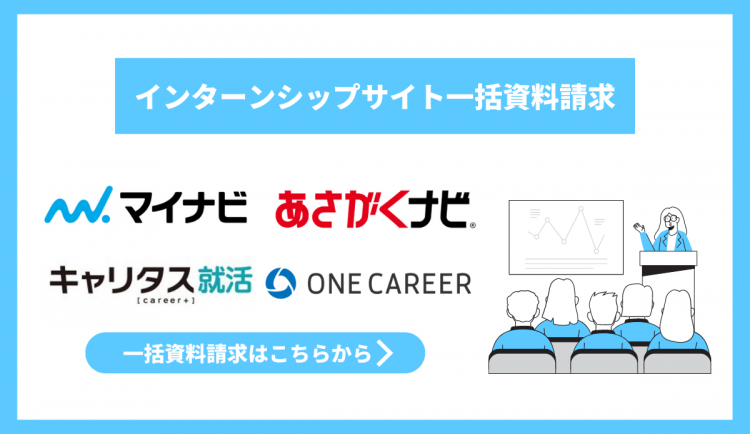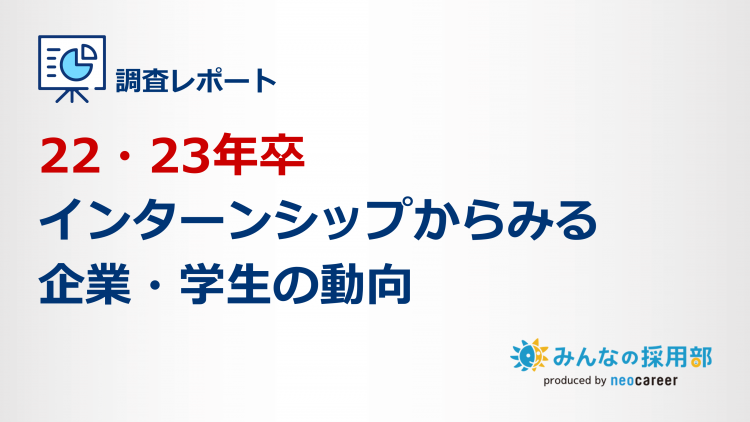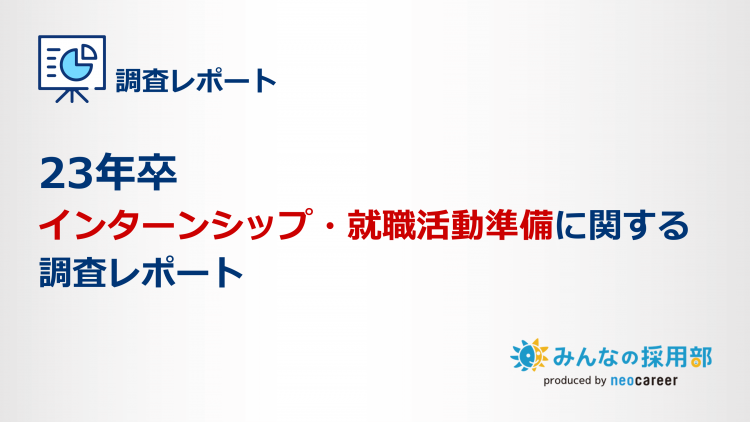インターンは40%以上が1DAY!?|インターンシップ他社事例
更新日:
インターンシップ事例
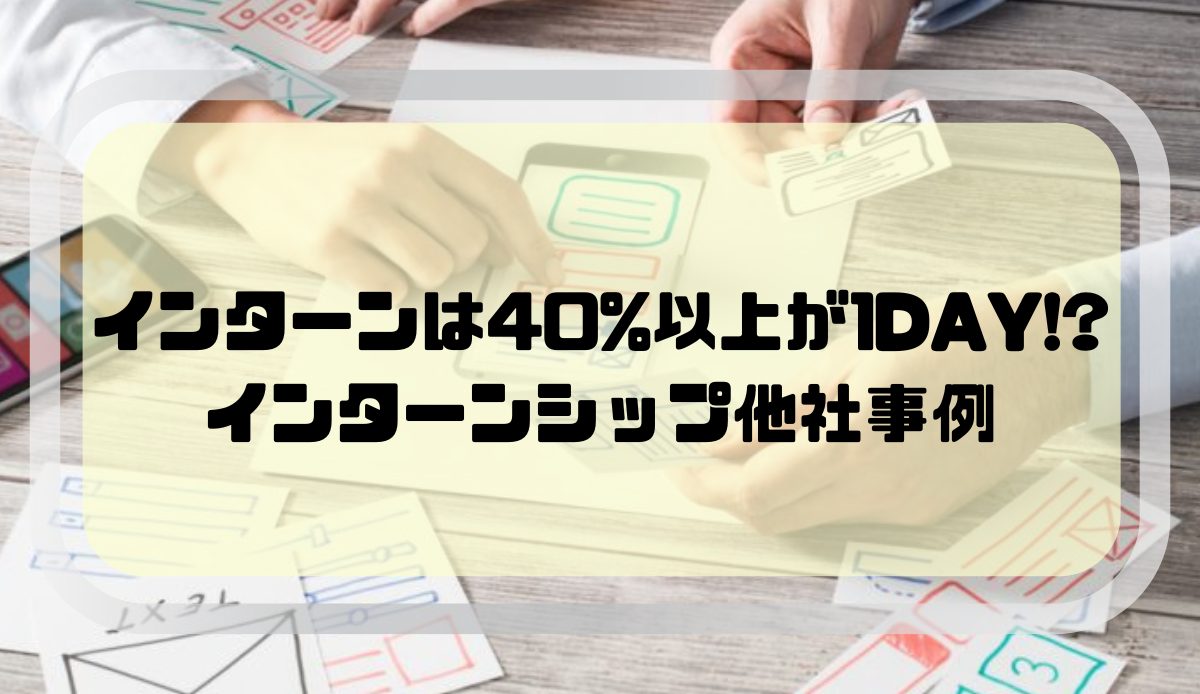
2025年卒採用から、インターンに参加した学生の情報を採用選考に利用することが認められることとなりました。今後は採用直結型のインターンが増えると予測されます。新卒の就活ルールを振り返ると、2018年に経団連は「就活ルール」の廃止を発表しました。「就活ルールとは」企業の採用活動に対し決められていたルールで企業説明会や採用面接の解禁日のほか、内定日が定められていたものです。
しかし、急激なルール変更は学生のみならず企業側にも混乱を招きかねないという理由から、2023年卒の就活ルール(解禁日)は現行日程を踏襲する方針が表明されています。では実際に、これからの新卒採用をどう考えていけばよいのでしょうか。そこで今回は、インターンシップに焦点をあて、どのようなインターンシップをおこうなうのか調べてみました。
本記事では
・インターンシップをおこなう目的
・インターンシップ情報を掲載している企業の状況
・実施期間、受け入れ人数にみるインターンの傾向
について解説していきます。
目次
- 【資料ダウンロード】学生が選ぶインターンシップアワード/アンケート結果
学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシッププログラムを表彰する、日本最大級のアワードです。
学生にどのようなインターンシップが人気なのか、他社インターンシップを参考にできるよう資料を準備しました。ぜひ参考にしてください。
1.インターンシップをおこなう目的

インターンシップとよく耳にするようになりましたが、そもそも「インターンシップ」とはどのような目的があるのでしょうか。
1‐1.採用の一環として
インターンを志望する学生は、意識が高く優秀と言われる学生が多い傾向があります。
そのような学生たちと早くから接点をとって自社の採用につなげようという狙いがあります。
ダイヤモンド社の記事によると、「大手企業の8割がインターン生に内定を出す」※というデータも出ており、インターンが採用に直結していることは明白です。
さらに、ユニークなインターンシップを行っている企業は口コミで評判が広がり、採用ブランディングにもつながります。
※引用:DIAMOND online大手企業の8割がインターン生に内定を出す
1‐2.社会貢献活動として
学生に就業体験の場を提供することも、企業の重要な役割の1つではないでしょうか。
学生が、企業や仕事というものに対し理解を深めることで、しっかりとした意図をもって就活に臨むことができます。
そうすることで、入社後にギャップが少なくなり、早期離職を防ぐことにつながり、また入社後も成長し続けられる人材になることでしょう。
長期的に見ると、インターンで学生を受け入れることは、次世代を支える人材育成のために大きな役割を果たすと、期待されています。
1‐3.仕事のサポーターとして学生の力を借りる
飲食・飲料、エンタメ、各種メーカー、サービス業など、学生の視点を商品開発の参考にしたいと考える企業もあります。
実際に学生からの意見を活用してHITした商品もあり、アイデアのヒントがたくさん転がっているかもしれません。
また、若手社員のやる気や能力の向上にもつながります。
インターン生と接することで、社会人の先輩としての自覚が大きくなり、より魅力的なビジネスパーソンになろうと奮起することにつながったり、フレッシュな学生と接することでモチベーションが上がったり、インターン生の担当になることでマネジメントも経験することができます。
2.インターンシップ情報を掲載している企業の状況

2025年卒の学生たちにとって、インターンシップの意識はより高く重要なものに変化しています。
なぜなら、2025年卒の新卒採用選考からは、特定の条件を満たした場合、インターシップでの情報を採用選考に利用することが認められたからです。
つまり、インターシップが採用選考の評価に直結する可能性が高まり、インターンシップの重要性もまた高まっているのです。
そうしたなか、インターンシップを導入する企業も増えているのですが、現在注目されているのが短期間のインターンシップです。
就職みらい研究所※1によると、2024年卒の学生たちの94.1%が1Dayインターンに参加しており、企業にとっても1Dayインターンは、長期的なインターンシップに比べ準備にコストや手間がかからず導入しやすいため、実施割合が大きくなっているのではないでしょうか。
また、マイナビ※2の調査では31.4%の学生たちが「2~3日程度の就業プログラムインターンシップ」に参加したいと回答しており、数日単位の短期インターンシップも学生と企業側からの需要が高まっています。
インターンシップの開催規模について一概には結論は出せませんが、1週間以内のインターンは1回の受け入れが10名以下の少人数制のものから、30名以上~100名規模のものまで幅広く実施されているように見受けられます。
1週間~1ヵ月以上の長期インターンシップでは1回の受け入れ人数も限られるため、1回で20名以下の受け入れが多くなっているように感じます。
※1参考:就職みらい研究所【2024年卒 就職活動TOPIC】 3月時点でのインターンシップ等の参加割合は約9割.pdf
※2参考:マイナビマイナビ 2025年卒 大学生 インターンシップ・就職活動準備実態調査(6月).pdf
3.実施期間、受け入れ人数にみるインターンの傾向
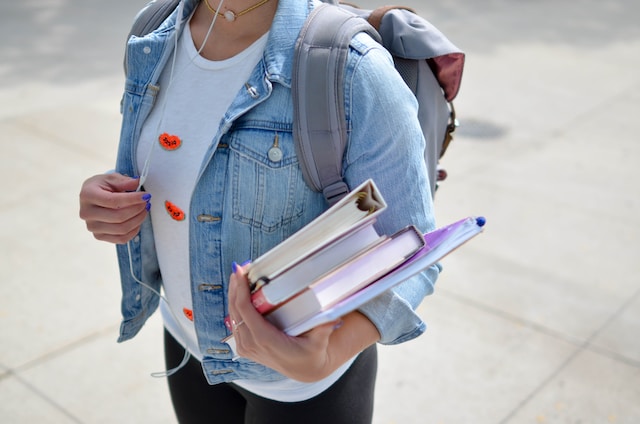
ここでは、企業の受け入れのキャパシティや人員体制などの事情がありますが、おおよその傾向としてまとめてみました。
ご参考までにご覧になっていただけると幸いです。
3‐1.インターン期間が1日~1週間以内で、人数は30名未満
1Dayインターンで30名未満の受け入れ人数の企業は、業界説明、自社紹介、先輩社員との座談会、就活ノウハウといったようなセミナー形式のものや、グループワーク形式のものが多く見られます。
さらに少人数になると、実際の執務スペースの見学や作業現場、店舗など、リアルなイメージがつくような職場見学・体験ができる内容のインターンを企画している企業もあります。
2~3日の期間のインターンになると、もう少し業界や自社の業務内容に関してより深く理解してもらうよう、時間をかけた濃いグループワークや職場見学を行っています。
さらに宿泊型のインターンを行う企業もあり、宿泊代は企業負担となるところが多い模様です。
少人数で行うことで、学生一人ひとりに対してしっかりとコミュニケーションをとれることや、「少人数制」と打ち出すことで特別感の醸成にもつながります。
3‐2.インターンの期間が1日~1週間以内で、人数は30名以上
1回の受け入れ人数が30名を超える企業も上記と同様に、就活セミナーや業界・仕事理解セミナー、グループワークといった内容のインターンが多い傾向が見られます。
また、5日間かけて戦略的なフレームワークから事業の企画提案を行うようなインターンや、宿泊型のインターンもありますが、さすがに1回で50名以上の受け入れを行っている企業は少ない模様です。
受け入れ人数が多ければ、当然接点を持てる学生が多くなるということがメリットに挙げられます。
ただし、人数が多ければ多いほど、受け入れ場所などの問題で企画内容が制限されるデメリットもあるのではないでしょうか。
3‐3.インターンの期間が1週間~1ヵ月以上で、人数は30名未満
こちらは長い時間をかけてインターンを行うことができるため、よりリアルな業務体験ができる内容を企画している企業が多くなっています。
たとえばドン・キホーテでは、仕入れ、販売、レイアウトなど店舗経営全てを自分たちで行う内容のインターンを、島津製作所では25もの研究ジャンルから自分のやりたいものを選択し、技術者と一緒に、研究、開発、評価などを体験できるインターンを企画しています。
このようなインターンは誰でも受け入れられるわけではないため、数ある応募の中から学生を選抜する必要があります。
そのため、書類、面接などの選考を経て、インターンに至るケースがほとんどです。
3‐4.インターンの期間が1週間~1ヵ月以上で、人数は30名以上
こちらも、長期のインターンになるため、宿泊形式のものや、OJT形式のものが多くありますが、受け入れキャパシティが他社と比べて余裕がある企業が該当します。
全体的な割合としては少ない印象です。
リクルートキャリアでは、9日間ミャンマーに滞在しインターンを行うといった、普段経験できないような内容のインターンを企画していたり、博報堂(HDY)も軽井沢での合宿形式のインターンを企画しています。
多くの学生と長期的に密に接点を持てるメリットがありますが、受け入れ体制に余裕のある企業でなければ実施が難しいでしょう。
また、インターンプログラムの企画に関しては以下を心がけてみてはいかがでしょうか。
- 自社の魅力や事業構造と直結するような内容を盛り込む
- 学生が親しみやすくエンターテインメント性ある形式にする
- 経営者層からの視点を上げるようなフィードバックや先輩社員からの現場の声を反映したフィードバックを行う
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
インターンに関しては、インターン専用のマッチングサイトの活用や自社ホームページのみで受付をしている企業もあり、さまざまな経路でインターンを受けれることが可能です。
ほとんどの企業はそこで学生と接点をもっておき、就活のタイミングで自社採用に呼び込もうと考えているかもしれません。
ちなみに海外、特にアメリカのインターンシップは、新卒一括採用といった文化がないため、自分で企業を探してインターンとして受け入れてもらい、そのまま雇用につながっているケースが多く、「採用直結型インターンシップ」のようなものがほとんどです。
そのため、インターンシップが企業と学生にとって重要視されており、「Google」や「Facebook」といった有名企業でのインターンシップともなると、月50万円以上の給料がもらえるとも言われています。
同様の手法をとることは難しくとも、インターンシップの内容次第では、採用ターゲットの絞り込みや惹きつけを行うことが可能です。
ぜひ今後のインターンシップ企画について検討してみてください。
- 【資料ダウンロード】学生が選ぶインターンシップアワード/アンケート結果
学生にどのようなインターンシップが人気なのか、他社インターンシップを参考にできるよう資料を準備しました。ぜひ参考にしてください。
<資料内容>
・インターンシッププログラム
・インターンシップを通して得られた効果・満足感
・インターンシップを経験したその後の変化
・効果的なインターンシップを設計・運営するためのチェックリスト

企業学生双方の素敵な出会いの実現を目指して
新卒で入社して以降、ずっと新卒採用支援事業に所属しています。より良い採用に向けて人事の方とご相談させていただく時間が大好きです。3年間の産休・育休で年子の女の子2人を出産し、今は育児・家庭と仕事の両立に日々奮闘しています!
- 名前
小泉/新卒領域
この営業が携わった他の事例・記事を見る