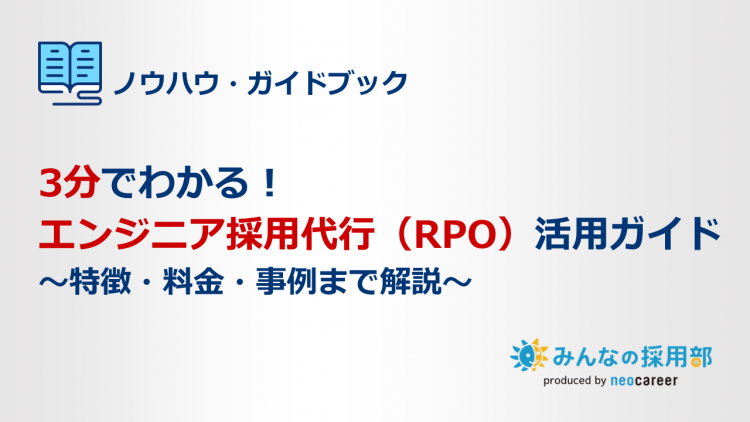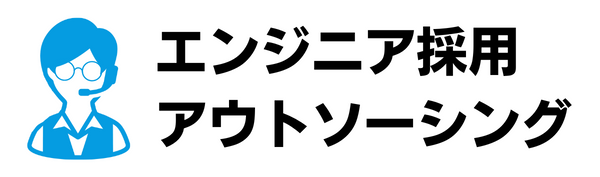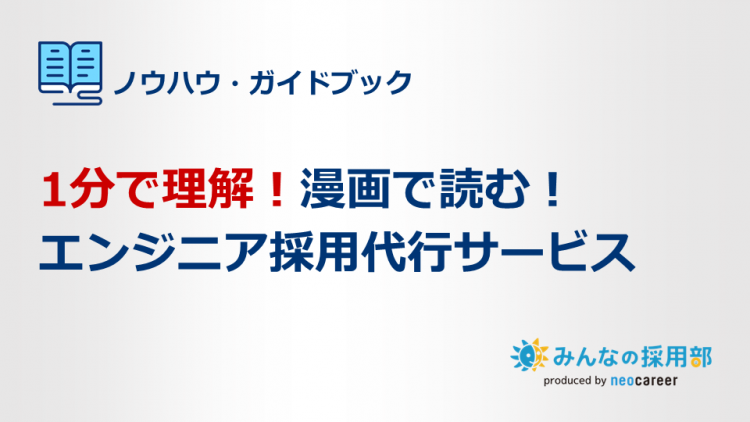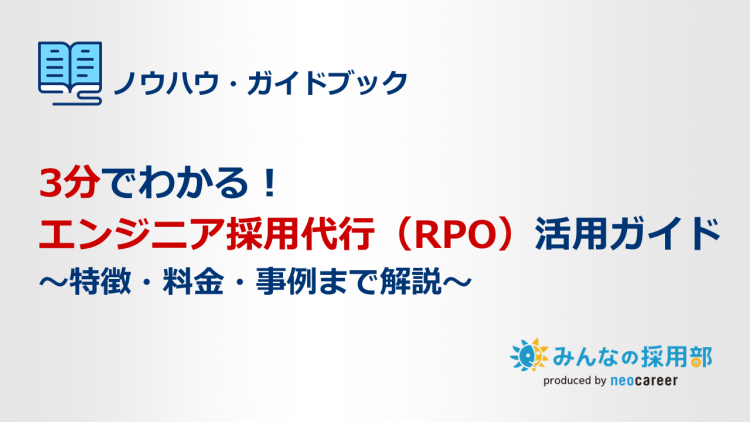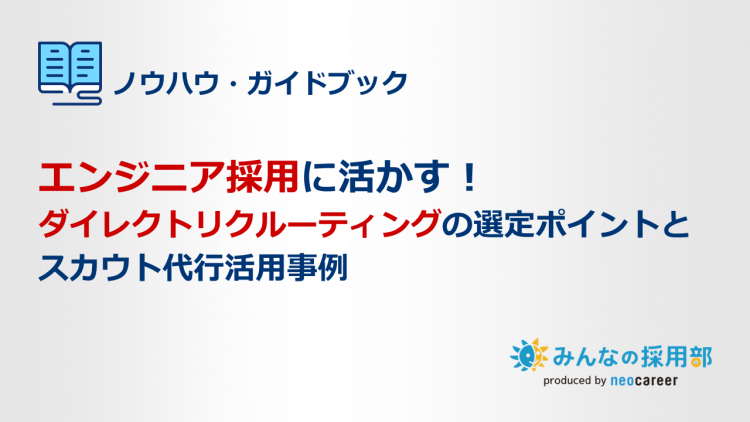エンジニア経験者を採用する方法とは?採用時の注意点や必要な知識をご紹介
エンジニア 経験者 採用
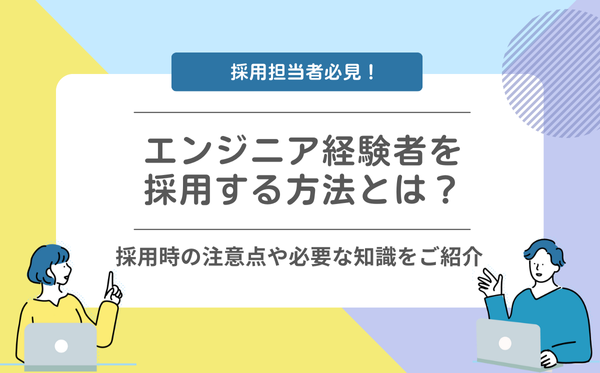
IT技術の進歩によりエンジニアの需要は日々高まっていますが、その反面IT業界ではエンジニア経験者の採用はもちろん、エンジニア志望の人材の採用にも苦戦を強いられています。
エンジニア経験者の母数が足りないため、企業も採用に苦戦するケースが多いでしょう。エンジニア採用においては、下記のような悩みを抱える企業が多くあります。
本記事では、
・面接で聞くべき質問8選
・採用の際に気をつけること
・エンジニア経験者を採用する方法
について解説しています。
また採用担当に必要な知識や、採用に関するトレンドについても紹介していますので、エンジニア経験者の採用の参考にしてください。
1.エンジニア経験者を採用する方法
エンジニアの人材不足が深刻な中、一般的な採用方法ではエンジニア経験者の採用は難しいでしょう。
エンジニア経験者を募集する際に有効な採用方法は以下のとおりです。
採用手法 | 特徴 |
| 求人媒体・広告 | メディアへの露出が増えるため、 エンジニアからの認知度向上に役立つ。 |
| リファラル採用 | 自社エンジニアからの紹介のため、 入社後のミスマッチ防止に繋がる。 |
| フリーランスエンジニア採用 | 経験豊富なエンジニアを 正社員よりも安価で採用できる。 |
| ダイレクトリクルーティング | 企業から求職者へ直接アプローチでき、 転職潜在層の採用にも有効。 |
| エンジニア採用代行 | エンジニア採用のプロが |
ぜひ自社の採用方法として取り入れていただき、希望のエンジニア経験者を採用しましょう。
1-1.求人媒体や広告の活用
求人媒体や広告の利用は、メディアへの露出が増えるため採用の確率が上がります。エンジニア経験者の採用において重要なのは、1人でも多くのエンジニアに自社の認識を促すことです。エンジニアを採用したい多くの企業は、メディアへの露出を増やすべくさまざまな手法を用いて採用活動をおこないます。
自社で応募ページを設けるだけではエンジニアの目に届きづらいのが現状です。転職に興味を持つエンジニア経験者は求人媒体やネットで企業を検索することが多く、求人広告内に提示されている条件と自分のスキルを照らし合わせ、会社で活躍できそうかどうか判断します。
求人媒体や広告内では会社が必要とするスキルを文章でアピールでき、採用後の条件も明確に表現できるので、エンジニア経験者が企業を選ぶ際の判断材料を増やせます。各メディアで自社のアピールができるよう、求人媒体への掲載や広告の利用は積極的におこないましょう。
ただし、求人媒体に転職情報を掲載する場合はコストがかかります。採用が長期化する場合はコストがかさむデメリットがあるので、注意しましょう。また採用広告の活用方法はチラシやポスター、新聞や求人情報誌への掲載など多岐にわたります。複数の広告を利用することは認知度の向上に役立ち、ターゲットとなる人材の採用にも有効なので、求人媒体への掲載と平行しておこないましょう。
1-2.リファラル採用の推進
リファラル採用とは、社内の人脈を利用して新たな人材を採用する手法です。人材不足が原因で採用が難航するケースが多い中、リファラル採用はエンジニア経験者の採用を効率よく低コストで進められます。すでに入社しているエンジニアからの紹介のため、知り合いがいるという点で、一から人脈を築く企業よりも入社のハードルは下がります。また、紹介者のエンジニアも交えて自社紹介をおこなうことで企業理解も進みやすく、ミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。
さらに求人媒体や広告を利用する場合と比較しても、費用を抑えることが可能です。採用にあまりコストを割けない企業や全体的に予算が少ないスタートアップ企業には、リファラル採用が向いているでしょう。
リファラル採用を推進する上では、採用が決まった際、紹介者にインセンティブのような形で一定の報酬を渡すことも効果的です。エンジニア経験者の人脈は貴重なので、うまく活用し採用を効率よく進めましょう。
1-3.フリーランスエンジニアの活用
中途採用においてなかなか経験者が採用できない場合は、フリーランスのエンジニアを採用するのも1つの方法です。専門性の高いエンジニアを、正社員よりも安価で採用できる可能性が高いため、コスト面では大きなメリットがあります。
仕事はプロジェクトごとに依頼をおこない、成果報酬もしくは時給制で報酬を支払います。繁忙期でエンジニアが欲しいのに採用が進まない企業にとっては、一時的にフリーエンジニアをプロジェクトに参加させることができるため、人員不足を即座に解消できるでしょう。
しかし、正社員ではないエンジニアはほかに待遇の良い案件がある場合そちらに流れてしまう場合があります。そのため長期的な関係構築が難しい点はデメリットといえます。フリーランスであっても十分にコミュニケーションを取り、単価交渉があった場合は相談に乗るようにすると、関係の構築もしやすくなるでしょう。
1-4.ダイレクトリクルーティングの活用
ダイレクトリクルーティングは、SNSやスカウトサイトを通じて求職者に直接アプローチする方法です。求人媒体や広告では基本的にエンジニアからのアクションを待つ形になるため、企業側から直接アプローチはできません。そのため、自社から求職者へアプローチしていきたい企業にとってはダイレクトリクルーティングがおすすめです。
求職者の中には、積極的に転職活動をおこなわず、希望に合う企業を見つけて初めて転職を意識する人材が一定数存在します。ダイレクトリクルーティングでは、あまり転職を検討しておらず転職市場にも出ないような潜在層にも企業側からコミュニケーションが取れるメリットがあります。
- 合わせて読みたい記事はこちら
1-5.エンジニア採用代行の活用
エンジニア採用代行は、エンジニアの採用活動をほぼすべて、もしくは部分的に代行会社に依頼できるサービスです。例えばエンジニア採用手法の1つとして解説したダイレクトリクルーティングは、専門職であるエンジニアの採用に向いていますが、アプローチ方法の構築にはある程度の工数とノウハウが必要です。そのため、初めてエンジニア採用に挑む場合、ダイレクトリクルーティングを用いての採用は難航する可能性があります。
エンジニア採用代行は、採用活動をほぼすべて代行できるので、工数やノウハウ不足も心配する必要がありません。また、採用活動の一部分だけをお任せしたい場合でも活用できます。採用代行会社を選ぶ際には、数多くのエンジニア経験者を採用してきたノウハウがある会社を選びましょう。
エンジニアの経験者採用にはエンジニアに関する知識と採用ノウハウが必要なため、実績がある会社であれば効率よくエンジニア経験者を採用できるでしょう。エンジニア採用代行は、理想とするエンジニア像は固まっていてもエンジニア経験者採用のノウハウがない企業にぴったりのサービスです。
2.エンジニア経験者を採用する際に気をつけること
エンジニア経験者の採用においては、注意すべき点がいくつかあります。注意点を理解しないまま採用活動を進めると採用がうまく進まなかったり、採用できてもミスマッチによる早期離職を引き起こしかねません。
また、未経験者採用の場合はスキルよりも成長意欲があれば採用に繋がることが多いですが、経験者採用の場合はスキルや過去の経験が重視されます。企業がエンジニアにスキルや経験を求めるのと同様に、エンジニアも企業に対して開発環境の整備や給与・待遇などを求めるでしょう。
エンジニア経験者を採用できるだけの環境が自社に整っているかどうか、事前に確認しておくことが大切です。エンジニアにとって魅力的だと感じる環境は以下の通りです。
- エンジニアへの社内理解が深い
- 社員同士でスムーズに連携できる体制が整っている
- 高スペックのパソコンやツールの導入など開発インフラが整備されている
未経験者採用と違って、エンジニア経験者の場合は求職者からも会社に一定の条件を求められるようになることを理解し、求職者と企業がお互いに納得して入社を決められるようにしましょう。
2-1.採用条件を明確化する
エンジニアが持つスキルは多岐にわたるため、企業が必要とするスキルを明確にしないとミスマッチが起こり、せっかく採用できたエンジニアの早期退職に繋がります。自社の事業内容や今後取り組む予定のある事業を元に、どのようなスキルを持ったエンジニアが必要かを明確にしましょう。
採用条件を明確に記載しておくことで、エンジニアも就職後のキャリアを具体的に描くことができ、応募に繋がります。また、スキルだけでなく入社後の配属先とのマッチや性格・志向などについてもしっかりと検討し採用条件を明確化させましょう。面接時は候補者とも携わりたい仕事やキャリアプランのすり合わせをおこない、ミスマッチを防ぐことも大切です。
レバレジーズが調査した「社会人エンジニアに聞く、企業の選び方」によると、エンジニア経験者が企業に求めることの代表例として、給与や業務内容、会社の技術力や成長が見込める企業かどうかが挙げられます。採用活動の際はエンジニア経験者が求める基準に合わせ、入社後の待遇や職場環境の整備がおこなわれているかをチェックし、アピールできるようにしましょう。
出典:レバテックルーキー調査「社会人エンジニアに聞く、企業の選び方」
2-2.エンジニア採用の相場を理解する
エンジニアの転職は人材不足の背景から売り手市場になっており、採用する企業側の希望を一方的に出すだけでは採用には至りません。人事に求められるのは、自社の強みとエンジニアのレベルを考慮して相場に合ったエンジニアの採用をおこなうことです。
株式会社ユニゾン・テクノロジーが調査した「IT エンジニアの平均年収ランキング」によると、経験者と未経験者のエンジニア給与相場は以下の通りです。
未経験者 | 250~400万円 |
経験者 | 393~636万円 |
出典:ユニゾン・テクノロジー「ITエンジニアの平均年収ランキング」
エンジニア経験者の給与相場はエンジニア未経験者と比較すると大きな開きがあることがわかります。上記の数値はあくまで平均であり、エンジニアの場合はスキルが上がれば収入も比例して上がっていく職業です。求めるスキルが上がれば、その分報酬も上げていかなければエンジニアの採用が難しいことを理解しておきましょう。
2-3.選考スピードを意識する
エンジニアは市場価値が高く、複数の企業から内定をもらっている場合がほとんどです。選考スピードが遅い場合、ほかの企業に取られてしまう可能性があるので注意しましょう。
株式会社overflowが発表している「エンジニアの採用スケジュールの例」によると、エンジニア経験者の採用は、一般的に下記のようなスケジュールで進んでいきます。
4月 | 採用計画の策定と共有 |
5月 | 募集要項の作成と出稿 求人用サイトの構築 説明会の実施 面接官の選出 |
6~7月 | 採用選考スタート (書類審査・適性検査・技術試験・面接) 内定者への内定通知 |
8~9月 | 内部定者フォロー 入社・入社手続き 採用活動の振り返り |
出典:株式会社overflow「エンジニアの採用スケジュールの例」
一般的には採用計画を立ててから入社手続きまで半年程度かかります。なお、実際に採用活動を始めてから早ければ月内に内定を出す企業が多いため、採用に遅れを取らないよう、ほかの企業と同等のスピードで進められると良いでしょう。
工数が足りずスピード感を上げたくても上げられない企業は、ノンコア業務を採用代行で依頼し、スピード感を高めるのも有効です。下記の資料ではエンジニア採用代行について、依頼できる内容や料金、事例などを詳しく解説しています。採用代行を検討する際はぜひ参考にしてください。
2-4.採用担当だけで採用を進めない
採用を進める場合は、採用担当だけで進めずに自社エンジニアを巻き込むことをおすすめします。現場エンジニアの協力を得ずに採用を進めようとすると会社に必要なエンジニアの理想像が見つからず、かえって採用の難易度を上げてしまいます。
現場のエンジニアにヒアリングすることで求めるスキルや性格などが明確にでき、ミスマッチが起こりづらいメリットがあります。また面接に同席してもらえば、採用担当に知識がない場合でも専門的な分野について代わりに質問してもらうことができます。
しかし、現場は採用の市場を把握できていない場合が多いため、エンジニアの要望をそのまま採用条件に反映すると、理想が高くなりすぎて採用が進まなくなる可能性があります。現場の声を聞きつつ自社の既存エンジニアと合う雰囲気の人はどんな人か、スキルがやや足りない場合でも自社に教育できるエンジニアはいるかをすり合わせることが大切です。
また、採用条件の設定はMUSTとWANTの見極めが重要です。エンジニア経験者の採用においては必須条件のMUSTと、あればなお良いスキルのWANTを分けて考える必要があります。理想が高くならないよう、本当に必要なスキルなのか、WANTの条件が優先されていないかをよく確認して、現実的な採用基準を決めるようにしましょう。
2-5.採用担当のスキルアップを怠らない
エンジニアの採用には、採用担当のスキルアップが欠かせません。IT業界や開発業務はどんなものかを知らないと、採用時にエンジニアがどの分野で活躍できそうかイメージができません。
エンジニアとも今後のキャリアプランについて話ができず、採用がうまくいかなくなる可能性もあるでしょう。また、基礎知識すらない状態だと特にエンジニア経験者から不信感を抱かれやすいです。転職を希望するエンジニアは今後のキャリアも考える必要があるため、当然慎重に企業選びをします。
採用担当者が面接時にエンジニアからの質問に答えられない場合、エンジニアの企業に対する評価も下がるため結果的に採用率の低下に繋がってしまいます。採用担当者であれば最低限、開発に用いられる主要言語やエンジニアがどのようにキャリアアップしていくのかは基礎知識として備えておきましょう。
3.エンジニア経験者との面接で聞くべき質問8選
企業とエンジニア経験者のミスマッチを防ぐためには、面接時にどのような質問をするのかが重要です。本章では、面接時に聞いておいたほうが良い8つの質問を紹介します。
面接の主な目的は、企業とエンジニア経験者のマッチングやスキルの見極めです。エンジニア候補が必要なスキルをもっているかどうかを見極めると同時に、自社にエンジニアが求める環境が備わっているかも見極めなければなりません。面接時にすべき質問の内容を事前に理解し、面接を進める際の参考にしてください。
3-1.質問その1:転職した理由
転職理由は面接でも定番の質問ですが、エンジニア候補の仕事に対する考え方や企業とのミスマッチを避けるために有効です。転職をしようと思ったきっかけを聞くと、キャリアアップを目的とした前向きな理由と、仕事への不満がきっかけとなった後ろ向きな理由に分かれるでしょう。
前向きな理由であれば、エンジニアの描く未来に自社がどう貢献できるかがアピールポイントです。自社の不足ポジションや開発内容など、エンジニアが働くイメージを湧かせる材料を与えられると良いでしょう。
仕事への不満がきっかけで転職を目指したエンジニアは、どんなことに不満を感じたのかを重点的に聞くべきです。自社でも似たような問題を抱えている場合はミスマッチが起こり、採用後の早期離職に繋がってしまいます。それぞれの候補者に合わせ、的確なアプローチをおこなってミスマッチを減らすためにも、転職理由の深堀りは欠かさず実施しましょう。
3-2.質問その2:チームでの業務経験
最近はフリーランスとして個人で案件をこなすエンジニアも増えているため、全てのエンジニアがチーム単位で進める業務に慣れているとは限りません。企業に所属すればチームプレイが基本となるので、面接では過去にチームで仕事をした経験があるかどうかは必ずチェックしましょう。
チーム単位で働くことに慣れていないと進捗共有がおざなりになったり、行き詰まったときの相談先がわからずに業務をストップさせてしまうリスクがあります。またチームで動くことにはメンバー同士の協力が必要なので、助け合いの精神がないとチーム全体に影響します。新しく採用したエンジニアがチームの輪を乱す存在になると、既存のエンジニアにも影響が及び、最悪の場合は退職を検討する原因にもなるので注意しましょう。
いくらエンジニアとしてのスキルが高くても、チームでの業務経験がなく、面接時にもチームプレイに関して否定的な意見を持つ場合は注意が必要です。
3-3.質問その3:どんなときにやりがいを感じるか
エンジニアがやりがいを感じるポイントを聞くことは、仕事に対する価値観や、自社の社風に合っているかを見極める上で重要です。チームで1つのことを成し遂げることがやりがいであれば、チームプレイが好きなエンジニアであることが容易に判断できます。自社エンジニア同士の風通しが良く、コミュニケーションを重要視する企業にとってはぴったりの人材でしょう。
成長を実感できたときにやりがいを感じる場合は、自身でもスキルアップのために行動できるエンジニアである可能性が高いです。自主性を求める会社に合う人材であり、また成長意欲の高いチームに所属しても問題なく業務をこなしてくれるでしょう。このように、仕事に対するやりがいのヒアリング内容は、自社にマッチする人材かどうか即座に判断できる材料になるため、必ず質問しましょう。
また、やりがいの質問に答えられるエンジニアは、しっかりと自己分析ができているといえます。自己分析ができていると、感情に左右されることなく的確な判断ができるので、企業にとっても貴重な人材になるでしょう。
3-4.質問その4:使用経験のあるツールと言語
使用できるツールや言語がわかれば、何の開発が得意なのかが判断できます。エンジニアの得意分野がわかると、自社でどのように活躍できるかイメージする際に役立つのでおすすめの質問です。
万が一自社に足りているスキルであっても、そのほかの得意な分野や興味のある開発をヒアリングするきっかけになります。自社に不足しているスキルを持ったエンジニアであれば、職場環境とのマッチング次第で即座に内定を出すこともできます。特にライバルが多いエンジニア経験者の採用においては内定までの時間が短いほうが獲得できる確率も上がるので、使用経験のあるツール・言語の質問は必須といえます。
ただし、上記のような判断を面接時にするためには採用担当にも最低限の知識が求められますので、面接に備えて日頃から勉強しておくようにしましょう。
3-5.質問その5:失敗の経験と対応方法
過去に業務で経験した失敗と対応方法について質問することで、トラブルが起きた時の対応力や問題解決能力を図ることができます。仕事においてトラブルはつきものなので、失敗をしてしまった時にどう対応するかは自社での働き方に合うかを確認する上で大切です。自主性を求める企業であれば可能な限り自身で対応する性格が望ましく、逆にコミュニケーションを重んじる企業であれば即座に質問してくれるようなエンジニアが望ましいでしょう。
また、将来マネジメントを任せたい場合、失敗したものの最後までやり遂げた経験を持っているかどうかは重要です。失敗と対策を知っているエンジニアは、チームメンバーのミスに対して適切に対応できる能力があるため、マネジメント層が不足している場合は採用を前向きに検討すると良いでしょう。
3-6.質問その6:最も権限を与えられた経験
業務上どこまでの権限を持ったかは、リーダーシップや意思決定力を図る上で必要な質問です。過去にどこまでの権限を与えられたかがわかれば、入社後にどこまでの仕事を任せられるか判断する材料が増えます。チームメンバーとしても、確かな実績を持ったエンジニア経験者がリーダーになれば信頼しやすいため、納得の人選となるでしょう。
注意しなければならないのは、エンジニアとしての業務のスキルが高いからといって、必ずしもマネジメントに優れているわけではないということです。専門スキルが十分あることだけを理由に、チームを率いる経験の有無を確認せずにリーダーに抜擢すると、チームが機能しなくなるリスクがあります。専門スキルの有無だけで安易に判断せず、権限を持った経験があるかどうかをしっかり確認しましょう。
3-7.質問その7:将来のキャリアプラン
エンジニアの望むキャリアパスを用意できないと、せっかく採用できても早期離職するリスクが高まってしまいます。キャリアパスとは、自身のキャリアを積み重ねていくために必要な過程や道筋のことで、入社後にどのような職務にどのような立場で就くかを指します。
エンジニアが将来的に考えている職務やポジションが自社にはすでに足りている場合、希望のキャリアパスは用意できない可能性もあります。万が一キャリアプランを深堀りせずに採用してしまうと、希望の将来が描けないとわかったエンジニアは転職を決めてしまうでしょう。
ミスマッチを防ぐためにも、面接の段階でキャリアプランは必ずヒアリングするよう心がけ、社内でキャリアパスを用意できるかを判断してから内定の決断をしましょう。
3-8.質問その8:会社に求める環境
面接時には、エンジニアが希望する開発環境は必ず聞いておきましょう。自社の環境が整っていないとエンジニアのパフォーマンスが低下し、早々に離職してしまう可能性を高めます。
現場のエンジニアにも開発環境について事前にヒアリングをおこなって改善点を洗い出し、対策を練っておくことも有効でしょう。開発環境が良くなれば、エンジニア採用時のアピールポイントとして使うことができ、また既存エンジニアの満足度向上にも繋がります。新規のエンジニア採用後もミスマッチが起こりにくくなり、エンジニアが離れず長く定着する企業になれるでしょう。
採用前は自社の環境を見直す良い機会でもあるので、今一度振り返りをおこない、エンジニアが希望する環境が提供できているのか、改善できる点はないのかを見つけ、より良い環境づくりに努めましょう。
4.採用担当に必要な知識
希望のエンジニアを採用したいのであれば、採用担当にも必要最低限の知識が求められます。採用前にエンジニアと最もコミュニケーションを取るのが採用担当であり、企業の印象は採用担当で決まるといっても過言ではないでしょう。
本章ではエンジニア採用担当者が身につけておくべき知識について解説します。採用前にチェックして、不足している知識がある場合は補いましょう。
4-1.必要な知識その1:エンジニアの種類
エンジニアは主に開発系とインフラ系の2種類に分かれています。開発系のエンジニアは、プログラマーやシステムエンジニアなどが該当します。業務範囲としては、さまざまな業務の効率化や自動化を可能にするシステムの設計・開発や、アプリケーションの設計・開発を担っています。
インフラ系のエンジニアは、システムを動かすための基盤を整備するエンジニアです。企業が安定したネットワーク環境を利用できているのは、インフラ系のエンジニアが機能しているからです。業務範囲としては主にネットワークインフラの設計や構築、運用保守を担っています。
システムの開発を得意とするのが開発系、ネット環境の整備を得意とするのがインフラ系と覚えておくと良いでしょう。
4-2.必要な知識その2:エンジニアのキャリアパス
エンジニアがどのようにキャリアアップしていくかを理解していないと、面接でエンジニアからの質問に答えられない可能性があるので注意しましょう。エンジニアが将来希望するキャリアは主に、ゼネラリストかスペシャリストの2つに分かれます。
ゼネラリストは多くの分野で経験を積み幅広く活躍したいエンジニアを指し、スペシャリストはある分野のみ特化したエンジニアを指しています。また、ゼネラリストはチームのまとめ役に向く傾向にあり、将来的にはマネジメント層への起用も期待できるでしょう。
スペシャリストの場合は狭い範囲で技術を追求するため、マネジメントよりも現場で活躍し続ける方が向いています。エンジニアが希望するキャリアによって働き方が変わるため、採用担当の理解が進んでいないと、自社でキャリアプランが叶うかどうかの判断ができません。有意義な面接にするためにも、キャリアについては事前に必ず理解しておきましょう。
4-3.必要な知識その3:開発に用いる主要言語
エンジニアは、開発の際に「言語」と呼ばれるコンピューター専用の言葉を用いて開発をおこないます。
- C/C++(シー/シープラスプラス)
- Python(パイソン)
- JavaScript(ジャバスクリプト)
各言語における特徴は以下のとおりです。
C/C++(シー/シープラスプラス) | 【C言語】 自動車の電装パーツや家電メーカーの製品開発に使われる言語。 機械にプログラムを組み込んで動かす仕事全般に利用できる。 【C++】 C言語よりもさらに効率の良いプログラミングを可能にした言語。 業務アプリケーションの開発に特化しており、金融システムの開発や国が運営する公共機関のシステム開発に用いられている。 |
Python(パイソン) | アプリ開発やAI開発などに特化した言語。 大手企業でも使用例が多く、Google内での検索アルゴリズムや、Instagramの開発に用いられた言語でもある。 初心者でも学習しやすく、入門の言語としては最適。 |
JavaScript(ジャバスクリプト) | Webサイトなどの開発に用いられる言語。 Webブラウザ上での表現に特化した言語でもあり、Webページに動きを付けられる。 Python(パイソン)と同様に汎用性の高い言語で、初心者でも扱いやすい言語。 |
表のように言語別で特化している開発があるため、主要な言語を覚えておくだけでエンジニアがどの開発に強いのかが理解できます。
4-4.採用動向の把握
エンジニア採用時には、業界全体の採用動向を把握することが重要です。求人数や各社の採用状況、年収など、採用の戦略を立てるためにもエンジニア転職市場の動向をチェックしましょう。
採用動向が把握できないと戦略が立てられないまま採用活動をおこなうことになるため、希望の人材を獲得することは難しくなります。各社でどのような採用方法を用いているのか、またエンジニアは企業に何を求めているのかなどの動向を調べることは採用のヒントになる情報を収集することに繋がります。希望のエンジニアを1人でも多く採用できるよう、採用活動を始める前に業界の動向は把握しておきましょう。
5.エンジニア経験者採用のトレンド
希望のエンジニアを採用するためには、エンジニア採用におけるトレンドもしっかりチェックしておきましょう。トレンドを把握すれば、採用の戦略を立てる際に役立ち、また採用に行き詰まったときに現状を打破するヒントにもなりえます。本章では、エンジニア経験者の採用における最新のトレンドについて解説します。
5-1.採用媒体の複数利用
エンジニア採用においては人材不足も大きな問題となっています。東京ハローワークのデータによれば、IT関連職の有効求人倍率は令和6年1月時点で2.91倍です。
有効求人の数値が1よりも大きくなればなるほど、求人に対して応募が不足した状態を指すため、2.91倍という数字は人材不足が非常に深刻であることは言うまでもありません。エンジニアの母数が少ない中では応募の獲得自体が難しいため、複数の媒体を利用することでエンジニアの認知度を高め、興味を持ってもらうことが有効です。
それぞれの媒体で特長があるため自社に合った媒体を選ぶことが大切ですが、選定基準がわからず進まない場合もあるでしょう。「みんなの採用部」では最適な媒体の選定も可能なので、媒体選定に迷った際はぜひご相談ください。
5-2.ミドル層への注目
最近ではエンジニア中途採用の傾向として、30〜50代のミドル層への注目が高まっています。統計局の労働力調査年報「年齢階級、職業別就業者数」によると、エンジニアの年齢分布は35〜49歳に集中しています。
この結果から、総数は35〜49歳のエンジニアが最も多いため、採用できる確率が高い年齢層でもあります。ミドル層は経験も豊富で即戦力として採用でき、管理職経験もある場合が多いため、未経験者や若い手を育成もできる強みを持ちます。
若年層のエンジニア経験者は母数が少ない上にライバルも多いため、即戦力として採用できるミドル層の採用も検討しましょう。
5-3.採用代行の活用
エンジニアは専門職のため、採用時の条件選定や候補者の見極めが難しい場合があります。また今までエンジニア採用をしたことがない企業にとってはノウハウがないため、採用は高確率で難航するでしょう。
エンジニアの経験者採用で苦戦する企業が多い中、最近ではエンジニア採用の知見を持つ採用代行会社を活用する企業が増えています。パーソルキャリア株式会社が発表している採用とRPOに関する調査では、全体の4割がRPO(採用代行サービス)を利用したことがあるという結果が出ており、検討したことがある企業も3割に上がることから需要の高さがうかがえます。自社にノウハウがなく採用活動が不安な企業や、採用を始めたものの全く進展していない企業は、採用代行の利用も検討しましょう。
※出典:パーソルキャリアホールディングス株式会社「採用とRPOに関する調査」
下記資料ではエンジニア採用を取り巻く現状や採用代行サービスで得られる効果、依頼できる内容や料金・事例まで詳しく解説しています。エンジニア採用代行・アウトソーシングについて詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
5-4.カジュアル面談の実施
お互いの理解を深める場として、カジュアル面談の実施をおこなう企業が増えています。面接よりもラフな雰囲気でおこなうため緊張も和いだ状態になり、面接では聞けなかったことも自然と話せるメリットがあります。
株式会社学情が企業・団体の人事担当者に対しおこなったカジュアル面談に関する調査では、4社に1社は「カジュアル面談」を実施しており、実施を検討している企業も25.7%に上っているため、主流になりつつある採用過程であることがわかります。選考の過程で内面をもっと知りたい企業は、カジュアル面談の導入をおすすめします。
※出典:学情「カジュアル面談に関する調査」
6.まとめ
エンジニア経験者を採用する際は、注意すべき点をしっかり理解し、自社で対策できるポイントを洗い出しておきましょう。採用活動においては採用担当だけで進めずに、自社エンジニアの協力を得つつ、採用すべきエンジニアの理想像を固めることが大切です。
また採用担当自身も最低限の知識が求められるので、現場のエンジニアの力を借りて事前準備をおこない、採用確率の向上に努めましょう。もしエンジニアの経験者採用に困ったら、エンジニア採用のノウハウが豊富な「みんなの採用部」へぜひ相談ください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を
新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。
- 名前
小泉/アウトソーシング関連
この営業が携わった他の事例・記事を見る