- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 就活
- お悩み
- 元人事が好きなことを仕事にするメリット・デメリットを徹底解説
元人事が好きなことを仕事にするメリット・デメリットを徹底解説
目次
本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます
「どうせ働くなら、好きなことを仕事にしたい」と考える就活生も多いのではないでしょうか。
好きなことをしている時と好きではないことをしている時の体感時間は違いますよね。
正社員の場合、1日あたり少なくとも8時間仕事に時間を費やすことになります。
「好きなことを仕事にできれば、仕事も楽しく充実した毎日を送れるのに」と思いますよね。
本記事では好きなことを仕事にすることのメリット・デメリットや、好きなことを仕事にするのが向いている人・向いていない人、後悔せずに好きなことを仕事にする方法について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
この記事のまとめ
- 好きなことを仕事にすることは可能?
- 好きなことを仕事にするメリット・デメリット
- 好きなことを仕事にするのが向いている人・向いていない人
- 後悔せずに好きなことを仕事にする方法
- 好きなことではなく得意なことを仕事にする

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?
就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。
好きなことを仕事にすることは可能?
「そもそも好きなことを仕事にすることは現実的に可能なのか?」と疑問に思う方も多いと思います。
結論、好きなことを仕事にすることは可能です。
ただし、好きなことを仕事にしたからといって必ず幸せになれるとは言えませんし、好きなことを仕事にすることのメリット・デメリットもそれぞれ存在します。
きちんと理解したうえで、好きなことを仕事にするのか?を検討してみてください。
好きなことを仕事にするメリット・デメリット
好きなことを仕事にすることにはメリットとデメリットがそれぞれ存在します。
メリットだけでなく、デメリットも理解し比較検討しましょう。
好きなことを仕事にするメリット3選
ここでは好きなことを仕事にするメリット3選について紹介します。
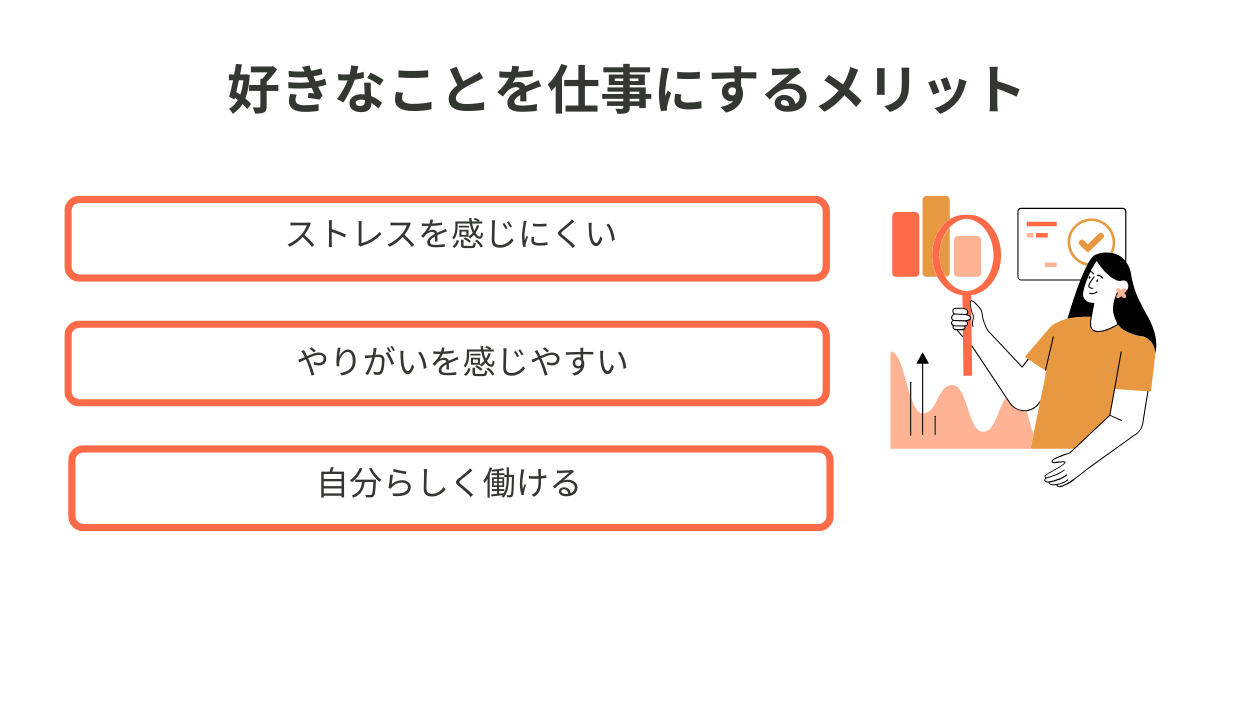
ストレスを感じにくい
好きなことを仕事にすることで、毎日の仕事でストレスを感じにくいというメリットがあります。
退屈な時間と友達と遊ぶ時間では同じ1時間でも前者は長く感じますが、後者はあっという間に過ぎてしまう。そんな体験はありませんでしょうか?
これは体感時間の差が要因だと言われています。
仕事においても、嫌いなことを毎日することは当然ストレスを感じやすいですし、逆に好きなことを仕事にすれば毎日ストレスを感じにくいでしょう。
やりがいを感じやすい
好きなことを仕事にすることで、やりがいを感じやすいというメリットがあります。
好きなことで稼ぐことができたり、好きなことで人から感謝されると、自分自身を評価してもらえたように思い、大きなやりがいを感じられるでしょう。
やりがいを感じられるのでさらに頑張って、より稼げるようになったり、より多くの人に感謝されるようになるなど好循環に入れる可能性があります。
自分らしく働ける
好きなことを仕事にすると仕事と私生活におけるギャップや矛盾を感じることが減ります。
好きなことを通して自分のこだわりを追及したり、自己表現をすることで、本来の自分らしく働くことができます。
好きなことを仕事にするデメリット3選
好きなことを仕事にすることはメリットはあってもデメリットは無いのでは?と思われる方もいるかと思います。しかし実は好きなことを仕事にするデメリットも存在することを見落としがちです。ここでは好きなことを仕事にするデメリット3選について紹介します。
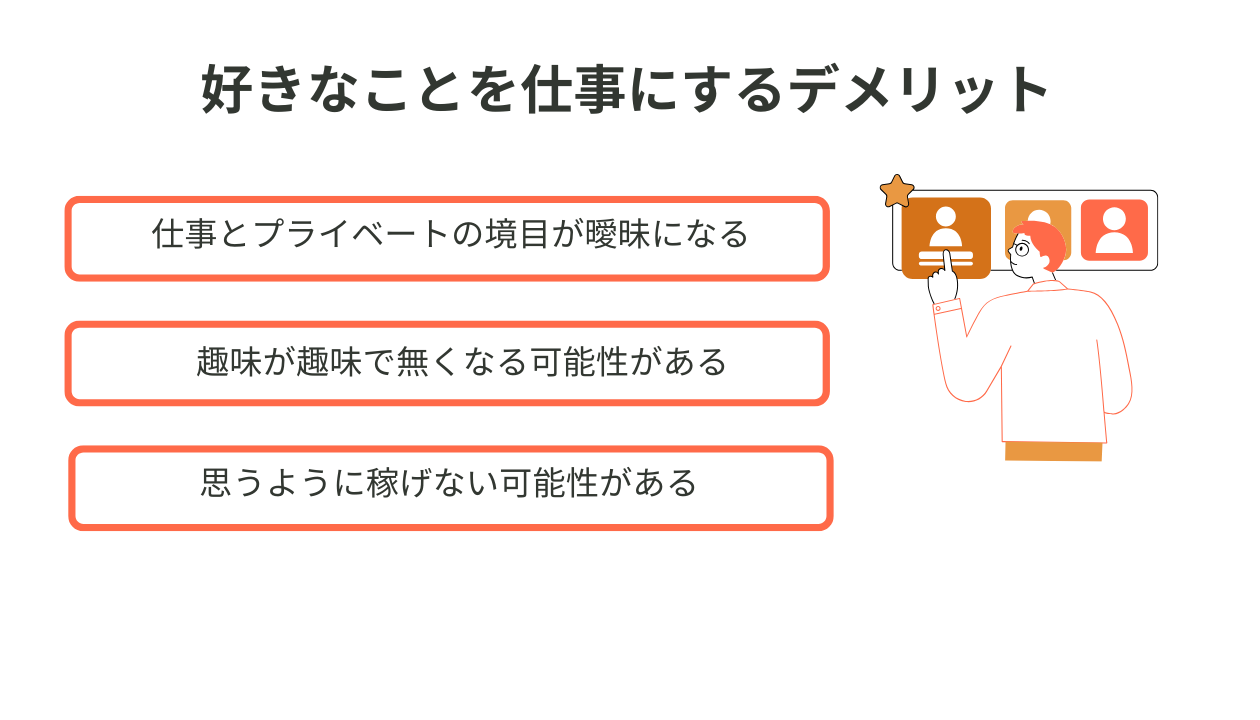
仕事とプライベートの境目が曖昧になる
好きなことを仕事にすると仕事とプライベートの境目が曖昧になるというデメリットがあります。
たとえば趣味がカフェ巡りでカフェを経営したいと考えている人が、休日にカフェに行った際に、「お客さんの回転率はどのぐらいだろう?」「このメニューの利益率はどのぐらいだろう?」など自身のカフェ経営のために無意識に他のカフェを分析したり研究したりしてしまう可能性があります。
好きなことを仕事にしたからこそ、休日にも関わらず気が休まらない、仕事のことをつい考えてしまうといった状態に陥る場合があります。
ただ、好きなことなら四六時中考えていても苦にならないという方は問題無いかもしれません。
趣味が趣味で無くなる可能性がある
好きなことを仕事にすると趣味が趣味で無くなる可能性があるというデメリットがあります。
弊社で実際に働いていたキャリアアドバイザーの中に、前職で旅行代理店に勤めていた社員がいます。
その社員は就職活動をする際に、自分の趣味であった旅行を仕事にしたいと思い、新卒で旅行代理店に入社しました。
しかし働いている中で、お客様の旅行のプラン設計や送り出しばかりで、自分自身は仕事の都合上、長期休暇やまとまった休みが取れず、周囲の友人とも休みが合わず、大好きな旅行に行けなくなってしまったのです。
結果その社員は旅行は趣味のままにしたいと考え、弊社に転職をしました。
このように好きなことを仕事にすると趣味が趣味で無くなる可能性があります。
思うように稼げない可能性がある
好きなことを仕事にすると思うように稼げない可能性があるというデメリットがあります。
稼げるかどうかということは、世の中の需要と供給のバランスによって決まります。
たとえばスポーツであれば競技人口が多いサッカーでコーチをする場合、需要側の競技人口が多い分、供給側のサッカーコーチも多数存在します。そのため熾烈な競争環境にあるといえます。一方でマイナースポーツであれば需要側の競技人口が少なく、供給側のコーチの存在も希少といえます。この場合、需要側も少ないですが供給側も少ないため、ニッチですが必要とする人からは熱烈に求められる可能性もありますし、逆にいくらコーチの存在が希少でも、需要側の競技人口が少なすぎる場合は稼げない可能性が高まります。
このように好きなことを仕事にするうえで、世の中の需要と供給のバランスによっては思うように稼げない可能性があります。
好きなことを仕事にするのが向いている人3選
ここでは好きなことを仕事にするのが向いている人3選について紹介します。参考にしてみてください。
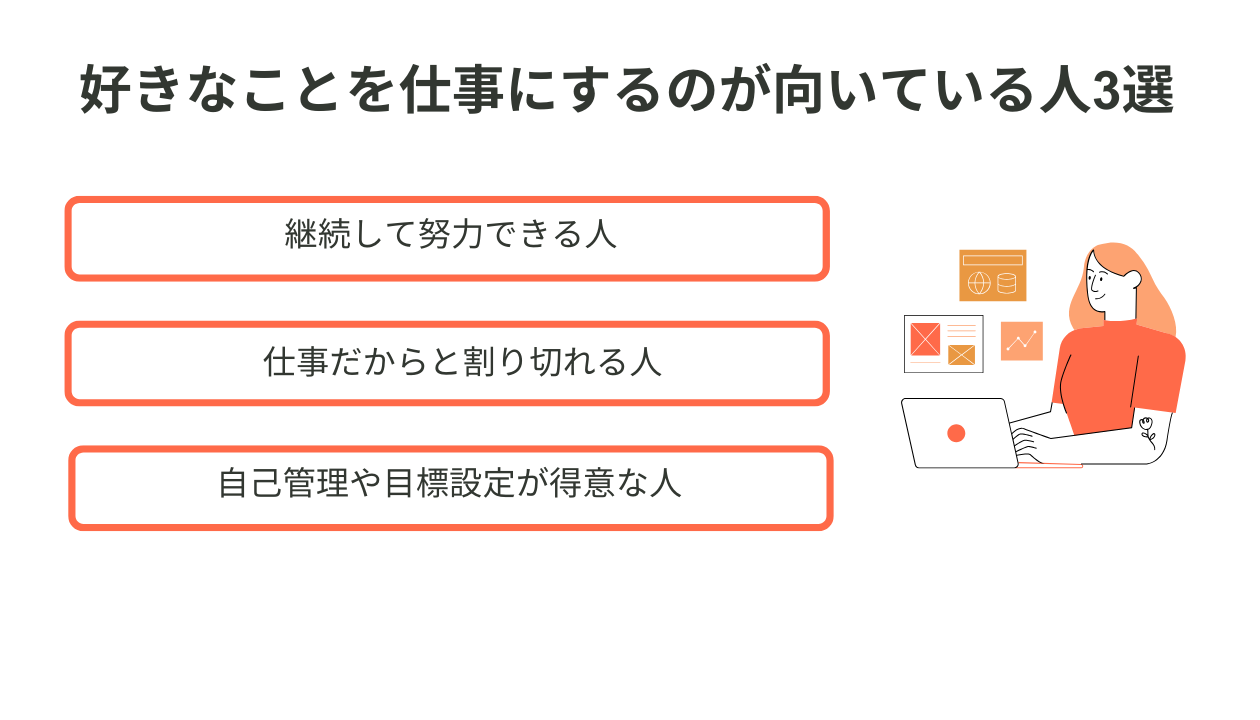
継続して努力できる人
好きなことを仕事にしたからといってすぐに結果が出たり、稼げるとは限りません。
そのため好きなことも一過性で終わるのではなく、今後仕事として生活していけるようになるためにも継続して努力をする必要があります。
仕事だからと割り切れる人
「納期に追われる」「お客様のクレーム対応をしないといけない」など好きなことを仕事にしたからといって全て楽しいことだけではありません。
そのため「好きなことを仕事にしたら楽しく働けると思っていたのに、こんなはずじゃなかった」となりかねません。
仕事である以上こういった大変なことにも向き合う必要があり、その際に「仕事だから仕方ない」と割り切れる人には向いています。
自己管理や目標設定が得意な人
特にフリーランスや起業などの選択肢の場合、会社組織に属するわけではないので、自分自身での高い自己管理能力と目標設定が求められます。
稼働時間に際限が無く根を詰め過ぎてしまったり、逆に上司に報告するなどの工程が発生しないためサボってしまったり、自由度が高い分、高い自己管理能力が無いと事業として継続することが難しくなってしまいます。
また会社や上司から売上目標などを設定されることも無いため、自分自身で計画的に目標設定を行う必要性があります。
h2 好きなことを仕事にするのが向いていない人3選
ここでは好きなことを仕事にするのが向いていない人3選について紹介します。参考にしてみてください。
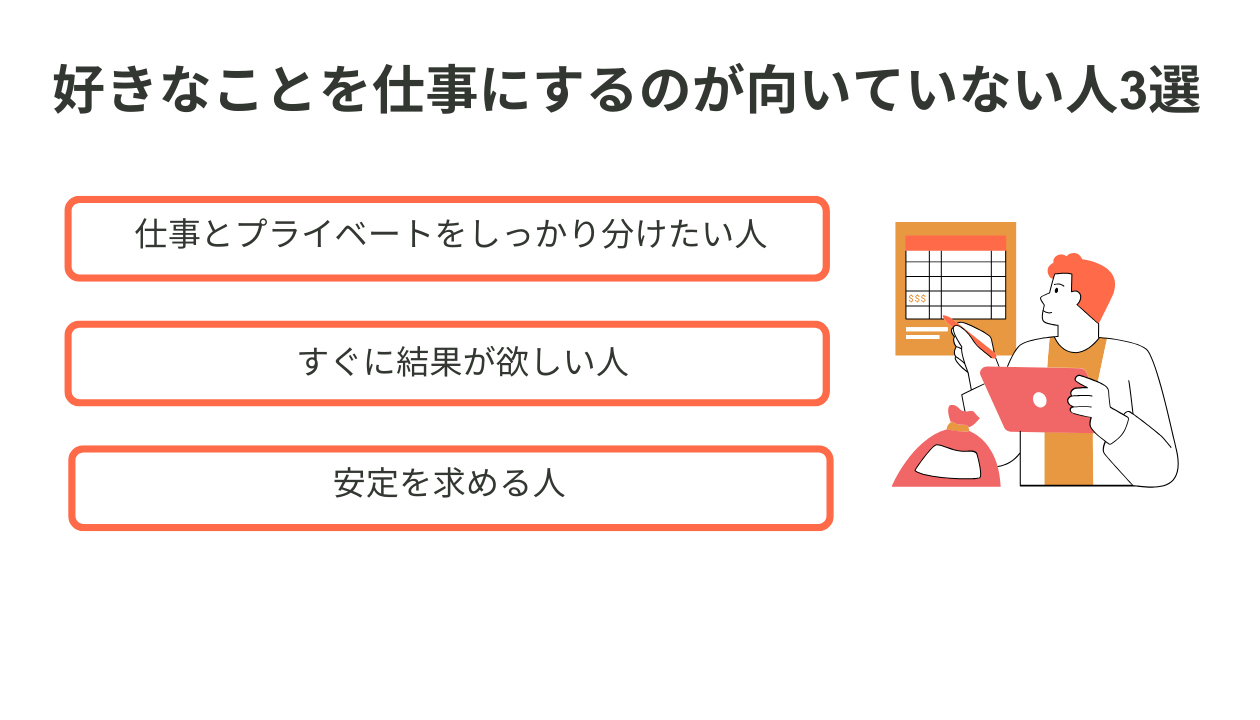
仕事とプライベートをしっかり分けたい人
前述したように、好きなことを仕事にすると、仕事とプライベートの境目が曖昧になったり、趣味が趣味で無くなる可能性があります。そのため仕事とプライベートをしっかり分けたい人には向かない可能性が高いです。好きなことを仕事にすると、人によってはどこまでが仕事でどこまでがプライベートか境目をしっかり分けることが難しくなってしまう可能性があります。
すぐに結果が欲しい人
好きなことを仕事にしたいと考える人は世の中に多く存在します。そのためライバルも多く競争が熾烈なためプロとして求められる基準も高くなる傾向にあります。
好きなことを仕事にしてその道のプロとして結果を出すためには、資格取得のための勉強や、日々の自己研鑽など努力がすぐに報われない時期もあったり、忍耐が必要な場面もあります。
すぐに結果が欲しいという思いが強すぎると「思った通りに成果が出ない=自分に向いていないかもしれない」という思考になってしまう可能性があります。
安定を求める人
好きなことを仕事にするうえで、フリーランスや起業などの選択肢を取る場合、会社員のように会社から毎月決まった給与を振り込まれることも無く、安定した収益を得られる保証が無いです。独立したて、起業したての初期段階では特に十分な資金を持ち合わせていない可能性が高いため、経済的にも精神的にも余裕が無い場合が多いです。
そのため安定を求める方には向いていないといえます。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?
就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。
好きなことを仕事にするうえで覚悟すべきこと
好きなことを仕事にするうえで覚悟すべきことがあります。
「こんなはずじゃなかった」をなくすためにも下記の点を事前に知っておきましょう。
仕事なので好きではないこともやる必要がある
たとえばカフェ経営をする中で、接客やコーヒーを淹れることが好きでも、お店の管理会計などが苦手な人もいます。
しかし、カフェ経営をするうえでお金の管理は避けて通れません。
また、絵を描くのが好きでイラストレーターとしてフリーランスで活動していた場合、絵を描くことは好きだとしても営業活動は苦手な人もいます。しかし、フリーランスで活動する限り、自身をイラストレーターとして起用してくれるクライアントを見つけるために営業活動は避けて通れません。
このように好きなことを仕事にすると、仕事なので好きではないこともやる必要があります。
稼ぐこと・お金に向き合うこと
前述した通り、好きなことを仕事にすると思うように稼げない可能性がある点がデメリットです。
好きなことであるがゆえに、稼ぐことやお金を度外視して好きなことをひたすら追求してしまう傾向がありますが、生活がある以上稼いでいかないといけませんよね。
また、好きなことを仕事や事業として継続していくためにもお金は必要です。
稼ぐことやお金のことを考えることは気が引けてしまう人もいるかもしれませんが、好きなことを仕事にするうえで、稼ぐこと・お金に向き合うことは覚悟すべきです。
自分の好きではなく相手のニーズに応える必要がある
好きなことを仕事にするうえで、自分の好きを追求してしまうと自己満足になってしまい、結果的にお客様に満足してもらえないことがあります。たとえば、デザインが好きでデザイナーとして働いている場合、自分のセンスや好きなデザインを追求するのではなく、クライアントのオーダーに応える必要があります。
仕事は相手のニーズに応えた結果として、お客様からの「ありがとう」が報酬という形としてお金をもらえます。好きなことを仕事をするうえでは、自分の好きではなく相手のニーズに応える必要がある点を覚悟する必要があります。
後悔せずに好きなことを仕事にする方法
後悔せずに好きなことを仕事にするためにも事前に取り組むべきことを紹介します。
自己分析をする
まずはそもそも「あなたが好きなことは何か?」ということを知る必要があります。
これまでの過去の経験から「何をしている時に楽しく感じたか?」「どんな時に喜びを感じたのか?」「無意識に選ぶもの」などを振り返ると、自分自身の好きなことを見つけることができます。
また自己分析の際に名詞だけでなく動詞に注目することをおすすめします。
たとえば、「【ゲーム】が好き」という名詞に着目すると、「プロのゲーマー」「ゲームの企画開発」「ゲーム用品の販売」などのゲームに関連する仕事に思考が派生しますが、「ゲームの攻略法など自分で【戦略や思考を考える】ことが好き」という動詞に着目すると、「コンサルタント」「企画職」「マーケティング職」などゲーム以外の別業界や別職種に思考を派生させることが可能です。
資格取得や勉強をする
自分の好きなことの分野が専門的な領域や勉強や資格が役立つ内容であれば、資格取得や勉強をすることも有効です。
「デザイナー 資格」などのキーワードでGoogleで検索をすると沢山の資格情報が出てきますので、自分の好きな分野と資格をワードセットで検索してみると良いでしょう。
ただし、資格取得や勉強自体が目的ではないので、資格を取得して満足するなどの状況は避け、最低限の資格取得や勉強を進めたうえで、後述するアルバイトや副業などで実務経験を積むことを重要視しましょう。
既にその分野で成功している人に会ってみる
たとえば、「中高生向けのキャリア教育で起業したい」などやりたいことが見えてきた際に、実際に既にその分野で成功している人に会ってみるのも有効です。
Googleで検索してみる、SNSでリサーチしてみる、社会人の先輩に人を紹介してもらう、交流会などに参加してみるなど様々な方法があります。
大学のキャリアセンターに問い合わせてみると過去の先輩達の進路記録があり、繋いでもらうことも可能です。
また少し心理的ハードルは高く感じるかもしれませんが、SNSのDM機能などで経営者などに連絡を取り、アポイントを取ることも可能です。
もちろん失礼の無い文面で連絡をする必要はありますが、経営者や社会人の先輩達も学生や若い世代の貴重な意見を聞ける機会を求めていたりします。勇気を出して連絡してみると意外と快諾してもらえるケースも少なくありません。
既にその分野で成功している人に話を聞くことで、「成功するまでにどのような大変なことがあったのか?」「日々の仕事のやりがい」など良い面も悪い面もリアルな情報を知ることができ自分のキャリアの解像度も上がるためおすすめです。
アルバイトから始めてみる
好きなことが見つかった際に、いきなり起業する、独立する、就職することはリスクが高いです。何故なら「仕事にしてみると想像していたのと違った」「思っていたよりも稼げなくて生活が苦しい」などの事態が起こる可能性があるためです。
アルバイトであれば大学に通いながらもできますし、正社員よりも責任も重くなく、在学中であれば仮に途中で辞めたとしても職歴に悪影響を及ぼすリスクもありません。
そのためまずはアルバイトから始めてみることをおすすめします。
副業で始めてみる
副業の場合はアルバイトと違い、自分で作業時間や進め方などをコントロールできるため自由度が高いというメリットがあります。
一方で全て自分で管理する必要があるため、根を詰め過ぎてしまう、逆にサボってしまうなどの事態が起こる可能性があります。
副業で行う場合は、特に明確な目標設定や作業計画などの自己管理を徹底する必要があります。
就活エージェントに相談してみる
前述した通り、好きなことを仕事にするうえでまずは自己分析をすることが大切ですが、一人で自己分析をしても限界があり行き詰る可能性があります。またアルバイトや副業で経験を積んだとしても「好きなことを本当に仕事にしていいのか?」という不安を完全に解消することはできません。
そこで就活のプロである就活エージェントに相談することをおすすめします。
あなただけでは深堀し切れなかった自己分析を第三者の視点から客観的に言語化してくれたり、実際に社会に出て働いている社会人から「好きなことを仕事にする」ことに対して率直な意見をもらえます。
また、キャリアアドバイザーはキャリアの考え方にも精通しているため、あなたと一緒にあなただけのキャリアプランを作成するサポートをしてくれます。
「好きなことを仕事にする」ことを一人で悩んで決断するよりも就活エージェントに一度相談してみることも検討してみてはいかがでしょうか?
好きなことではなく得意なことを仕事にする
ここまで好きなことを仕事にするということについて述べてきましたが、私自身は好きなことを仕事にすることで幸せに働けると思いますし、一方で好きなことを仕事にしなくても幸せに働ける方法は他にもあると考えています。
前述した通り、好きなことを仕事にすることにはそれなりのデメリットや大変さがあります。それを受け入れる覚悟があれば問題ありませんが、過酷な道のりであることは確かだと思います。
一方で好きなことではなく得意なことを仕事にして幸せに働いている人も沢山見てきました。得意なことを仕事にすると働く本人にとってもストレスは少ないですし、得意なことで価値提供し、お客様からも自然と喜ばれて感謝される。結果として本人も充実した日々を過ごせるという好循環になります。
好きなことではなく得意なことを仕事にするという選択肢も検討することをおすすめします。
「自分の得意なことが分からない」という方は下記の記事を参考に自己分析を進めてみてください。
【就活生必見】自己分析のやり方!5つのステップで自分の強みを見つける方法(フレームワークあり)
おすすめの就活エージェント3選
ここではおすすめの就活エージェント3選についてご紹介します。
就職エージェントneo
参照元:就職エージェントneo
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| オンライン対応 | 可 |
| 主な特徴 | 初回面談60分、2回目以降の面談30分と手厚いサポート面談、東証プライム上場企業・大手グループ求人もあり、累計紹介求人数10,000件、内定支援実績45,000件 |
| 公式サイト | こちらをクリック |
「就職エージェントneo」は業界のパイオニアとして業界内でもトップクラスの歴史を持つ就活エージェントです。東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業の求人を保有、累計紹介求人数10,000件、内定支援実績45,000件を誇ります。
メーカー・商社・不動産・人材・コンサル・ITなど幅広い業界の求人を紹介してもらえます。
このエージェントのおすすめポイント
- 累計紹介求人数10,000件、内定支援実績45,000件を誇る業界のパイオニア的存在
- 東証プライム上場企業や大手グループの求人から中小・ベンチャー企業まで幅広い求人を保有
- 選考フェーズごとの対策や選考後フィードバックなど手厚いサポートが魅力
- いきなり責任者面接を受けられるなど特別推薦枠多数
- 時期によっては最短1日で内定が出るケースあり
キャリアチケット就職エージェント
キャリアチケット就職エージェント
| 対応エリア | - |
|---|---|
| オンライン対応 | 可 |
| 主な特徴 | 内定率が1.4倍向上、厳選された平均5社を紹介 |
| 公式サイト | こちらをクリック |
「キャリアチケット就職エージェント」は「量より質」にこだわって就活支援を行ってくれる就活エージェントです。
何十社もの選考をやみくもに受け続けるような就活ではなく、面談を通してあなただけの就活軸を明確にしたうえで、活躍する人物像にマッチした企業紹介を行います。そのため効率的に就職活動を進めることが可能です。
また1Day選考会などの特別選考フローで短期集中型でスピード内定可能となっております。内定まで最短1週間とスピード感を持って就職活動を進められます。
このエージェントのおすすめポイント
- 厳選された平均5社を紹介
- 独自の企業別選考対策によって内定率が向上
- LINEで気軽に質問可能
- 1Day選考会などの特別選考フローで短期集中型でスピード内定可能
キャリアスタート
キャリアスタート
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| オンライン対応 | 可 |
| 主な特徴 | 就職支援実績4,000名以上(※1) 定着率92%(※2) 内定率86% 最短2週間で内定 有名企業への就職支援実績多数 キャリアアドバイザーの親身さ・面接対策の丁寧さが好評 |
| 公式サイト | こちらをクリック |
※1.2022/3までの実績
※2.2025年8月時点でのホームページ掲載情報
「キャリアスタート」は入社後の定着率92%を誇る就活エージェントです。
有名企業への就職支援実績も多数あり、最短2週間で内定を得られるのも嬉しいポイントです。全国の求人を紹介してもらうことができ、オンライン面談も可能です。
中でもスピーディーに就活を進めたい学生、手厚いサポートを受けたい学生におすすめのサービスとなっています。「大手解禁前に早期で内定が欲しい」「就活の進め方がよくわからない」という学生はぜひ一度利用してみてください。
このエージェントのおすすめポイント
- 入社後定着率92%
- 最短2週間のスピード内定
- 入社実績2,000人以上
- 有名企業への就職支援実績多数
まとめ
前述した通り、好きなことを仕事にすることは大変なことや覚悟しないといけないことも多く、決して楽な道のりではありません。
また周囲からも「好きなことを仕事にするなんてやめておいたほうが良い」「世の中そんなに甘くない」など否定的な意見をもらうことも多いかと思います。
もちろんあなたを心配しているからこそのアドバイスもあると思いますが、私個人としては好きなことを仕事にしたいと思う方は、大変なことも覚悟のうえであれば信じて突き進んで欲しいと思います。
好きなことを仕事にすることは悪いことでもないですし、好きなことを仕事にする以外にも得意なことを仕事にするなどの選択肢もあります。何が正解で何が間違いということは無いのであなた自身の意思で決めることが重要です。
あなたの人生の主役はあなた自身なので、周囲の意見は参考にしつつも、最後はあなた自身が納得のいく後悔のない選択をしてください。本記事がその参考に役立てれば幸いです。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?
就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。
この記事を書いた人

元採用人事・営業リーダー
アキラ
2018年株式会社ネオキャリアに新卒入社。 その後は新卒人材紹介・保育士転職支援の営業として企業の採用支援。約6年間で3,000名程度の就労支援に携わってきました。また、キャリアとしては20代でリーダーとして6名のメンバーの新卒育成担当、新規拠点立ち上げなどを経験してきました。 その後採用人事としての経験を経て、現在はWebマーケティングを担当しております。 就活エージェント・新卒育成担当・採用人事などの視点から就職・新卒・キャリアについて専門的に発信していきます。 読者の皆さんの一番の味方として伴走できるような情報発信をしていきますのでよろしくお願いします。
同じ条件の就職・転職記事
就活のやり方がわからない…始め方やスケジュールなど徹底解説
就活の始め方:①就活サイトに登録する ②自己分析をする ③業界研究をする ④インターンに参加する ⑤OG・OB訪...
最終更新日:2026.01.09




