- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 就活
- 自己PR
- 【グループディスカッション(GD)対策】初めてでも評価されるコツ|役割分担&進め方と流れ&テーマ設定を解説
【グループディスカッション(GD)対策】初めてでも評価されるコツ|役割分担&進め方と流れ&テーマ設定を解説
目次
本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます
この記事のまとめ
- グループディスカッション(GD)の目的と役割について解説
- 人事に評価されるポイントを解説
- 5テーマ毎の過去問題を紹介
就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

グループディスカッション(GD)の目的

企業がグループディスカッション(GD)を通して見極めようとしているのは、学生の「協調性」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「問題解決能力」「リーダーシップ」といった、社会人として必要なスキルです。 単に優れたアイデアを提案するだけでなく、チームとして目標達成を目指せるか、 周囲と協力しながら議論を円滑に進められるか、といった点を評価しています。
グループディスカッション(GD)の主な役割
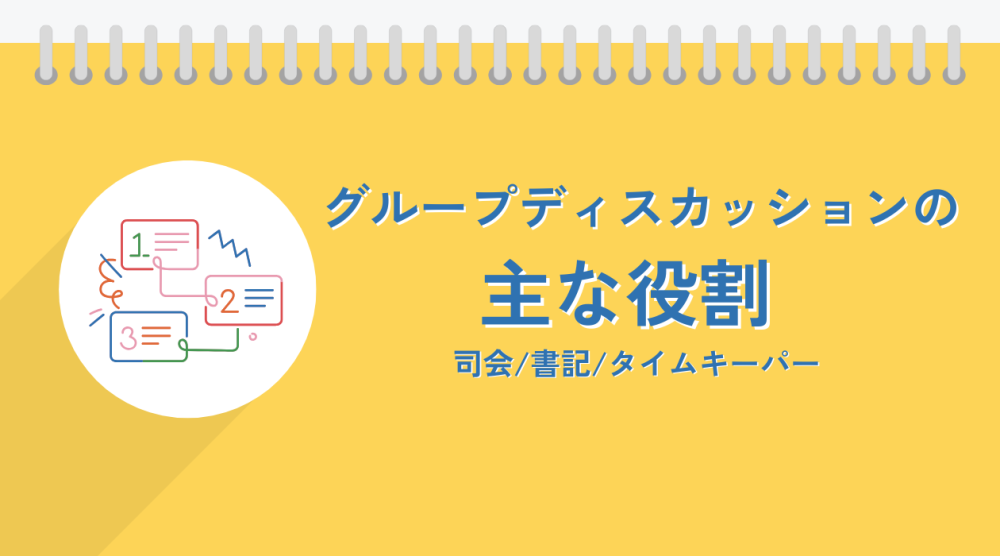
グループディスカッション(GD)では、主に「司会」「書記」「タイムキーパー」といった役割が存在します。 これらの役割は、議論をスムーズに進行させるために必要なものです。 役割を全て一人で担う必要はなく、状況に応じて柔軟に対応できる能力が求められます。
司会
司会は、議論の進行を担当し、メンバーが意見を述べやすい環境を作ります。議論が停滞した場合に新たな視点を提供したり、テーマに沿った発言を促進することが求められます。司会はグループ全体の議論をまとめるために中心的な役割を果たします。
書記
書記は、議論の内容や結論を記録します。議論の要点や重要な発言をまとめ、後で全員に共有できるようにする役割です。記録を取ることで、議論の進捗状況を振り返りやすくなり、結論へ導きやすくなります。
タイムキーパー
タイムキーパーは、時間の管理を担当します。議論の進行状況を把握し、決められた時間内に結論を出すために時間を調整します。タイムキーパーは、議論が長引きすぎないように適切なタイミングで議論を締めくくる役割を果たします。
グループディスカッション(GD)の一般的な流れ

グループディスカッション(GD)では、さまざまなテーマが課され、その内容によって議論の詳細は変わります。 しかし、大まかな議論の進め方には共通の流れがあり、これをしっかりと押さえることで、スムーズかつ質の高い議論を展開できます。 具体的には、以下の6つのステップを踏むことが効果的です。
役割の決定
各メンバーの役割を決定します。 役割分担をにより、議論がスムーズに進行し、誰もが意見を述べやすい環境が整います。
時間配分の決定
グループディスカッションでは、限られた時間の中で最大限の成果を出すことが求められます。そのため、各ステップに適切な時間を配分することが非常に重要です。
アウトライン作成
議論の全体的な流れや方向性を決めるためにアウトラインを作成します。 アウトラインでは、議論のテーマを簡潔に整理し、何を中心に議論を進めるかを明確にします。 脱線を防ぎ、議論が焦点を失わないようにすることができます。
立場・目的の明確化
議論の前提として、各メンバーがそれぞれの立場や目的を明確にすることが重要です。 自分たちが解決すべき課題や目的を共有することで、意見のズレを防ぎ、共通のゴールに向かって議論を進めることができます。
全体像の把握
議論の進行中には、全体像を把握しながら問題を解決するための方向性を見極めます。 全体像を把握することで、部分的な問題にとらわれず、広い視野で解決策を考えることができます。
課題の特定
議論を通じて解決すべき課題を明確にします。 問題が曖昧だと、議論が漠然としたものになり、解決策が見えてこないことがあります。
打ち手の立案
特定した課題に対して解決策や打ち手を立案します。 この段階では、創造的で実行可能な解決策を提案し、それに対するフィードバックを受けながら議論を深めます。 多角的な視点から意見を交わすことで、より良い解決策を導き出すことができます。
就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

効果的なテクニック・コツ

ポイント1:論理的な意見の展開
自分の意見を分かりやすく伝えることが重要です。そのためには、論理的な思考に基づいた意見を展開しましょう。
根拠:なぜその意見に至ったのか、具体的な根拠や事例を交えながら説明しましょう。数字やデータを用いると、説得力が増します。
具体例:抽象的な話だけでなく、具体的な例を挙げることで、相手はイメージしやすくなります。
結論:主張、根拠、具体例を踏まえて、改めて自分の意見を表明しましょう。
ポイント2:積極的な発言とリーダーシップの発揮
グループディスカッション(GD)は、参加者全員で作り上げていくものです。積極的に発言や、話していない人を配慮するなどのリーダーシップを発揮することで、議論を活性化させましょう。
質問:他の参加者の意見に対して、「〇〇について、もう少し詳しく教えてください」など、質問を投げかけることで、議論を深掘りすることができます。
意見の整理:議論が混乱してきた際には、「これまでの意見を整理すると、〇〇と〇〇という意見が出ていますね」と、論点を整理する役割を担うことで、議論をスムーズに進めることができます。
ポイント3:協調性と他者への配慮
様々な意見を持つ人が集まります。相手の意見を尊重し、協調性を持ちながら議論を進めることが大切です。
共感:相手の意見に共感できる部分があれば、「〇〇さんの意見に共感します」と伝え、その上で自分の意見を述べるようにしましょう。
反論する際は:相手の意見を否定するのではなく、「〇〇さんの意見も理解できますが、私は別の視点から〇〇だと考えます」のように、相手の意見を尊重した上で、自分の意見を伝えるように心がけましょう。
ポイント4:適切なマナーと姿勢
グループディスカッション(GD)ではマナーや姿勢も評価対象です。相手に失礼な態度をとらないよう、注意しましょう。
言葉遣い:丁寧な言葉遣いを心がけましょう。尊敬語、謙譲語を正しく使い分け、悪い言葉遣いは避けましょう。
声のトーン:声の大きさは、場に合わせて調節しましょう。大きすぎても小さすぎても、相手に不快な印象を与えてしまいます。
メモを取る:話を聞くだけでなく、重要なポイントをメモしておきましょう。これは、議論を整理するためだけでなく、自分の意見をまとめる際にも役立ちます。
ポイント5:決めゼリフの活用
限られた時間の中で結論を導き出す必要があります。決めゼリフを活用することで、議論をスムーズにまとめることができます。
意見の一致:意見がまとまった場合は、「全員一致で〇〇という結論でよろしいでしょうか」と確認します。
最終結論の表明:グループの意見をまとめ、「私たちのグループでは、〇〇という結論に至りました」と、簡潔かつ明確に発表します。
グループディスカッション(GD)で避けるべき行動

クラッシャー行為
議論を妨害したり、他の参加者の意欲を削いだりする行為を「クラッシャー行為」といいます。クラッシャー行為を行う人は、議論をスムーズに進めることを困難にするだけでなく、グループ全体の成果を低下させる原因にもなります。
否定的な態度:反論ばかりしたり、他の参加者の意見を頭ごなしに否定するのは辞めましょう。
私語:議題に関係のない私語は控えましょう。
スマホの操作:議論中にスマホを触る行為は非常に失礼です。
マイナス評価になる行動
無関心な態度:話を聞いていない、反応がないといった態度は、評価者に悪印象を与えてしまいます。
責任転嫁:自分の意見が通らなかったり、議論がうまくいかなかった場合でも、他の参加者のせいにするのはやめましょう。
自信過剰:根拠のない自信や、自分の意見を押し付けるような態度は、評価者にマイナスの印象を与えてしまいます。
発言量と時間配分のバランス
発言量のバランス:グループディスカッション(GD)は、あくまでもチームで成果を出すことが重要です。一人だけ発言量が多い、少ないといった偏りが内容に影響しないよう、バランスを意識しましょう。
時間配分:与えられた時間内で結論を導き出す必要があり、時間配分は非常に重要です。議論に集中しすぎて、結論をまとめる時間がなくなってしまうことは避けなければなりません。
グループディスカッション(GD)対策と練習方法

事前準備の重要性
グループディスカッション(GD)では、幅広い知識や情報が求められます。そのため、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
時事問題:グループディスカッションでは、社会問題や経済動向など、時事問題に関するテーマが出されることも少なくありません。新聞やニュースなどで、幅広い分野の情報を収集しておきましょう。これにより、議論に積極的に参加し、自分の意見を裏付ける根拠として活用することができます。
自己分析:自分の強みや弱み、経験などを整理しておきましょう。自己分析をしておくことで、自分の意見を効果的に伝えることができます。
効果的な練習方法
友人と練習友人や家族とグループディスカッション(GD)を想定した練習を繰り返し行うことで、実践を想定した対策が可能です。
模擬グループディスカッション(GD):就職支援サイトや企業が開催する模擬グループディスカッション(GD)に参加するのも効果的です。
WEBグループディスカッション(GD)の活用
WEBグループディスカッション(GD)の選考やイベントに参加し、一連の流れや相手に伝わるような話し方など事前に対策しておきましょう。
ツールの活用:チャット機能を活用して、他の参加者と意見交換したり、資料を共有したりするなど、オンラインならではのメリットを活かしましょう。
頻出!抑えておきたいテーマ一覧【5選】

グループディスカッション(GD)のお題のテーマは大きく、5つのパターンに分かれます。 それぞれ進め方が異なるため実際の質問例を参考に対策を進めてみましょう。
グループディスカッション(GD)テーマ例
-
1
課題解決型:与えられた課題に対する解決策を考えるテーマ
-
2
売上アップ型:企業の売り上げを増加させる方法を考えるテーマ
-
3
新規事業立案型:企業が取り組むべき新規事業を提案するテーマ
-
4
抽象テーマ型:抽象的なテーマに対する解決策を考えるテーマ
-
5
意思決定型:与えられた選択肢の中から当事者が取るべき選択を決定するテーマ
過去出題例
課題解決型
「外国人観光客の一人当たり支出額を増加させるにはどうすればいいか」
参考:PwCコンサルティング合同会社
考え方の例
- 現状分析: 外国人観光客の消費動向(宿泊費、飲食、観光体験、ショッピングなど)を把握する。
- 課題特定: なぜ支出額が増えないのか(価格の高さ、魅力的なサービス不足、決済手段の不便さなど)。
- 解決策立案: 訪日観光客の属性ごとにターゲティングし、購買意欲を高める施策(高付加価値サービスの提供、観光体験の充実、インバウンド向けプロモーションなど)を考える。
- 実行可能性: 施策のコスト・実現性・影響度を評価し、優先順位をつける。
売上アップ型
「日本レンタカーの売り上げを推定し、それを1.2倍にせよ」
参考:ローランド・ベルガー
考え方の例
- 現状分析: 日本レンタカー市場の規模や売上構成(法人向け・個人向け、地域ごとの需要、季節変動など)を推定する。
- 売上要素の特定: 売上 = ①顧客数 × ②利用頻度 × ③単価 で分解し、どこに伸ばせる余地があるかを分析。
- 成長戦略: 顧客増加施策(ターゲット拡大、プロモーション)、利用頻度向上策(サブスクプラン、長期レンタル割引)、単価向上施策(オプションサービス充実、高級車レンタル強化)などの具体策を検討。
- 実行可能性: 実施に必要なリソースや市場環境を踏まえ、現実的な施策を選定する。
新規事業立案型一覧
「スポーツビジネスを始める総合商社が最初に取るべき方策は何か」
参考:三井物産
考え方の例
- 市場分析: スポーツビジネスの全体像(プロスポーツ、アマチュアスポーツ、フィットネス、スポーツテックなど)を理解する。
- 事業機会の特定:商社の強み(グローバルネットワーク、投資力、物流・流通)を活かせる分野を選定。
- 事業モデルの構築: 参入戦略(パートナー企業との提携、自社ブランド立ち上げ、投資など)を考える。
- 実行可能性: 実施に必要なリソースや市場環境を踏まえ、現実的な施策を選定する。
自由討論型
「日本人が海外に誇れる強みを3つ上げて発表せよ」
参考:双日(本選考)
考え方の例
- 論理的な根拠:主観ではなく、客観的なデータや事例が必要(例:技術力ならノーベル賞受賞数、ホスピタリティさなら観光業の満足度ランキング)などを選定。
- 国際比較:他国と比較して日本がどの点で優位性を持つのかを整理。
- 多様な視点を持つ: 経済・文化・技術・社会制度など、幅広い観点で強みを抽出。
- 選定のためのディスカッション:強みを3つに絞るため、ディスカッションの余地をを行う。
選択型
「うどんとそば、世界に売り出すならどちらか」
参考:アクセンチュア
考え方の例
- 市場分析:うどんとそば、それぞれの認知度、海外での受容度、競争環境を比較。
- ターゲット選定:どの国・地域に向けて売るか(アジア、欧米など)。
- 戦略立案:商品のブランディング(ヘルシーさ、伝統的な魅力、食べ方の提案)、流通チャネル(現地飲食店との提携、EC販売)などを考える。
- 要点をまとめる:どちらを選ぶべきか、論理的に説明できるようにする。
就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

就活生のための最終チェックリスト

採用担当者が注目するポイント
- 論理的思考力:意見の根拠を明確に、筋道立てて説明できるか
- コミュニケーション能力:相手の意見を理解し、自分の意見を伝えられるか
- 協調性:チームとして目標達成のために、積極的に行動できるか
- 主体性:問題意識を持ち、自ら課題を見つけて解決しようとする姿勢があるか
- 熱意:企業や仕事に対する熱意が伝わってくるか
自分の強みを活かす方法
- 経験談:アルバイトやサークル、ボランティア活動など、自分の経験を交えながら話すことで、説得力が増します。
- 個性:無理にリーダーシップを発揮する必要はありません。持ち味を活かして、チームに貢献できる役割を見つけましょう。
- 協調性:チームとして目標達成のために、積極的に行動できるか
- 自己PR:グループディスカッション(GD)は、自己PRの場でもあります。自分の強みや能力をアピールできるよう、事前に準備しておきましょう。
グループワークでの発表のポイント
- 簡潔明瞭:時間配分を意識し、結論から先に述べ、要点を絞って話しましょう。
- 堂々と話す:声のトーンや話すスピードを意識し、自信を持って発表しましょう。
- 視線:発表時は、参加者全員に視線を向け、特に評価者席を見つめすぎないようにしましょう。
- 質疑応答:落ち着いて、簡潔に答えるようにしましょう。わからない場合は、「申し訳ありませんが、わかりかねます」と正直に伝えましょう。
さいごに
グループディスカッション(GD)では、論理的な思考力、協調性、発言力が評価されます。
実際の選考で出題されたテーマや、選考突破のポイントを知ることで、より実践的な対策が可能になります。
先輩が実際に経験した選考の内容や、回答例が見られる就活サイト「unistyle」を活用してみることをおすすめします。

