- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 転職
- 業界研究
- 【転職】ゲーム業界の面接で聞かれやすい職種別の質問と逆質問を紹介!
【転職】ゲーム業界の面接で聞かれやすい職種別の質問と逆質問を紹介!
目次
一般的にゲーム業界の転職は、「難しい」と言われています。
そのため、転職を成功させるためには、頻出質問を理解して事前に回答案を考えておくなど、面接対策に力を入れることが必要不可欠です。
そこで本記事では、ゲーム業界への転職を考えている人に向けて、ゲーム業界の面接で聞かれやすい頻出質問と回答例、採用担当者の印象に残りやすい逆質問などを紹介します。
ゲーム業界の転職成功率を高めるためにも、本記事を参考にしてください。
この記事でわかること
- ゲーム業界の転職面接ではゲームに対する情熱と活躍度を見られる
- ゲーム業界の転職面接では職種ごとに聞かれやすい質問が異なる
- ゲーム業界の転職面接を受ける際、事前準備として「資格の取得」や「業界に強い転職サービスの活用」などが効果的
仕事の悩みを誰かに相談したい・・・そう感じていませんか?

第二新卒エージェントneoは、第二新卒に特化をした転職支援サービスです。「仕事が辛いけど転職してもいいのかな?」など仕事に関する一人ひとりのお悩みに寄り添います。ゲーム業界への転職についてのお悩みも含め、だれに相談したら良いかわからないと感じている方はぜひキャリアアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。
ゲーム業界の転職面接で見られやすい2つのポイント
ゲーム業界の面接では、必ずしもスキルや経歴だけを見られるわけではありません。
「人柄」や「将来性」といった観点も評価軸となるため、採用担当者がどのようなポイントを面接で見ているのか把握しておくことが重要です。
ゲーム業界の転職面接で見られやすいポイントは、以下の通りです。
ゲームに対する情熱はあるか
ゲーム業界では、ゲームに対する情熱が成果に繋がる場面が多くあります。
たとえば、ゲームプログラマーであれば、長時間のバグ修正や細かい調整が続くケースも多々あります。その際に、「自分が関わるゲームをもっと良くしたい」という情熱が支えになり、挫折せずにゲーム開発に取り組めるなどです。
そのため、採用担当者はなぜゲーム業界を選んだのか」「どんなゲームに影響を受けたのか」といった質問を通じて、応募者のゲームに対する熱意を見極めています。
ゲームへの情熱をアピールできるようにしておくためにも、具体的なエピソードを交えながら話せるようにしておきましょう。
入社後にどのように活躍できるか
ゲーム業界は専門性の高い仕事でありながらも、即戦力として活躍できる人材を求める傾向にあります。そのため、入社後にどのように活躍できるか、というポイントも選考では見られています。
ただスキルや経験面だけでなく、チームでの開発において「役割意識」や「協調性」といった応募者の潜在的な特徴も確認しているため、未経験の場合はそういったヒューマンスキルを伝えることが大切です。
たとえば、デバッガーであれば、細かい不具合を根気よく見つけられ、開発チームに正確に伝えられる協調性などです。
また将来的にどのようなポジションを目指したいのかまで話せるようにしておくと、成長意欲の高さもあわせて伝えられます。「入社後すぐにどう動けるか」と「長期的にどうキャリアを築きたいか」の両面を意識して話せるようにしておきましょう。
職種別!ゲーム業界の面接で聞かれやすい質問と回答例
ゲーム業界の面接でどのような点を見られているのかを把握できたら、実際にゲーム業界の面接で聞かれやすい質問と回答例について見ていきましょう。
ここでは職種別の頻出質問を紹介するので、自分自身が目指している職種の回答例を参考に、自分だけの回答案を考えてみてください。
ゲームプランナー
ゲームプランナーとはゲームの企画から制作、リリース後の分析や改善まで、ゲーム開発を一貫して取りまとめる職種です。
そのため、コミュニケーション能力はもちろんのこと、企画力やマネジメントスキルがアピールポイントとして効果的です。
「ゲームプランナーとはどういった仕事だと感じますか?」
回答例
ゲームプランナーは、プレイヤーが求めている体験を企画として立案し、その企画案が完成するようにチーム全体を動かす役割だと考えています。
前職ではWeb広告の運用を担当し、クライアントの要望を踏まえて改善施策を企画・実行してきました。その際、デザイナーやエンジニアと連携し、成果を出すために仕様や指示を分かりやすく伝える工夫を行いました。
自分自身のアイデアを周囲の人に落とし込み、アイデアを成果に結ぶためにチームをまとめるWeb広告運用のように、ゲームプランナーも企画の立案・マネジメントが重要な仕事だと考えています。
この例文では、前職の経験と照らし合わせながらゲームプランナーとしての仕事について自分なりの考えを伝えています。
未経験の場合は、仕事内容をきちんと理解しているかを判断するために、仕事内容について質問されるケースも多くあります。
志望職種にこれまでの仕事経験と関連する部分がある場合は、例文のように前職の経験を交えながら話せるようにしましょう。
「ゲームプランナーを目指してどのような取り組みをしていますか?」
回答例
ゲームプランナーを未経験から挑戦するにあたり、まずは「企画力」と「仕様の理解力」を養うことに力を入れています。
具体的には、日常でプレイするゲームを開発側の立場で考え、ターゲット層やゲーム進行の意図を分析して企画書形式でまとめています。ほかにもオンライン講座を利用してゲーム開発プラットフォームである「Unity」の基礎を学び、簡単なプロトタイプ制作も経験しました。
企画書を作成するだけでなく、実際にプロトタイプとして形にしてみることで、実現の可能性や工数を意識した企画立案の大切さを実感しました。御社に入社後も、ゲームプランナーとしての知識やスキルを自己で学び続けていく所存です。
ゲームプランナーなど専門的な職種を志望する場合、採用担当者はどのようなスキルを応募者が持っているのかを確認します。
その際、「これまでにどのような取り組みをしてきたのか」などの質問をされるケースがあります。この場合、未経験であれば資格の取得やオンライン講座など、独学で学んだ知識やスキルを具体的に伝えましょう。
個人的にスキルを学習している場合、学ぶ意欲があることを採用担当者にアピールできます。
ゲームプログラマー
ゲームプログラマーは、ゲームプランナーやデザイナーが作成した設計書に基づいてゲームが動くようにプログラムを組む職種です。
「C++」「C#」「Python」といったプログラミング言語や、「Unity」などのゲームエンジン知識が転職の面接で問われる傾向にあります。
「ゲームプログラマーを目指している理由はなんですか?」
回答例
私は、ゲームを「遊ぶ側」から「作る側」に挑戦したいという強い思いから、ゲームプログラマーを目指しています。
前職では業務効率化のために独学でPythonを学び、データ集計ツールを作成しました。
自分の書いたコードでチームの作業時間を短縮できた経験から、プログラミング知識を通じて人々に価値を届けることに大きなやりがいを感じました。
そこで小さな頃から今に至るまで趣味として行っているゲーム制作で、人々にゲームの魅力や楽しさを届けたいと思うようになったのです。
今では「Unity」を使ったミニゲームの制作にも取り組んでいて、楽しさを形にする難しさと面白さを実感しています。
ゲームプログラマーは未経験であっても何かしらのプログラミング経験が必須です。
そのためゲームプログラマーを目指している理由を聞かれた際は、これまでのプログラミング経験を交えながらゲームプログラマーを魅力に感じた理由を説明できるようにしましょう。
「プログラミングする際のこだわりはありますか?」
回答例
私がプログラミングで大切にしていることは、「読みやすさ」と「再利用性」です。
前職で作成した自動化ツールでは、ほかのメンバーが後から修正しやすいようにコメントや処理単位ごとの関数化を徹底しました。
その結果、自作したツールが部署を飛び超えて活用されるようになり、想定以上の効果を生みました。
ゲーム開発においても限られた時間の中で効率良く作業を進めるために、仕様変更や追加要素に柔軟に対応できるコードを書くことが重要だと考えています。
前述した通り、ゲームプログラマーはプログラミング経験がほぼ必須です。
そのため、一歩踏み込んだ質問として「プログラミングする際のこだわり」などを採用担当者から聞かれる可能性もあります。
この場合は、ゲームのプログラミングで重要だと感じることを整理したうえで、自身がプログラミングする際に気を付けていることと照らし合わせながら話せるようにしましょう。
ゲームデザイナー
ゲームデザイナーは、ゲームの設計や開発に携わる職種です。たとえば、ゲームのキャラクターやアイテム、背景などのデザインを担当します。
プレイヤーがゲームのファンになるようなビジュアルを考える役割であるため、ゲーム制作において重要な役割です。
「好きなゲーム作品はありますか?またどのような点に魅力を感じましたか?」
回答例
私が特に影響を受けたのは、「ゼルダの伝説」です。
広大な世界を自由に探索できる一方で、どのエリアにもプレイヤーを惹きつける謎解きや仕掛けが施されていて、発見するたびに驚きと喜びが生まれる点に強く魅了されました。
前職では広告デザインを担当していて、ユーザーが直感的に行動したくなるレイアウトを考えてきました。
そして自分自身がデザインを担当する立場になってからは、「ゼルダの伝説」はプレイヤーが自然に楽しめる「導線」を意識したデザインが施されていることに気付き、ヒット作として納得できました。
ゲームデザイナーは、キャラクターのデザインやアイテムなど、ゲームの世界観を作り上げる役割を担います。
そのため、採用担当者は好きなゲーム作品を聞くことで、どのようなデザインや仕様を魅力的に感じるのか応募者の感性を判断しています。
好きなゲーム作品を回答する際は、回答例文のように具体的な魅力を伝えられるようにしておきましょう。
「どのようなデザイナーになりたいですか?」
回答例
私は、遊んでくれる人の体験を第一に考えられるデザイナーになりたいです。
現在はゲーム開発の基盤となるスキルを磨いている段階ですが、「Photoshop」「Illustrator」を使ったUIデザインの練習を重ね、既存ゲーム画面を模写・改良する課題に取り組んでいます。
デザインを制作する際は見た目の美しさだけでなく、プレイヤーが迷わず楽しめるような導線作りを心掛けています。御社に入社後は、学び続ける姿勢を持ち続け、プレイヤー視点を忘れないデザイナーを目指します。
転職の面接では長期的な活躍を想定し、将来の理想像について質問される場合もあります。
そのため入社時のイメージだけでなく、入社してから5年・10年後の将来像についても考えておくことが大切です。
例文のように目指している将来像を具体的に伝えられると、将来の活躍する姿を採用担当者は想像しやすくなります。
未経験だからこそ聞かれる!ゲーム業界の転職で聞かれる頻出質問
未経験からゲーム業界を志望している場合は、未経験だからこそ聞かれやすい頻出質問も押さえておきましょう。
ここでは未経験だからこそ聞かれやすい頻出質問を2つ紹介するので、回答例文を参考にしてください。
「ゲーム業界を志望している理由を教えてください」
回答例
私は「人に感動や楽しさを届ける仕事がしたい」という思いから、ゲーム業界を志望しています。
前職ではコンサルタントとしてクライアントの課題を分析し、提案を形にして成果に繋げてきました。私はこの仕事を通じて、自身の企画や工夫で人から感謝されることにやりがいを感じました。
そして私にとってゲームは子どもの頃から一番夢中になれる体験であり、自分の力で誰かに喜びを与えられる環境として理想的だと考えています。
未経験ではありますが、前職で培った企画力や調整力を活かし、自己学習を深めながら御社に貢献していきたいです。
未経験であれば多くの場合で、ゲーム業界を志望する理由を問われます。その際は、前職の経験などと紐づけながら、ゲーム業界を志望するようになった経緯を伝えましょう。
例文ではコンサルタントとしての仕事と、夢中になれる体験であることからゲーム業界を志望していることを伝えています。前職の経験を交えながら話すことで、前職の経験をゲーム業界でも活かせることをアピールできます。
「採用されたらどの職種で働きたいですか?」
回答例
御社に採用された際は、ゲームプランナーとして活躍したいです。というのも、前職で培った企画提案力やチームを動かす調整力を最も活かせる職種だと感じているからです。
もちろん、理想だけではゲームプランナーは務まらないと考えています。
そのため、Unityを使った簡単なプロトタイプ制作や、既存ゲームの企画分析を独学で行い、企画を形にする難しさと面白さも理解しているつもりです。
未経験であることから、最初はアシスタントとしてプランナーを支える役割からスタートになると理解していますが、経験を積み重ねながら自ら企画をリードできる存在を目指したいです。
採用担当者は、応募者に対してどのような職種を志望しているのかを確認します。特に未経験の場合は、応募する職種の想像がつかないため、より具体的に知りたいと考えるはずです。
そのため、志望している職種と志望理由、どのように活躍していきたいのかをセットで具体的に回答できるようにしておきましょう。
仕事の悩みを誰かに相談したい・・・そう感じていませんか?

第二新卒エージェントneoは、第二新卒に特化をした転職支援サービスです。「仕事が辛いけど転職してもいいのかな?」など仕事に関する一人ひとりのお悩みに寄り添います。ゲーム業界への転職についてのお悩みも含め、だれに相談したら良いかわからないと感じている方はぜひキャリアアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。
ゲーム業界の面接に臨む際の事前準備
ゲーム業界の面接は、他業界と比べても「専門性」と「熱意」の両方が求められやすい業界です。
そのため、頻出質問を覚えたり応募書類を整えたりするだけでは、選考対策は不十分だといえます。ここでは面接前に特に意識すべき準備を2つ紹介します。
ゲーム業界の面接に臨む際の事前準備は、以下の通りです。
ゲーム業界に役立つ資格を取得する
未経験であっても、ゲーム業界に通じる資格を取得しておくことで「基礎知識を身に付けている」「業界に挑戦したい熱意がある」と選考で印象に残りやすくなります。
たとえば、次のような資格は面接のアピール材料になりやすいです。
ゲームプランナー:統計検定、基本情報技術者試験
ゲームプログラマー:Unity認定試験、C言語プログラミング能力検定
ゲームデザイナー:Photoshopクリエイター能力認定試験、CGクリエイター検定
資格そのものが直接合否を決めるわけではありませんが、学んだ知識は志望理由や自己PRに結び付けられます。
面接での回答に説得力を持たせるためにも、転職活動前に自分に合った資格を取得しておきましょう。
ゲーム業界に強い転職サービスを活用して面接対策を入念に行う
冒頭でも伝えた通り、ゲーム業界への転職を成功させるためには、充実した面接対策が必要不可欠です。そのため、ゲーム業界に強い転職サービスを活用しましょう。
特にゲーム業界は選考倍率が高いため、「普通の準備」では選考を突破できない可能性も大いにあります。ゲーム業界に強い転職サービスを利用するメリットは、以下の通りです。
未経験でも選考に通過しやすい企業を紹介してもらえる
面接でよく聞かれる質問や回答のコツを指導してもらえる
過去の質問事例を基に具体的なフィードバックを受けられる
ゲーム業界では「好きなゲームとその理由」など独特な質問も出やすいです。こうした想定質問も事前に対策できるよう、転職のプロに面接対策を依頼しましょう。
ゲーム業界の面接対策に期待が持てる転職サービスは、こちらで詳しく紹介しています。
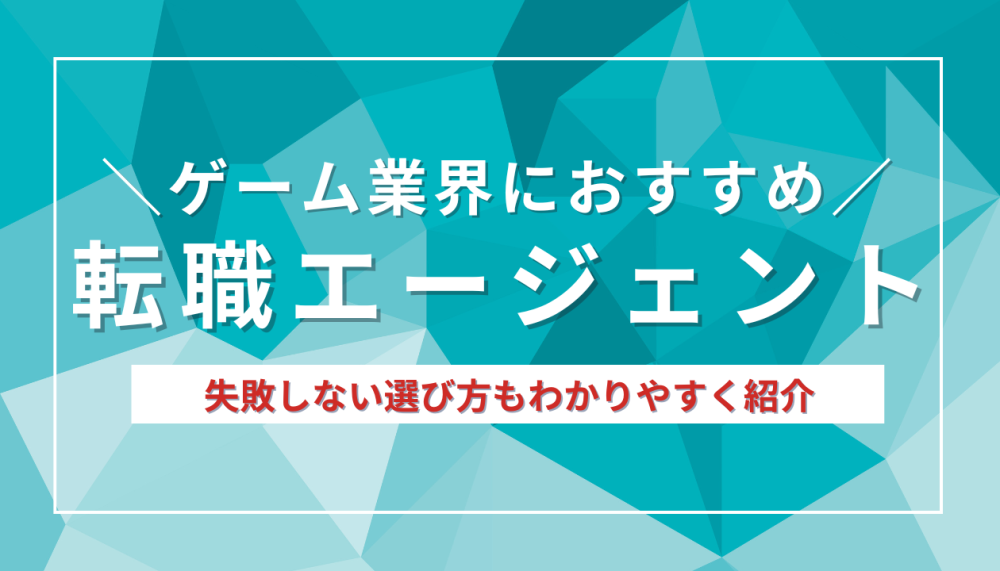
【最新版】ゲーム業界に強いおすすめ転職エージェント12選
ゲーム業界の面接で聞いておくべき逆質問2選
面接の最後に、「何か質問はありますか?」と聞かれる場面は多々あります。
そしてゲーム業界は多彩なキャリアやチーム文化が特徴的であるため、これらの特徴を踏まえた逆質問ができるように準備しておきましょう。
ここではゲーム業界の面接で聞いておくべき逆質問を2つ紹介します。
「入社後はどのようなキャリアが用意されていますか?」
入社後のキャリアについて質問することで、長期的に活躍する意思があることを面接官に示せます。
また入社してから数年後にディレクターやプロデューサーを目指せるのか、あるいは特定ジャンルの企画に特化できるのかなど、道筋は会社によって異なります。
そのため採用担当者に入社後の意欲を伝えつつ、入社後の将来的なイメージを想像しやすくするためにも、キャリアパスの確認は逆質問として効果的です。
「チーム内のフィードバック文化について教えてください」
未経験の場合、フィードバックの仕組みや文化について逆質問で確認しておくことで、成長意欲があることを採用担当者に伝えられます。
またフィードバックの環境を確認することで、業務を通じて成長できる環境であるかも判断できるでしょう。
たとえば、定期的な個別ミーティングで改善点を話し合う企業がある一方で、開発のスピードを優先してフィードバックを最小限に押さえている企業もあります。
逆質問でフィードバック文化について確認し、面接官に対して「自身の成長や改善を意識できる人材」であることをアピールしましょう。
仕事の悩みを誰かに相談したい・・・そう感じていませんか?

第二新卒エージェントneoは、第二新卒に特化をした転職支援サービスです。「仕事が辛いけど転職してもいいのかな?」など仕事に関する一人ひとりのお悩みに寄り添います。ゲーム業界への転職についてのお悩みも含め、だれに相談したら良いかわからないと感じている方はぜひキャリアアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ゲーム業界の転職を成功させるためには、ゲーム業界ならではの頻出質問への対策など、充実した面接対策が必要です。
そのため、これからゲーム業界への転職を考えているのであれば、本記事を参考にどのような質問に答えられるようにしておくべきかを理解しておきましょう。
またゲーム業界の転職は難易度が高いため一人で転職活動を進めるのではなく、転職サービスを活用することも大切です。
ゲーム業界に強い転職サービスは以下の記事で詳しく紹介しているため、自分に合った転職サービスはこちらで確認してください。
関連記事
【最新版】ゲーム業界に強いおすすめ転職エージェント12選
この記事を書いた人

就・転職専門ライター
さりぃ
大学時代は法学を専攻、卒業後は人材紹介企業にて約5年間就・転職専門ライターとして累計1,000本以上の記事を執筆。並行して、第二新卒層をターゲットとした就・転職支援事業のサービスサイトの管理責任者としてWebマーケティングも担当しておりました。
いわゆる「フリーター」というポジションから正社員としての働き方に切り替え、サービスサイトの責任者を任せていただけるまでになった経験を活かし、
就・転職のノウハウだけでなく、「人生の選択肢の多様性」「自身の選択への向き合い方」について発信することで少しでもお役に立てれば幸いです。

