- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 転職
- 退職関連
- 【ケース別】退職金の計算方法かんたん解説|税金の種類も
【ケース別】退職金の計算方法かんたん解説|税金の種類も
本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます
「退職金をいくら受け取れるか知りたいけど計算方法がわからない」とお悩みではありませんか?退職金をいくら受け取れるかによって、今後の何にどれくらいお金をかけるべきかが変わってくるかと思います。
本記事ではケース別に退職金の計算方法をご紹介いたします。退職金の種類やかかる税金についてもわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
この記事のまとめ
- 退職金とは労働者が企業を退職する際に受け取れるお金を指し、退職手当や退職慰労金とも呼ばれる
- 退職金制度は主に4種類ある
- 退職金として受け取れる額は企業ごとのルールや勤続年数、役職などの様々な要素によって決まる
- 退職金にかかる税金は大きく「所得税」「住民税」の2種類
→ 横にスクロールできます
【働きやすい仕事を教えてもらうなら】
おすすめ転職エージェント3選
| サービス名 | 公式サイト | おすすめポイント | |
|---|---|---|---|
|
編集部イチオシ 第二新卒エージェントneo |
 |
公式サイト | 未経験者に強い20代特化型! 親身な対応が好評で相談のみでもOK |
| マイナビジョブ20's |  |
公式サイト | 全求人が20代向け!約8割が未経験OK求人 |
| doda |  |
公式サイト | 28万件以上(※2025年12月時点)の求人から探せる |
※右にスクロールするとそれぞれの特徴が掲載されています
そもそも退職金とは?
退職金とは労働者が企業を退職する際に受け取ることができるお金のことで、退職手当や退職慰労金とも呼ばれています。
制度の正式名称は「退職給付制度」ですが、一般的には退職金制度と呼ばれており、この制度を取り入れている会社でのみ退職金を受け取ることができます。
退職金は定年退職の時だけでなく、会社都合で解雇された時や自己都合で退職する場合にも受け取れるもので、労働者が亡くなった場合にも適用されます。
退職金の受け取り方は「一時金タイプ」「年金タイプ」に大別されます。
退職金の種類
退職金制度で得られるお金は主に「退職一時金」「退職金共済」「確定給付年金」「確定拠出年金」の4種類がありますので、下記でそれぞれチェックしておきましょう。
退職一時金
退職一時金の受け取り方は「一時金タイプ」に分類され、勤続年数や退職理由、基本給や役職などによって企業ごとに計算方法が決められています。
企業の経営状態にかかわらず、規定が変更されない限り受け取ることができます。
退職金共済
退職金共済は企業が加入している共済を通じて退職金を受け取れるという制度で、受け取り方法は「一時金タイプ」に分類されます。
条件を満たせば一括払い、分割払い、一部分割、その併用も選択することが可能です。計算方法は下記になります。
掛け金 × 納付月数 +α
※「+α」には付加退職金、利回りなどが含まれます
※掛け金の額は企業が決定します
退職金共済で受け取れる金額は、掛け金の額や勤続年数(納付月数)によって異なります。
企業の経営状況に関係なく積み立てた分の額を受け取れるメリットがありますが、共済を介している分、制度によっては積み立てられる金額が比較的少ない場合もあるため留意しましょう。
確定給付年金(DB)
確定給付年金(DB)は労働者が退職金として受け取れる給付額があらかじめ決められている企業年金制度で、企業の経営状態にかかわらず決められた金額を受け取ることができます。
原則として60歳以降に受け取れるもので、企業の規約によっては制限がありますが、一般的には一時金タイプ、年金タイプ、またはそれらの併用の3パターンから受け取り方を選べます。計算方法は下記の通りです。
掛け金 × 納付月数 +α
※「+α」には付加退職金、利回りなどが含まれます
※掛け金の額は企業サイドで決定されます
こちらも、掛け金の額や勤続年数(納付月数)次第で受け取れる金額が異なります。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(DC)は事業主や加入者自ら掛金を拠出し、資産運用を行い、その成果次第で将来受け取れるの年金額が決まるという制度で、掛金額(拠出額)が決められている(=Defined Contribution)ことからDCとも呼ばれます。
これには企業が運用する「企業型確定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2種類が挙げられ、下記の計算方法で金額が求められます。
掛け金 × 納付月数 + 運用結果
※掛け金の額は企業サイドで決定されます
こちらは掛け金の額や勤続年数(納付月数)、運用の仕方によって金額が異なります。
退職金制度がない企業もある
退職金はどの企業でも受け取れると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、退職金制度の導入は法律で定められているものではなく、導入していない企業も一部存在します。
人事院「令和3年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び令和2年の調査結果について」によれば、退職金制度のある企業の割合は下記の通りとなっています。
退職給付制度がある企業:91.9%
(事務・技術関係職種の従業員がいる企業が対象)
└「退職一時金制度」がある企業:91.2%
└「企業年金制度」がある企業45.8%
自分の勤めている会社に退職金制度があるかどうかは就業規則か労働協約次第になりますので、まずはチェックしてみましょう。また、退職金の支給額(支給内容)についても企業によって異なります。
自分が働きやすい職場と出会える!おすすめの転職エージェント3選
退職金の相場はどれくらい?
総務省統計局の「令和5年就労条件総合調査」によれば、退職理由別の退職金は下記のようになっています。

これによれば退職金の相場は月収の約40か月分前後となっています。
早期優遇退職(企業がリストラの一環として退職希望者を募るもの)では退職金が上乗せされるため最も金額が高くなっていますが、一方、自己都合退職では減額措置が取られるためその水準は最も低くなっています。
受け取れる退職金の額は企業の規定、企業規模、退職理由、勤続年数、学歴、業種などによって大きく異なることがわかるでしょう。
20代に寄り添った転職を支援!

第二新卒エージェントneoは、第二新卒をはじめとした20代に特化した転職支援サービスです。一人ひとり異なる状況、強み、適性、思考を加味し、あなたの初めての転職を支援します。未経験からの転職支援実績も多数!あなたの未来に寄り添い、最適な企業をご紹介します。
【ケース別】退職金の計算方法
ここからは先ほどお伝えした4つの退職金制度ごとの計算方法をご紹介します。ぜひご自身に当てはめて計算してみてください。
退職一時金
まずは退職一時金の計算方法についてですが、これにはいくつか計算方法があるため代表的な4種類の計算方法をご紹介したいと思います。
定額制
定額制は、勤続年数によって退職金の額が決まるものになります。たとえば勤続年数が10年なら100万円、20年なら250万円、などとあらかじめ決められた額が支給され、成果や役職は加味されません。
実際に受け取れる金額は就業規則や退職金規程によって異なりますので、ぜひ確認してみてください。
基本給連動型
次に基本給連動型です。これは勤続年数、退職時の基本給を加味して退職金の額が決まるものになります(企業によっては退職理由や役職も考慮されます)。
支給係数は企業ごとに異なりますが、基本的には勤続年数に応じて上がっていくケースが多くなっています。
退職理由も加味する際には会社都合で×1.0、自己都合で×0.8(会社都合の場合よりも2割減る)などと設定している企業が多い傾向があります。
<前提となる支給係数>
勤続年数における支給係数
└勤続3年目:1.8
└勤続10年目:10
└勤続20年目:20
退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、基本給25万円、自己都合退職
└25×1.8(3年目の係数)×0.8(自己都合)=36万円
(2)勤続10年目、基本給30万円、自己都合退職
└30×10(10年目の係数)×0.8(自己都合)=240万円
(3)勤続20年目、基本給40万円、会社都合退職
└40×20(20年目の係数)×1(会社都合)=800万円
別テーブル制
別テーブル制は、勤続年数に応じて基準額が設定されているもので、役職や等級、退職理由をもとに作成された表(テーブル)をもとに計算されます。
<前提となる支給係数>
■役職別基準額
└一般社員:70万円
└課長:100万円
└部長:180万円
■役職別支給係数
└一般社員:0.8
└課長:1.2
└部長:1.6
■退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、一般社員、自己都合退職
└70×0.8(役職別の係数)×0.8(自己都合)=44.8万円
(2)勤続10年目、課長、自己都合退職
└100×1.2(役職別の係数)×0.8(自己都合)=96万円
(3)勤続20年目、部長、会社都合退職
└180×1.6(役職別の係数)×1(会社都合)=288万円
ポイント制
ポイント制は退職時の基本給、勤続年数、退職理由、人事評価などをもとに在職1年あたりのポイントが決められ、最終的な累計ポイント数に応じて金額が決まるものになります。
<前提となるポイント・係数>
■1ポイントあたりの単価
└1万円
■勤続年数・加算ポイント
└勤続一年ごとに+10ポイント
■役職別・加算ポイント
└一般社員:なし
└課長:10ポイント
└部長:20ポイント
■退職理由における支給係数
└会社都合退社:1
└自己都合退社:0.8
<計算例>
(1)勤続3年目、一般社員、自己都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×3年×0.8(自己都合)×1万円(ポイント単価)
=24万円
(2)勤続10年目、課長、自己都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×10年×0.8(自己都合)×1万円(ポイント単価)
=80万円
(3)勤続20年目、部長、会社都合退職
└10(勤続年数による加算ポイント)×20年×1(会社都合)×1万円(ポイント単価)
=200万円
退職金共済
退職金共済は「月額掛け金×納付月数」で決まるものになります。
月額掛け金は中退共(独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部)の場合5,000円~3万円の間に16種類あり、企業が勤続年数などを考慮して掛け金を決定します。
中退共の「基本退職金額表」を基にすると、計算例は下記のようになります。
<計算例>
(1)勤続4年目
└掛け金1万円×48か月+1.0%(利回り)=48万1,700円
(2)勤続10年目
└掛け金1万円×120か月+1.0%(利回り)=126万5,600円
(3)勤続20年目
└掛け金1万円×240か月+1.0%(利回り)=266万6,600円
確定給付年金(DB)
確定給付年金も「掛け金月額×納付月数」で決まるほか、月額掛け金は企業ごとに定められています。
<計算例>
(1)勤続10年目
└掛け金1万円×120か月+利回り
(2)勤続20年目
└掛け金1万円×240か月+利回り
確定拠出年金(DC)
最後に確定拠出年金です。こちらも「掛け金月額×納付月数」で決まります。
運用は事業主あるいは社員個人が行うことになり、運用が成功すればその分受け取れる額が増えますが、もし失敗すれば受け取れる額が減ってしまう点に注意が必要です。
<計算例>
(1)勤続10年目
└掛け金1万円×120か月+利回り
(2)勤続20年目
└掛け金1万円×240か月+利回り
退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」
退職金は退職所得として税金が課せられ、具体的には「所得税」「住民税」の2種類を修めることになります。
退職金の中でも退職一時金については受け取る額が大きくなりやすい分納める税金も高くなりやすいですが、所得税については「退職所得控除」によって税負担が軽くなるよう配慮されています(計算式上、結果的に住民税の負担も軽くなることになります)。
また、他の所得とは別で課税されるため余計に税金を納める必要はありません。控除を受けるには「退職所得申告書(所得税法第203条1項各号の定めによる申請書)」を職場に提出する必要があります。
提出後は職場に手続きを進めてもらえますので、退職一時金を受け取った後に源泉徴収などを申請する必要はありません。
控除額・課税対象額の計算方法
具体的な控除額、課税対象額はの計算方法は下記の通りです。
(1)勤続年数が20年以下の場合
└勤続年数×40万円
(退職所得控除額が80万円未満の場合には、80万円)
(2)勤続年数が20年以上の場合
└(勤続年数-20)×70万円+800万円
※勤続年数は1年未満の端数を切上げて計算
※参考元:人事院「退職手当制度の概要」
また、課税対象額は「(退職金-控除額)×1/2」で求めることができます。
(1)勤続10年、退職金240万円の場合
└240万円-(10年×40万円)=-160万円
→退職金240万円は控除額400万円以内に収まるため、税金はかかりません。
(2)勤続30年、退職金2800万円の場合
└(30年-20)×70万円+800万円=1500万円
→1500万円までは税金がかからず、課税対象となるのは(退職金2800万円-1500万円)×1/2=650万円となります。
ちなみに、今後の転職先がまだ決まっていないという場合には可能な限り早く見つけるのがベターです。というのも、転職市場においては退職後のブランクが長くなればなるほど企業から内定が出にくくなるためです。
「なかなか内定が出ずに困っている」「どんな企業を選べば良いのかわからない」という方は転職エージェントに相談すると安心です。
転職相談だけでなく求人紹介や選考対策などを講じてもらえるほか、サービスによっては企業へ推薦してくれる場合もありますのでぜひ活用してみてください。
20代に寄り添った転職を支援!

第二新卒エージェントneoは、第二新卒をはじめとした20代に特化した転職支援サービスです。一人ひとり異なる状況、強み、適性、思考を加味し、あなたの初めての転職を支援します。未経験からの転職支援実績も多数!あなたの未来に寄り添い、最適な企業をご紹介します。
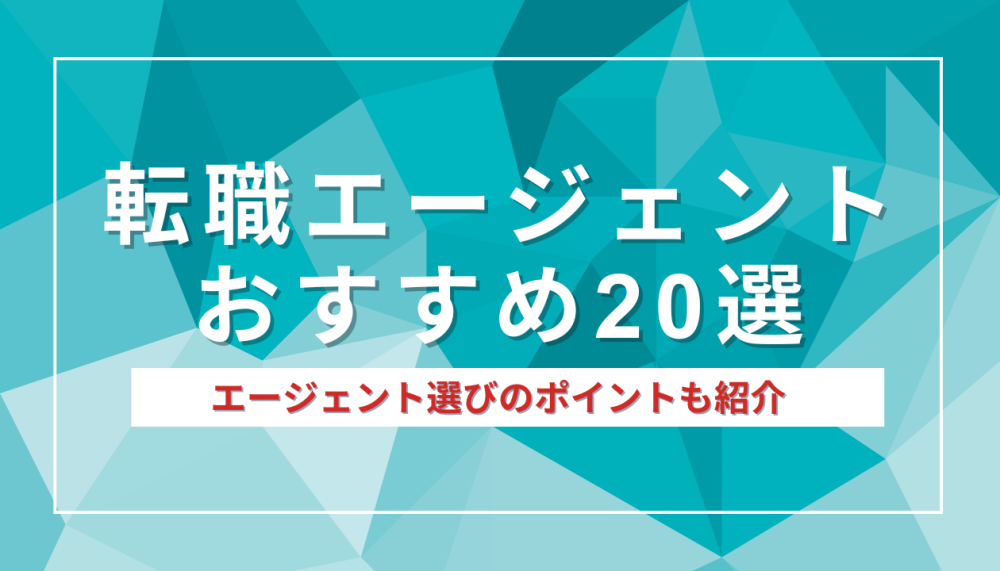
転職エージェントおすすめ徹底比較|2025年最新版完全ガイド
この記事を書いた人

就・転職専門ライター
さりぃ
大学時代は法学を専攻、卒業後は人材紹介企業にて約5年間就・転職専門ライターとして累計1,000本以上の記事を執筆。並行して、第二新卒層をターゲットとした就・転職支援事業のサービスサイトの管理責任者としてWebマーケティングも担当しておりました。
いわゆる「フリーター」というポジションから正社員としての働き方に切り替え、サービスサイトの責任者を任せていただけるまでになった経験を活かし、
就・転職のノウハウだけでなく、「人生の選択肢の多様性」「自身の選択への向き合い方」について発信することで少しでもお役に立てれば幸いです。
同じ条件の就職・転職記事
退職金の平均はいくら?相場は月収の約40カ月分?条件別に解説
退職金の相場は給与の約40カ月分であることが一般的ですが学歴や企業規模、退職理由、勤続年数などによって...
最終更新日:2026.01.29

