- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 転職
- 退職関連
- 【最新】退職金の税金の計算方法を初心者向けにかんたん解説!
【最新】退職金の税金の計算方法を初心者向けにかんたん解説!
本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます
退職金を受け取る際には「所得税」「住民税」が課税されることになりますが、これは受け取る退職金の額によって異なってきます。
本記事では退職金にかかる所得税と住民税の計算方法をわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
この記事のまとめ
- 退職金にかかる税金は「所得税(所得税、復興特別所得税の2種類)」「住民税」
- 退職金にかかる税金の額は、勤続年数や会社から出る退職金の金額によって異なる
→ 横にスクロールできます
【働きやすい仕事を教えてもらうなら】
おすすめ転職エージェント3選
| サービス名 | 公式サイト | おすすめポイント | |
|---|---|---|---|
|
編集部イチオシ 第二新卒エージェントneo |
 |
公式サイト | 未経験者に強い20代特化型! 親身な対応が好評で相談のみでもOK |
| マイナビジョブ20's |  |
公式サイト | 全求人が20代向け!約8割が未経験OK求人 |
| doda |  |
公式サイト | 28万件以上(※2025年12月時点)の求人から探せる |
※右にスクロールするとそれぞれの特徴が掲載されています
そもそも「退職金」とは?
退職金とは労働者が企業を退職する際に受け取ることができるお金のことで、退職手当や退職慰労金とも呼ばれています。
制度の正式名称は「退職給付制度」ですが、一般的には退職金制度と呼ばれており、この制度を取り入れている会社でのみ退職金を受け取ることができます。
退職金は定年退職の時だけでなく、会社都合で解雇された時や自己都合で退職する場合にも受け取れるもので、労働者が亡くなった場合にも適用されます。
退職金制度で得られるお金は主に「退職一時金」「退職金共済」「確定給付年金」「確定拠出年金」の4種類(本記事では「退職一時金」の場合の税の計算方法をご紹介いたします)があり、退職金の受け取り方は「一時金タイプ」「年金タイプ」に大別されます。

退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」
退職金にかかる税金は「所得税」「住民税」の2種類になります。
これらの税金は給与やボーナスを受け取る際にもかかりますが、退職金はその他の所得と区別して課税されるため、税のかかり方が異なります。
まずは前提知識として、所得税と住民税の基本をおさらいしておきましょう。
所得税とは?
「所得税」は個人の所得に対してかかる税金で、一年間における全ての所得から所得控除額を引いた残りの額(課税所得)にかけられます。
所得税の課税方法には「総合課税」「分離課税」の2つが存在します。

退職金(退職所得)は分離課税となるため、その他の所得と分けて課税されることになります。
また、退職金にかかる所得税には「退職所得控除(課税対象となる退職所得額を計算する過程で一部の額が控除される)」が適用され、この金額は勤続年数が長いほど大きくなります。
中でも退職一時金の場合は一度に受け取れる額が多くなりやすいためかかる税負担も大きくなりがちですが、この退職所得控除によって税負担が軽くなるよう配慮されているのです。
【退職所得控除について】
退職所得控除を受けるには「退職所得申告書(所得税法第203条1項各号の定めによる申請書)」を職場に提出する必要があります。
提出後は職場に手続きをしてもらえるため、退職一時金を受け取った後に源泉徴収などを申請する必要はありません。
また、平成25年から令和19年までは所得税に加えて「復興特別所得税(東日本大震災からの復興施策に必要な財源確保のために課されることになった税金)」も納める必要があり、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されます。
住民税とは?
住民税は地方税のひとつで、道府県民税と市町村民税の総称で、教育や福祉、救急、ゴミ処理などの公共サービスのために使用されます。住民税には「均等割」「所得割」があります。

先ほどもお伝えした通り退職金(退職所得)にかかる住民税は分離課税となるため、退職所得が生じた年に他の所得と区別して課税されることになります。
1月1日から5月31日までに退職した場合、基本的には退職月の給与や退職金から5月分までの住民税を一括で徴収されることになります(退職月の給与と退職金の合計よりも住民税額が多い場合は普通徴収に切り替わり、自分で納付することになります)。
6月1日から12月31日までに退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きされる形で会社に徴収されます。
その翌月以降に納付予定の住民税は普通徴収に切り替わるため、自分で納付することになります(この場合は自治体から普通徴収のための納税通知書が届きます)。
退職金にかかる「所得税」の計算方法
ここからは退職金にかかる所得税と住民税の計算方法を見ていきましょう。
まずは所得税についてですが、ここでは「所得税」「復興特別所得税」の2つについてお伝えします(繰り返しになりますが、ここでは退職一時金の場合の税の計算方法をご紹介いたします)。
退職金にかかる「所得税」の計算方法
退職金にかかる所得税額は下記の計算式で求めることができます。
【退職金の所得税額の計算式】
退職金の所得税額
=課税退職所得金額×所得税率-控除額
上記を計算するには「課税対象となる所得金額」「所得税率」「控除額」を知る必要があります。順に把握していきましょう。
(1)退職所得控除額の計算式
まずは「課税退職所得金額(受け取れる退職金のうち、課税対象になる額)」を求めるために「退職所得控除額」を求めましょう(退職金の所得税額の算出式にある「控除額」とは別です)。
(1)勤続年数が20年以下の場合
└勤続年数×40万円
(退職所得控除額が80万円未満の場合には、80万円)
(2)勤続年数が20年以上の場合
└(勤続年数-20)×70万円+800万円
※勤続年数は1年未満の端数を切上げて計算
└例)10年3ヶ月→「11年」で計算
※参考元:人事院「退職手当制度の概要」
(2)課税対象となる退職所得金額の計算式
次に、「課税退職所得金額」を算出しましょう。こちらは(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2で求められます(「退職所得控除額」の部分には先ほど計算した控除額を当てはめましょう)。
具体的な計算式は、たとえば下記のような形となります。
(1)勤続10年、退職金240万円の場合
└(10年×40万円)=400万円
→退職金240万円は控除額400万円以内に収まるため、税金はかからない
(2)勤続30年、退職金2800万円の場合
└(30年-20)×70万円+800万円=1500万円
→1500万円までは税金がかからず、課税対象となるのは(退職金2800万円-1500万円)×1/2=650万円
(3)最終的にかかる所得税を計算しよう
では一番最初にお伝えした、退職金に最終的にかかる所得税を計算しましょう。
【退職金の所得税額の計算式】
退職金の所得税額
=課税退職所得金額×所得税率-控除額
この式にある「所得税率」「控除額」は課税退職所得金額ごとに税法によって定められています。詳しくは国税庁のWebサイトをご参照ください。
退職金にかかる「復興特別所得税」の計算方法
次に、復興特別所得税の計算についてですが、これは上記で導き出された所得税額(基準所得税額)に2.1%の税率をかけるだけで算出することができます。
【復興特別所得税額の計算式】
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
好待遇の求人が豊富!おすすめの転職エージェント3選
退職金にかかる「住民税」の計算方法
次に退職金にかかる「住民税」の計算方法について見ていきましょう。こちらは先ほど算出した「課税退職所得金額」に「住民税率」をかけることで算出できます。
住民税率は課税退職所得金額に関係なく一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)となります。
【住民税額の計算式】
住民税額=課税退職所得金額×住民税率10%
20代に寄り添った転職を支援!

第二新卒エージェントneoは、第二新卒をはじめとした20代に特化した転職支援サービスです。一人ひとり異なる状況、強み、適性、思考を加味し、あなたの初めての転職を支援します。未経験からの転職支援実績も多数!あなたの未来に寄り添い、最適な企業をご紹介します。
退職金にかかる税金の計算例
計算方法を把握していただいたところで、ここからはケース別に実際の計算式をご紹介します。ここでは早期退職したケース、長年勤めて退職したケースを例として見ていきましょう。
【ケース1】勤続年数3年、退職金30万円
まずは勤続年数3年で退職し、退職金が30万円のケースです。「所得税」「復興特別所得税」「住民税」について順に計算していきましょう。
まずは退職控除金額を算出します。前述した計算式に則ると、勤続年数が20年以下の場合は勤続年数×40万円のため、下記の通りとなります。
退職控除金額:3年×40万円=120万円
(退職所得控除額が80万円未満の場合には80万円となるが今回はこのケースに当てはまらない)
この時点で控除額の120万円が退職金の30万円を上回っているため、所得税、復興特別所得税、住民税は非課税となります。
【ケース2】勤続年数24年3ヶ月、退職金2,200万円
次に、勤続年数24年3ヶ月で退職金が2,200万円のケースです。
所得税の計算例
まずは所得税を算出するにあたって控除額を計算しましょう。今回は勤続年数24年3ヶ月ということで、控除額を算出するにあたっては端数を切り上げて25年扱いとします。
勤続年数が20年を越えているため、所得税の控除額は下記の計算式で求めることができます。
退職控除金額:(25年(勤続年数)-20)×70万円+800万円
=1150万円
控除額は1150万円であることがわかったため、次に課税退職所得額を算出します。
課税退職所得額:(退職金額 2,200万円-退職所得控除額1150万円)×2分の1
=525万円
あとは所得税額を求める式に必要な情報を当てはめるだけです。
上記でもお伝えした国税庁のデータによれば、課税退職所得額が525万円の場合の所得税率は20%、控除額は42万7,500円となっているため、このケースの所得税額は下記の通りとなります。
所得税額:課税退職所得額575万円×税率20%-控除額42万7,500円
=72万2,500円
復興特別所得税の計算例
次に復興特別所得税の計算について見ていきましょう。先ほど算出した所得税額に2.1%をかけることで求められます。
復興特別所得税額:基準所得税額72万2,500円×2.1%
=1万5,172円
住民税の計算例
最後に住民税の計算をしていきましょう。こちらは先ほど算出した「課税退職所得金額」に住民税率10%をかけることで求めることができます。
住民税額:課税退職所得金額575万円×住民税率10%
=57万5,000円
これで退職金にかかる税金が把握できたことになります。ぜひご自身が受け取れる退職金について計算してみてください。
ちなみに、今後転職を考えていてまだ企業が決まっていないという場合にはできるだけ早く見つけるのがベターです。というのも、退職後のブランクが長くなればなるほど企業から内定が出にくくなる傾向があるためです。
「なかなか内定が出ずに困っている」「どんな企業を選べば良いのかわからない」という方は転職エージェントに相談するのが非常に便利です。
転職相談だけでなく求人紹介や選考対策などを講じてもらえるほか、サービスによっては企業へ推薦してくれる場合もありますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
20代に寄り添った転職を支援!

第二新卒エージェントneoは、第二新卒をはじめとした20代に特化した転職支援サービスです。一人ひとり異なる状況、強み、適性、思考を加味し、あなたの初めての転職を支援します。未経験からの転職支援実績も多数!あなたの未来に寄り添い、最適な企業をご紹介します。
もしまだ転職先が決まっていないという方は、下記で紹介しているような転職エージェントで求人を探すのが効率的で便利ですのでぜひ参考にしてください。
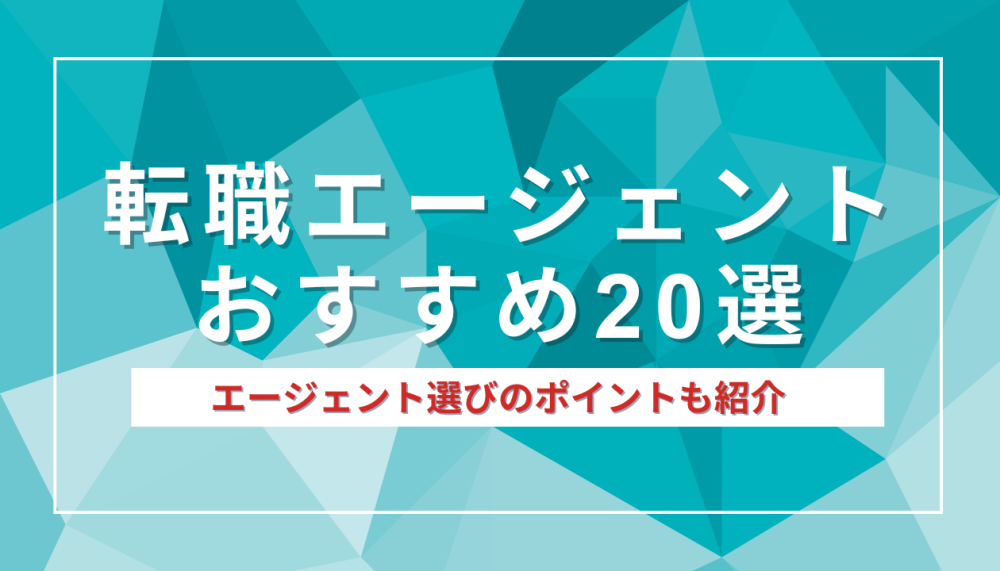
転職エージェントおすすめ徹底比較|2025年最新版完全ガイド
この記事を書いた人

就・転職専門ライター
さりぃ
大学時代は法学を専攻、卒業後は人材紹介企業にて約5年間就・転職専門ライターとして累計1,000本以上の記事を執筆。並行して、第二新卒層をターゲットとした就・転職支援事業のサービスサイトの管理責任者としてWebマーケティングも担当しておりました。
いわゆる「フリーター」というポジションから正社員としての働き方に切り替え、サービスサイトの責任者を任せていただけるまでになった経験を活かし、
就・転職のノウハウだけでなく、「人生の選択肢の多様性」「自身の選択への向き合い方」について発信することで少しでもお役に立てれば幸いです。
同じ条件の就職・転職記事
退職金の平均はいくら?相場は月収の約40カ月分?条件別に解説
退職金の相場は給与の約40カ月分であることが一般的ですが学歴や企業規模、退職理由、勤続年数などによって...
最終更新日:2026.01.29

