- キャリアトラスTOP
- 就職・転職記事をカテゴリから探す
- 転職
- 退職関連
- 休職のメリット・デメリットは?給料や過ごし方についてもご紹介
休職のメリット・デメリットは?給料や過ごし方についてもご紹介
本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます
この記事のまとめ
- 休職中は無給となるが、病気やケガで休業する場合には、傷病手当金を受け取ることができる
- 休職中であっても社会保険料は支払わなければならない
- 休職することで、ストレスから解放され、治療に専念でき、将来について冷静に考えることができるようになる
- 休職中は、「深く考え込まずにゆっくり休む」「生活リズムを整える」「好きなことを楽しむ」ことが大切である
仕事や人間関係のストレス、体調不良といった様々な理由で休職を検討している人がいるのではないでしょうか。
本記事では休職することのメリットやデメリット、休職中の過ごし方についてご紹介していきますので、休職を考えるうえでの参考にしてみてください。
→ 横にスクロールできます
【丁寧でサポート内容が良質】
おすすめ転職エージェント
| サービス名 | 公式サイト | おすすめポイント | |
|---|---|---|---|
|
編集部イチオシ 第二新卒エージェントneo |
 |
公式サイト | 親身で丁寧な対応が魅力 書類選考通過率94.7% |
| doda |  |
公式サイト | 28万件以上(※2025年12月時点)の求人から探せる |
| マイナビジョブ20's |  |
公式サイト | 全求人が20代向け!約8割が未経験OK求人 |
※右にスクロールするとそれぞれの特徴が掲載されています
休職とは?

休職とは、「仕事とは関係のない自分の都合」により長期間休みたい場合に会社に籍を置きながら休める制度」のことをいいます。
休職には法的な定めがないため企業ごとに休職制度の要件は異なります。また、休職期間中の賃金支払いの義務はなく無給になることが一般的です。
ここで期間や休職できる状況について詳しくみていきましょう。
休職できる期間は?延長は可能?
法律による明確な規制やルールなどはなく、会社がそれぞれ定めた就業規則に従って運用されているため期間や延長の可否は会社次第ですが、『独立行政法人「労働政策研究・研修機構」』の調査によると、中小企業では期間を1年未満としている会社が約半数を占めるのに対し、大企業では1年半~3年未満としている会社が約60%となっており、大企業ほど長く休める可能性が高いようです。
休職期間は勤続年数によって上限が異なることもありますので、会社の就業規則を確認しておきましょう。
休職ができる状況とは?
就業規則で定められた範囲内の理由であれば休職をすることができます。ここでは、代表的な休職例を3つご紹介します。
「傷病休職」
・業務とは関係ないケガや病気で働けなくなり、療養が必要になったケースなどが該当
・仕事を休んだ方が良いという主治医の判断を記した「診断書」を、会社に提出する必要がある
・うつ病など精神的な病気で仕事を休む人も多い
「自己都合休職」
・災害時のボランティアや青年海外協力隊への奉仕活動、専門学校への通学などが該当
・ケガや病気以外の自分の希望で休職するケースもここに含まれる
※社会貢献や地域支援といった重要な意義もあるため、休職期間中給与が支給される会社もある
「留学休職」
・海外で本格的に言語や技術などを学びに行くケースが該当
※留学終了後は復職して得たスキルを仕事に活かすことができる
※業界や職種によっては、留学休職を積極的に認めている会社もある
休職のデメリット4選

会社の規定内であれば休職できることが分かりました。では休職することによるデメリットはあるのでしょうか。
休職中は収入がない
1つ目のデメリットは、収入が得られないことです。法律上、休職中の従業員に対する給与の支払い義務は企業に課せられていないため、休職中は給与が一切出ないのが一般的です。
ただし、休職理由が病気の療養の場合には、健康保険組合から傷病手当金として休職前の給与の2/3が支給されます。療養以外の場合には無収入となるため、休職中の生活費などを考えるとデメリットといえるでしょう。
傷病手当金の受給要件
-
下記に当てはまる場合、傷病手当金を受給することができますので確認をしておきましょう。
(1)業務外のケガ・病気の療養が理由である
(2)働けない状態である
(3)連続する3日間を含み、4日以上仕事を休む
(4)休んでいる間、無給である
※全て満たす必要あり
受給できる期間は支給開始から1年6ヶ月です。
申請の手続きは職場を通して行いますので、「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。
【休業手当、傷病手当・傷病手当金の違い】
似たような言葉の手当がありますので、下記の違いを確認しておきましょう。
(1)休業手当とは?
業績悪化やストライキなどの会社の責任によって休業することになった場合に受け取れる手当
(2)傷病手当とは?
退職後、ハローワークに求職の申し込みをした後にケガ・病気が原因で15日以上継続して働けない場合に受け取れる手当
※雇用保険から支給される
(3)傷病手当金とは?
健康保険に病気やケガによって休職する場合に受け取れる手当で給料の代わりに支給される手当
※健康保険から支給される
社会保険料の支払いは継続する
休職のデメリットの2つ目は、休職中であっても社会保険料は支払わなければならないということです。社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険のことです。
休職中は給料は発生しなくとも会社に籍をおいている状態ですので、従業員としてみなされるため、社会保険料は変わらず発生することとなります。
支払い額は休職前と基本的に同額で通常は給料から天引きされるのですが、休職中は無給となるため、会社の指示に従い自分で振り込む必要があります。
このように休職中は金銭的なデメリットが多いといえます。
人事評価に影響する可能性がある
3つ目に人事評価に影響する可能性があるということです。特に、遅刻や欠勤などが評価基準に組み込まれている企業の場合、休職が人事評価に影響する可能性は十分にあります。
私用により長期間休業した場合、復職後に担当業務が変更となり評価ポイントが以前と変わり昇進・昇格が難しくなってまう、うつ病などの病気を理由に休職した場合、病気の再発を恐れ、あえて復職後は負荷をかけないためか昇格できなってしまうというケースが考えられます。
もちろんすべての企業が、復職後の人事評価に影響を与えるとは限りませんし、上記のような例はあまり多くはないと思いますが、企業や上司によってはこのような例もあるということを頭に入れておきましょう。
復職できない可能性もある
復職できない可能性がある点にも要注意です。『独立行政法人 労働政策研究・研修機構』が平成25年に行った調査によると、病気により休職した社員の復職率は平均51.9%という結果でした。
病気の種類にもよりますが、休職をした人の約2人に1人は復職できず退職しているということです。復職にあたって会社の支援がなかったり、「同僚や上司に迷惑をかけてしまった」「復職しても視線が気になる」などプレッシャーを感じたりして、復職を諦めてしまうケースもあります。
休職にはこのようにさまざまな注意点があるため、じっくり検討してから休むかどうかを考えましょう。
もし今後職場を変えることを前提に考えている場合は、下記の「第二新卒エージェントneo」などの転職エージェントに相談して転職先にあたりをつけたり今後の道筋を考えたりしてから休職するかを検討するのも良い方法です。
休職すべきかお悩みなら

休職しようか検討している方の中には「転職して環境を変えたほうが良いのでは」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。第二新卒エージェントneoは20代に特化した転職支援サービスで、一人ひとりの希望、状況、適性に併せて精神的に安定して働きやすい仕事をご紹介します。無理な求人提案は一切ありませんのでまずはご相談ください(完全無料)。
休職のメリット4選
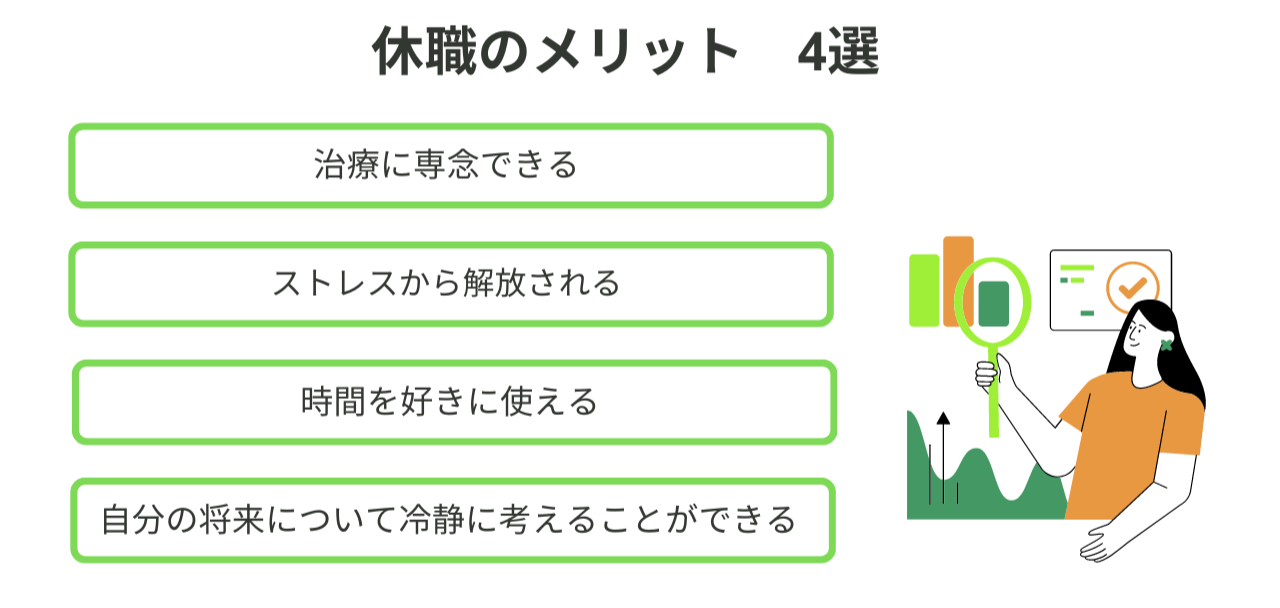
ここでは休職することのメリットについてお伝えしていきます。
治療に専念できる
身体的な病気やうつ病などの精神的な病の場合、休職することによって治療に専念することができます。仕事をしながら治療をしようとしても、多忙で通院することも難しく治療を後回しにしてしまい、完治するまでにかなりの時間がかかってしまうことも少なくありません。
しかし、休職して治療だけに専念できる十分な時間を確保することによって、自分の心と体のケアだけに集中することができるため、回復を早めることができるでしょう。
ストレスから解放される
2つ目は、ストレスから解放されることです。休職の理由が仕事や人間関係へのストレスの場合、ストレスから解放され快適な時間を過ごすことができます。
ストレスを貯め込み過ぎるとうつ病などの病気を発症してしまう可能性も考えられます。業務過多で体調の異変を感じている場合には、数週間でも良いので休職し、コンディションを整える時間を作ると気持ちが軽くなり、前向きに考えることができるようになるでしょう。
時間を好きに使える
3つ目のメリットは、自由に時間を使えることです。日々業務に追われていると趣味やプライベートの時間を取ることが難しいですが、休職することで自分の好きなことに時間を費やすことができます。
休職の理由にもよりますが、病ではなく自主都合の休職の場合にはリフレッシュを含めて小旅行に出かけるなどし、心に余暇を与えるのも良いでしょう。
自分の将来について冷静に考えることができる
残業が多いなどのハードワークを行っている場合には、毎日仕事のことばかりで休みの日は仕事の疲れが取れず、1年中頭の中に仕事がある状態になっている可能性があります。このような状態では、落ち着いて将来のことを考える時間が取れません。
しかし、休職することによって、仕事から離れることで時間に余裕が生まれ、今の状況を客観視することができ、冷静に将来について考えることができるでしょう。
ちなみに休職中に転職活動を行うことは法律上問題ありませんが、就業規則違反や心身の体調悪化の可能性、転職先に知られてしまうリスクなどに注意しましょう。就業規則上問題ない場合は「第二新卒エージェントneo」などの転職エージェントに相談することで、心身への負担を最小限に留めながら転職先を探すことが可能です。
心身のストレスが少ない職場と出会えるおすすめ転職エージェント3選
第二新卒エージェントneo |
未経験者歓迎求人が豊富!親身で丁寧なアドバイザーが魅力の20代特化型転職エージェント |
|---|---|
doda |
業界最大級の支援実績で求人豊富!企業ごとの担当者から情報を得られる転職エージェント |
マイナビジョブ20's |
全求人が20代向け!約8割が未経験OK求人の20代向けの転職エージェント |
休職する手順

休職は社員の権利ではなく、あくまでも福利厚生の一環として会社が独自に認めてくれている「解雇の猶予期間」ですので、長期的に仕事を休みたい場合は会社が定めるルールに従い手続きを行いましょう。
ここでは、一般的な手順を紹介しますので参考にしてみてください。
1.会社の休職制度について確認する
休職の細かいルールは、会社ごとに異なります。まずは、期間・休職中の給与の取り扱い・必要書類・復職後の支援体制などについて確認してみましょう。中には休職制度自体が存在しない会社もありますので、そもそも制度があるのかどうかも事前に確認しておきます。
2.診断書を提出する
休職するケースで最も多い理由は病気やケガです。そのため、休職を申し出た際に「診断書」の提出を求められることがあります。
診断書とは患者の症状や診断内容、治療などについて医師のみが作成できる書類のことをいい、作成してもらうためには、2,000~1万円ほど費用がかかります。
うつ病を発症したなどの精神疾患の場合も診断書を提出することで休職することが可能となりますので、身体への不調を理由に休職する場合には、必ず診断書を用意しましょう。
会社によっては診断書のフォーマットが決まっているケースもありますので、事前に確認をしておきます。
3.上司に休職したい旨を伝える
診断書の準備ができたら、会社に休職したいことを報告します。いずれ復職を考えているなら、直属の上司との関係悪化は避けたほうが無難ですので、人事部ではなく、まずは直属の上司に伝えましょう。
上司に相談することで、休職を考える程人間関係が悪化している、オーバーワークであるということが分かると、何らかの対処をしてくれる可能性も充分に考えられます。
場合によっては労働環境が改善し、休まずに事態を乗り越えられることもあるでしょう。ただし、上司との関係悪化が原因の場合には、この限りではありません。
4.必要書類を提出する
上司や会社との話し合いで休職が決定したら、休職に必要な書類を提出します。一般的には「休職願」など会社所定の申請書と「診断書」の2種類が必要になることが多いです。
すでに仕事を休んでいる場合は、必要書類を郵送で送ります。会社が必要書類を受け付けた段階で正式に休職が認められるため、できるだけ早く、不備のない状態で提出することが大切です。
休職中の過ごし方

ここでは休職中のおすすめの過ごし方についてお伝えしていきます。休職中の過ごし方によって今後の生き方が変わってくるかもしれません。
ストレスなどが原因で休職をしている場合を想定してお伝えしていきますので、参考にしてみてください。
深く考えずにゆっくり休む
休職してすぐの時期は、精神的にも肉体的にもまずはしっかり休むことが大切です。
今まで仕事に奔走してきたことにより疲労が貯まっているため、思考力や適切な判断力が低下しています。また、休職に対して罪悪感を覚えやすく、急に働かない環境に移ったことであれこれ悩んで沈みがちになる可能性も考えられます。
休職し始めたばかりの時期は、どうしても復職後のことや会社のことが気になってしまいますが、まずは心や体の状態がある程度よくなるまではできるだけ深く考えずに、仕事のことは忘れて自分の心と体のケアに専念しましょう。
生活リズムを整える
毎晩遅くまで仕事をする習慣がついている人はどうしても夜型の生活になりがちです。仕事から離れ心も少しずつリフレッシュし始めたら、健全な生活リズムを取り戻しすがすがしい一日を送ることができるように意識をしましょう。
具体的には、少しずつ起床・就寝時間などの生活リズムを整え、散歩など適度な運動も行います。食事も朝・昼・晩と日本食を意識し、野菜なども積極的に取り入れるようにしていくと良いでしょう。
このように生活リズムを整えることで体内のホルモンバランスも保たれやすくなり、生活習慣病やうつ病の予防ができます。休職前は気分が落ち込んでいたという人の場合は特に有効です。
好きなことを楽しむ
休職していることにも慣れ、少しずつ本来の自分を取り戻すことができたと感じたら、自分の好きなことを思いっきり楽しみましょう。
映画を観る、ショッピングをする、ドライブをするなどどんなことでも構いません。自分が好きなことをたくさん楽しみ、乾いた心をしっかり潤していきましょう。
客観的に将来について考える
最後に自分が将来どうしたいのかを冷静に考え直します。今の会社で働き続けたいのか、それとも他の企業に転職をしたいのか、自分がやりたい仕事はどんな仕事なのか、などリフレッシュされた頭で自分の本音と向き合う時間を作ると良いでしょう。
仮に復職を考える場合には、休職に追い込まれるほど大変だった要因を突き止め、改善する手立てを考えてみてください。今すぐには働けないと考えるのであれば、それも一つの選択肢です。
もう一度働きたいと感じたときに、万が一会社員として採用されることが難しかったとしても、職種によっては在宅で一人でできる仕事など様々な選択肢があります。まずは冷静に客観的に将来について考える時間も取ることをおすすめします。
転職すべきかお悩みの方におすすめの転職エージェント3選
最後に、おすすめの転職エージェントをご紹介しますのでぜひ参考にしてください
第二新卒エージェントneo|未経験者に強い!20代の様々な経歴に特化

参照元:第二新卒エージェントneo
| 対応エリア | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫、愛知、三重、岐阜、広島、福岡 |
|---|---|
| オンライン対応 | 可 |
| 主な特徴 | 20代の中でも第二新卒・高卒・中卒・既卒・フリーターそれぞれに特化、18~28歳までの就職・転職支援実績22,500人、面談実施件数34,000件、最短6日で内定、1名あたりのサポート時間平均8時間 |
| 公式サイト | こちらをクリック |
「第二新卒エージェントneo」は主に20代に特化した就職・転職エージェントです。
18~28歳までの就職・転職支援実績22,500人、面談実施件数は34,000件を誇り、第二新卒のほか、既卒、フリーター、高卒、中卒などのあらゆる方に対応しているため20代前半の方の転職にぴったりです。
未経験歓迎求人を数多く取り扱っている点が特徴で、新しい業界・職種へのキャリアチェンジ成功事例も豊富で、「そもそも休職すべきか、それとも転職すべきか」という点から相談に乗ってもらえます。
最短6日で内定が出るケースもありますので「今すぐ就職・転職したい」という方もぜひ利用してみてください。
このエージェントのおすすめポイント
- 18~28歳までの就職・転職支援実績22,500人、面談実施件数34,000件を誇る
- 20代の中でも第二新卒・高卒・中卒・既卒・フリーターそれぞれに特化
- 職務経験なしの就職・転職支援実績は10,000人を突破
- 最短6日で内定が出る可能性あり
- 1名あたりのサポート平均時間は8時間で親身なサポートを受けられる
doda|求人数が豊富で転職サイト機能も充実
業界最大級の28万件以上(※2025年12月時点)
の求人を誇るdodaは転職エージェント・求人サイト・スカウトサービスを一体化させた転職サービスで、
2024年オリコン顧客満足度Ⓡ調査「転職エージェント 20代」第1位を獲得するなど、転職希望者から高い支持を得ています。
転職サイトとエージェントの2つの機能を併せ持つこともあり、求人数の多さが魅力です。
doda
| 対応エリア | 全国+海外 |
|---|---|
| 主な特徴 | 2024年 オリコン顧客満足度®調査 転職エージェント 20代 第1位 転職エージェント、求人サイト、スカウトサービスがまとめて利用できる 専属のキャリアアドバイザーによる丁寧なサポート |
| 求人数 | 28万件以上 (※2025年12月時点) |
| おすすめの年代 | 25歳~39歳 |
| アプリ | 〇 |
| LINE・チャット | 〇 |
| 書類作成サポート機能 | 〇 |
| 選考スケジュール管理 | 〇 |
| 面談方法 | オンライン/電話 |
| 公式サイト | 詳細はこちら |
サービスを利用した人の生の声
ここからは、実際にエージェントサービスを利用した方への取材を元に、より詳しいサービスの内容をお届けします。
実際に「doda」のサービスを使ってみて印象的だった点はありますか?

「doda」はキャリアアドバイザーの他に、応募する企業ごとに担当が分かれていて、それぞれの担当者から詳細な情報を聞けた点が印象に残っています。
企業ごとに担当者がいるんですね!複数の担当者と連絡を取るのは大変ではありませんでしたか?

確かにたくさん応募すると少し大変ではありますが、dodaは公式LINEで気軽にやり取りできたので、やりにくさはさほど感じませんでした。
企業ごとの担当者から詳しい情報をもらえる!
dodaはキャリアアドバイザーと企業側の担当者の分業制が進んでおり、企業ごとに窓口が異なります。
そのため、その企業の詳しい仕事内容や雰囲気、対策情報などより詳しい情報を得られるでしょう。
担当者ごとに連絡を取り合う必要があるため、自身でスケジュール管理ができる方や連絡がマメな方であれば有効活用することができるはずです。
このエージェントのおすすめポイント
- 顧客満足度No.1 (※2024年オリコン顧客満足度®調査 転職エージェント 20代 第1位)
- 業界最大級の豊富な求人数が魅力
- 企業から直接スカウトを受け取れる
- 専属のキャリアアドバイザーによる丁寧なサポート
マイナビジョブ20's|20代向け、求人の76%以上が未経験OK

「マイナビジョブ20's」は株式会社マイナビ唯一の20代向けの転職エージェントで、年間約75,000人の20代が登録しています。利用者数は430,000人、全ての求人が20代向けであり、その76%以上が未経験OK求人となっています。
サービス概要
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 主な特徴 | 利用者数430,000人、全求人20代向け、未経験OK求人76%以上、定着率95.5%、適性診断を受験可能 |
| おすすめの年代 | 20代前半 |
| アプリ | ○ |
| LINE・チャット | ○ |
| 書類作成サポート機能 | ○ |
| 選考スケジュール管理 | ○ |
| 公式サイト | 無料で転職相談してみる |
面談内容
| 面談可能日・時間 | 平日の10:00~19:00スタートまで |
|---|---|
| 最短可能予約日 | 登録の当日から可能 ※1 |
| 面談方法 | 来社/WEB/電話 |
| 面談時間 | 30分 ※2 |
| 面談の流れ・内容 | ①転職活動の進め方の説明 ②転職理由のヒアリング ③希望のヒアリング ④質疑応答 ※2 |
※2:本サービスを利用した方からの取材に基づく内容を掲載しており、必ず同じサービスを受けられることを保障するものではありません。
サービスを利用した人の生の声
ここからは、実際にエージェントサービスを利用した方への取材を元に、より詳しいサービスの内容をお届けします。
実際に「マイナビジョブ20's」のサービスを使ってみて印象的だった点はありますか?

アプリの機能が充実していて便利だったことが印象的でした。
そうなのですね!具体的にどんなところが便利でしたか?

アプリに求人検索機能がついていて、アドバイザーさんからの紹介だけでなく、自分でも自由に求人を探せる点が便利でした。
また、スカウト機能がついていて企業から直接スカウトを受け取れる点も良かったです。
▼アプリ画面のキャプチャ

スカウトや求人検索などアプリの機能が充実!
「マイナビジョブ20's」の魅力は公式アプリの機能の充実度です。
企業から直接スカウトを受け取れる機能や、求人検索、入学・卒業年度自動計算ツールなど、便利な機能がたくさんついています。
在職中で忙しい方など、隙間時間に気軽に転職活動をしたいという人にはおすすめのサービスといえます。
サービスを利用する際のポイント
- 20代向けの転職エージェント
- 営業や接客、SESのITエンジニアなど、未経験歓迎の求人を豊富に保有
- アプリの機能が充実しており、空いた時間でサクッと転職活動を進めたい人にはおすすめ
- キャリアアドバイザーと密に連携を取りながら転職活動をしたい人は「第二新卒エージェントneo」などの転職エージェントを併用するのがおすすめ
休職すべきかお悩みなら

休職しようか検討している方の中には「転職して環境を変えたほうが良いのでは」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。第二新卒エージェントneoは20代に特化した転職支援サービスで、一人ひとりの希望、状況、適性に併せて精神的に安定して働きやすい仕事をご紹介します。無理な求人提案は一切ありませんのでまずはご相談ください(完全無料)。
この記事を書いた人

キャリアアドバイザー
しょん
キャリアトラスのプロダクトマネージャー 1992年生まれ。大学卒業後東証一部上場の飲食企業にてエリアマネージャーを経験し、株式会社ネオキャリアに転職。キャリアアドバイザーを経験したのちSEO業務に従事し約5年。サイトの立ち上げから行い、現在は600本を超える記事、7名の編集チームを管理しながら運営を行っております。 自身での転職経験はもちろん、会社の規模としても東証一部上場企業、10人に満たないベンチャー企業、3000人を超える規模の会社を経験しています。これらの経験を元にライフワークバランスや多様な働き方、キャリア形成まで様々な視点から信頼できる情報提供を行うことをお約束します。


